2019.11(第188回)秋川の古刹を巡る散策
2019年11月17日
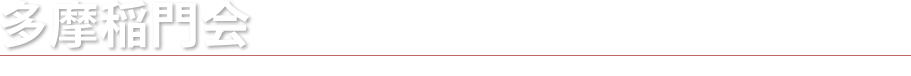
 武蔵五日市駅から10分弱戸倉バス停で下車した。街道の向かい側に野崎酒造の塀が遠くに見える。東京の10軒の酒造業者の一つであり、金子さんのお薦めの酒でもあった。
武蔵五日市駅から10分弱戸倉バス停で下車した。街道の向かい側に野崎酒造の塀が遠くに見える。東京の10軒の酒造業者の一つであり、金子さんのお薦めの酒でもあった。 バス停から少し戻り右折して坂道を上る。途中、炭焼きの設備かと思うような石組の釜のようなものがある。何だろうとみていると、向かいの家の人が、これは野崎酒造の仕込水に利用する伏流水をくむ井戸だと教えてくれた。上の斜面の畑は、猪で掘り返えされている。坂道は急坂となり、最初のポイントである光厳寺の高台に辿りついた。
バス停から少し戻り右折して坂道を上る。途中、炭焼きの設備かと思うような石組の釜のようなものがある。何だろうとみていると、向かいの家の人が、これは野崎酒造の仕込水に利用する伏流水をくむ井戸だと教えてくれた。上の斜面の畑は、猪で掘り返えされている。坂道は急坂となり、最初のポイントである光厳寺の高台に辿りついた。 光厳寺は、1334年足利尊氏によって開基された五日市では最古の寺ある。背後にある山は室町時代から戦国時代にかけて築かれた戸倉城跡で、大石定久の隠居城としても使われていた。
光厳寺は、1334年足利尊氏によって開基された五日市では最古の寺ある。背後にある山は室町時代から戦国時代にかけて築かれた戸倉城跡で、大石定久の隠居城としても使われていた。 食事の後、ここから通行止めが開放された下の遊歩道に降り佳月橋に向かう。道は整備されてはいるが、岸辺には倒木の残骸が至る所に散在し、台風禍の大きさがうかがえる。日陰は寒さを感じるが、歩きはじめると程よく暖かくなってくる。風もなく快晴の絶好のハイキングであるが、遊歩道は雨の影響で滑りやすくなっていた。
食事の後、ここから通行止めが開放された下の遊歩道に降り佳月橋に向かう。道は整備されてはいるが、岸辺には倒木の残骸が至る所に散在し、台風禍の大きさがうかがえる。日陰は寒さを感じるが、歩きはじめると程よく暖かくなってくる。風もなく快晴の絶好のハイキングであるが、遊歩道は雨の影響で滑りやすくなっていた。 佳月橋から両岸が見渡される。紅葉する秋川の上流には、最初に訪れた光厳寺背後の城山(戸倉城跡)の頂が遠望できる。
佳月橋から両岸が見渡される。紅葉する秋川の上流には、最初に訪れた光厳寺背後の城山(戸倉城跡)の頂が遠望できる。 広徳寺は1373年に創建され、茅葺の山門は室町期の面影を留め、堂々たる風格を漂わせている。山門をくぐると見事なイチョウの巨樹が左右に並んでいる。イチョウは黄葉の時期となり、振り返る姿は高く一見の価値があった。2本の大イチョウの間を進むと右側に鐘楼、前面に本堂が位置していた。
広徳寺は1373年に創建され、茅葺の山門は室町期の面影を留め、堂々たる風格を漂わせている。山門をくぐると見事なイチョウの巨樹が左右に並んでいる。イチョウは黄葉の時期となり、振り返る姿は高く一見の価値があった。2本の大イチョウの間を進むと右側に鐘楼、前面に本堂が位置していた。 茅葺の本堂の屋根には北条氏の家紋である三つ鱗が見える。本堂の横には池があり、裏には都内最大といわれるタラヨウが構え、実を一斉につけ赤く色づいていた。また、更に進むとカヤの巨木があり、どちらも都の天然記念物に指定されている。境内から出て秋川に向い下って行く。佳月橋の一つ下流にある小和田橋に向かう。
茅葺の本堂の屋根には北条氏の家紋である三つ鱗が見える。本堂の横には池があり、裏には都内最大といわれるタラヨウが構え、実を一斉につけ赤く色づいていた。また、更に進むとカヤの巨木があり、どちらも都の天然記念物に指定されている。境内から出て秋川に向い下って行く。佳月橋の一つ下流にある小和田橋に向かう。 武蔵五日市駅の売店で、地元酒造の「喜正」をそれぞれ買い求めた。これも金子さんに教えられ恒例となってしまった。立川駅から居酒屋「磯村水産」に入り、先ずは生ビールで乾杯。今日一日快晴の秋空に恵まれ、楽しい一日を過ごすことができた。
武蔵五日市駅の売店で、地元酒造の「喜正」をそれぞれ買い求めた。これも金子さんに教えられ恒例となってしまった。立川駅から居酒屋「磯村水産」に入り、先ずは生ビールで乾杯。今日一日快晴の秋空に恵まれ、楽しい一日を過ごすことができた。