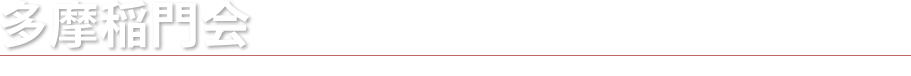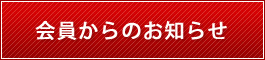Author Archive
第132回 「南高尾・草戸山」 (2012/12/15)レポート
12/15(土)に実施した山歩きの会 【南高尾・草戸山】レポート は、以下の通り・・・
(さらに…)
いねの会 12/18(火) 例会です~♪
1月のテニスコートが決まりました。
山歩きの会 12/15 例会です!
 今年も、余すところ20日となりました。12月の「山歩きの会」は、恒例となりました忘年山行です。 標高差の少ないハイキングが楽しめます。年末の忙しい中とは存じますが、同日の忘年会も、併せて ご案内いたしますので、ご参加下さいますよう お願いいたします。シモバシラの花は、温暖化のため観察できない可能性が多々のために、いつもと違うコースとしました。 ▲同上画像Click>Enlarge(動画)
今年も、余すところ20日となりました。12月の「山歩きの会」は、恒例となりました忘年山行です。 標高差の少ないハイキングが楽しめます。年末の忙しい中とは存じますが、同日の忘年会も、併せて ご案内いたしますので、ご参加下さいますよう お願いいたします。シモバシラの花は、温暖化のため観察できない可能性が多々のために、いつもと違うコースとしました。 ▲同上画像Click>Enlarge(動画)
(さらに…)
食べ~飲み~楽し~グルメの会(2012/11/28)
【いねの会2012点描】WEB
【いねの会2012点描WEB】を、更新しました。
こちらをクリックして、いねの会の楽しい雰囲気を写真で ご覧ください。
※)「いねの会(カラオケ)」の紹介文も、読み易く更新しました。(2012/12/12)
「いねの会10周年記念パーティ」 WEB
去る10月16日(2012年)、盛大に開催された「10周年記念パーティ」の様子を、WEB で公開しました。
ご覧下さい (こちらクリック) ⇒ いねの会10周年記念Party 《10/23 編集:HP活性化委員会》
いねの会:今後の定例会(12月~1月)
【定例会】
●クリスマスパーティー(12月):
12月18日(火), 於=カラオケスナック「麗」, 開始=12時~, 参加費=¥3,000
●新年会(1月):
1月15日(火), 於=「渋谷シダックス」, 集合=渋谷「西武百貨店A館入口」 11時50分,
参加費=¥5,000
以上、お申込みは事前に世話人= 金谷 E-mail / Tel ・ 橋本 E-mail / Tel まで、
お願い致しします。
「雪国文学散歩」の誘い
小さな旅(2013/1/17~18)企画 雪国文学散歩(越後湯沢)に、多数の方の参加お待ちしています。
⇒ ・詳細こちらクリック→ 雪国文学散歩 / ・お申込み先→ 多摩稲門会HP委員:Hombo_Kazuo
盛り上った東京三多摩支部大会
東京都下26の早稲田大学校友会が11月18日午後1時半から多摩市の京王プラザホテル多摩で東京三多摩支部大会を開催した。多摩稲門会からも40名を超える会員が参加した。大会は第一部が式典、第二部が男性合唱の東京稲門グリーンクラブの演奏会、続いて藤嶋昭東京理科大学学長による「研究も教育も感動からー光触媒を例として」という演題の講演、第三部が懇親会で、午後5時半過ぎに閉会となった。
(さらに…)