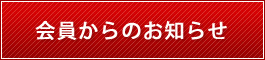Author Archive
今年も美味しい「こそば」が食べられそうです。
非公式サークルですが「こそばの会」から美味しいお蕎麦のお話しです。
妙高の山里にひっそりと可憐な花を咲かせる希少品種の「こそば」がすくすくと育っています。
今夏はとくに暑かったせいか実りが良いようです。(注:そばは水を嫌いからっとした土地が好き)
10月22~23日ごろ刈り取る予定ですが、その後乾燥させて11月半ばには製粉できますのでいよいよ新そばの美味しい季節となります。
今年も12月4日(日)に永山の「はなわ」でそば打ち会を予定しています。
詳細が決まり次第、ご連絡いたしますのでご期待ください。
お問合せ:依田敬一 yodak1jp@yahoo.co.jp
第42回多摩稲門会文化フォーラム 秋の懇親会開催
平成23年9月29日(木)
“多摩稲門会「第42回文化フォーラム・懇親会」報告書
日 時:平成23年9月24日(土) 14時~18時
場 所:京王クラブ(多摩市関戸)
文化フォーラム:講師 浅井隆夫氏(1973年政経学部卒、元朝日新聞政治部記者)
テーマ:「宰相 大平正芳を語る 政治再生への道」
佐藤会長が所用で欠席のため、加来副会長の挨拶があり、このたび当多摩稲門会に大学校友会より、「三多摩支部多摩稲門会~」と染め抜いた横断幕と幟2本の寄贈があったことの報告、披露あった。シンボルとして今後イベントなどに大いに活用して行きたい。
川面副会長・フォーラム担当より講師浅井隆夫氏の当初の講演予定が3月で、「東日本大震災」の影響で今日に延びた経緯が話された。
テーマはこの8月に誕生した校友の野田佳彦首相のスタートと重なり誠にタイムリーな企画となった。最初に野田首相の大平観を、最近の出版物での記事を披歴しながら、その政治認識では「地道な政治」「信頼と合意」を旨とする大平正芳の行動指針に強い共感を持っていることが分かった。浅井さんは大平正芳の施政と人となりを10項目に亘り、資料を踏まえながら理路整然、訥々と語られた。大平首相の当時を知る者は一見「アーウー」の分かりづらいイメージが強かったが、本人がこんなにも深く考え、慎重であったことを初めて知る思いであった。浅井さんの語り口も坦々と穏やかで、聞いているものを肯かせるに充分であった。大向こう唸らせ拍手喝采を得た政治家は強いインパクトがあるが、大平正芳はその反対側におり、じっくりと現状認識のもと次に踏み出す政治家であったといえよう。混迷する政治の中、今日の講演はとても説得力がありさわやかであった。野田首相のこれからに注目するとともに大平正芳は決して忘れてならない政治家である。
講演の余韻が残る中、懇親会が湯浅副会長の挨拶で開始となった。30数名の参加で全員に今日の講演の印象や会に対する思い、早稲田の動向、サークルなど日頃の活動を思い思い語っていただいた。今日の浅井さんの語り口で大平正芳観が変わるとともに野田首相への期待感、また「なでしこジャパン」の活躍に刺激された早稲田女子サッカー由井濱前監督の話、西村さんから近隣稲門会を集めた「南大沢囲碁会」の開始、遠藤市議からは最近の「多摩市政」の動向、長張さんからは「八ヶ岳縦走」の模様などが次から次へと話が尽きなくあっという間に時間となった。恒例の校歌斉唱とエールの交歓で和やかな内にお開きとなった。 (文責―平松)
参加者;青木康成、浅井隆夫、新井正子、按田 弘、井上一良、石井卓治、稲垣友三、尾ノ井光昭、遠藤千尋、加来健一郎、金谷勇作、金子宏二、川面忠男、菊沢光江、甲野善勇、子幡嘉之、小林 勲、櫻井和子、白井昭男、田中亮介、田辺繁友、中神尚男、中川邦雄、長張紘一、西村幸一、橋本 孜、藤井國男、半田正久、平松和己、広田
進、星野英仁、前田光治、又木淳一、湯浅芳衛、吉川啓次郎、由井濱洋一、若杉公朋、以上37名。
11月のテニスコート予約確定:新規会員を募集しています。
奮ってご参加ください。
いずれの日も、8:00―10:00です。
11月01日(火) Cコート Dコート
11月08日(火) Cコート Dコート
11月15日(火) Cコート Dコート
11月22日(火) Cコート Dコート
11月29日(火) Cコート Dコート
会場:一本杉公園内テニスコート
お問合せ:依田敬一 yodak1jp@yahoo.co.jp
グルメの会:夜景を楽しみ美味しくビールをいただきました。
31回目のグルメの会例会は9月28日(水)、高尾山中の高尾山ビアマウントで開いた。さわやかな快晴に恵まれて女性2人を含む9人が参加、飲み放題・食べ放題ながらひとり3千300円(女性は3千円)で食欲の秋を堪能した。午後5時から酒宴を始めたが、日暮は早く、奥多摩の山々の稜線が夕闇にくっきりと浮かび、都心方向の夜景が鮮やかだった。
ビールは、いずれも生ビール。アサヒのスーパードライ、キリンの一番しぼりやハートランドのほか、ドイツのレーベンブロイ、オランダのハイネケンが楽しめた。「外国ビールの生」がここの売り物でもある。暑い盛りに世話役が下見した時には見当たらなかった日本酒は、「男山」の熱燗が用意され、季節の移ろいを実感させた。
料理は、中華とイタリアンが中心という触れ込みで焼きそばの種類が多いのが印象的。サッパリ風のラーメンが人気を呼んだ。鍋やたこ焼きのセットも無料で借りられ、「手料理」を囲みながらワイワイガヤガヤ。大自然に囲まれたレストランの味を肴に、参加者はみな童心にかえったようだった。
お客さんは若い世代が多く、ほろ酔い気分の女性と意気投合して、一緒に参加者全員が記念撮影する一幕も。
台風15号の被害で倒木が目立った高尾山だったが、2時間ほどの酒宴は大いに盛り上がり、「もとは十分とった」「楽しかったわあ」「またここでやろう」と意気揚々と散会した。
以上
2010.09(第115回) 権現山
権現山は中央本線の車窓から探し出すのはなかなか難しい。北側に沿って続く扇山、百蔵山の山並みに遮られているためだ。標高1300mを越える山は、この辺りには他にないのだが、奥まっているせいか訪れる登山客も稀になっている。

今日のメンバーは川俣さん・宇田川さん・上杉さん・山岸さん・金子さん・長張の6名である。宇田川さんとは上野原駅で落ち合い、8時28分発のバスに乗り合わせた。今年の夏は呆れるほどの猛暑が続き、少々夏バテ気味であるのは私だけではないようだ。
バスの乗客は上野原駅で乗車した男女の高校生を次々に降ろした後は、狭い道で対向車をうまく交わしながら、30分ほどで初戸(はと)バス停に着いた。我々と一緒に3人の女性グループが同じ権現山を目指し降車した。
長閑なバス停前の田舎の集落を案内版に従って進んで行くうちに樹木の茂る山道となる。山道は植林された檜林が頂上付近まで続き、かなり急峻な山道である。今日のコースは累積標高差が1006mとなり、会では中級コースとなるそうである。
薄暗い檜の山道も高度を増してきた。ヤマジノホトトギス、アキノキリンソウ、シラヤマギク、オクモミジハグマがあちこちに咲きほこっており、秋の気配を感じさせる。
ツルニンジン(ジイソブ)の蕾を川俣さんが見つけた。辺りを探して見ると、多く実になったものの中にシュロソウに絡んだ花の見どころのものが一輪残っていた。ジイソブもシュロソウも花を見るのはラッキーといえる。写真を撮り早々に登山開始、苦しい急峻を登ると11時10分過ぎに雨降(あふり)山に辿り着いた。
頂上は平坦で樹木に覆われて視界はきかなかった。権現山から続く尾根筋に続く高台に大きなアンテナの鉄塔が立っている。湿った所が好きなツリフネソウが尾根伝いに群生していた。
雨降山から比較的に平坦な尾根道となる。ここは快適な広葉樹林で覆われている。山頂間近にある大ムレ権現の社殿は、自然の岩を削った急な階段を登った場所に建っていた。日本武尊を祀る社と立て札にある。ここで始めて1人の登山者に出会った。社殿の裏側を一気に登るのがルートのようであるが、社殿左側の方向にも山道が続き、山腹を廻り西側からの上り口に入りそこから頂上に辿り着いた。
最後の急峻は苦しかったが、正午少し前に頂上に立つことができた。この山頂も樹木に覆われていたが、北側は切り開かれ裾野を広げた三頭山の全容が視界に入る。また、三頭山を基点とする笹尾根は、高低差のないまま裾を東に延ばしていた。三頭山は何処からも見られるが、この位置からの眺めは格別である。山頂の平らな所は広くはないが、我々だけの食事には充分な広さであった。食事の終わるころバスに同乗した3人の女性グループが到着し、食事の場所を譲った。3人のグループは山とは関係の無い話題が延々と続いている。
帰りのバスの時間には充分の余裕があるが、次々に男性が到着し、山頂を彼らに譲ることになった。出合った登山者は5・6名であったが、云われるように人の訪れの少ない静かな山である。
和見分岐まで往路のなだらかな尾根道をゆっくり下る。小1時間の快適な山道である。分岐からは急峻を下る。樹木の切れ目から隣の扇山の姿が一瞬見える。
和見峠で広い林道に出た。和見入口バス停まで単調な林道を1時間半ほど下り、漸くバス停に到着した。40分程バスを待ち、4時30分発の上野原駅行きのバスに乗り込んだ。我々以外の乗客はいない。20号線の上野原駅へのT字路でバスを降り、山岸さんの知り合いである和菓子屋に寄り、各自家への土産を購入した。同店で紹介された近くの料理屋に入り、今日一日の山旅の成果を語り合った。まだ暑さが残る山歩きは喉の渇きも一層強く感じ、ビールの味は格別のものとなった。 長張 記
2011.09(Bコース) せせらぎ橋・多摩の橋立見学会
“せせらぎ橋”経由“多摩の橋立”見学会議事録
日 時:平成23年9月22日(木)13時30分~16時30分
場 所:パルテノン多摩2F歴史ミュージアム企画展コーナー
参加者:金子、長張、荒井、平松、櫻井、伊藤、橋本(敬称略)
1.“せせらぎ公園”経由“せせらぎ橋”
* 京王相模原線堀之内駅に全員が集合して、戸建住宅街の中を流れる水路に沿って緩やかな登り道を暫く歩くと「日枝神社」が有り、その先が“別所公園入口”。そこから北西に暫く歩くと展示にも有る水路のある“せせらぎ橋”にたどり着く。
* 橋の中央には水路が有り長池公園から流れてき、“せせらぎ公園”の水路を通り大栗川に流入する。
* 橋の下は尾根幹通りから南大沢駅への自動車道となっている。開発前のこの辺りの丘陵を水は如何流れていたのかが気になって、展示コーナーで解説者に聞くこととする。
* 唐木田駅まで歩いて、1駅120円で多摩センター駅へ。
2.多摩の橋立(橋から眺める地域史)
* 解説者:公益財団法人「多摩市文化振興財団」 学芸員 清水氏
* 多摩ニュータウン開発で、多摩市には大小さまざまな橋が建設された。特に歩道橋の数と種類の多さは街の大きな特徴で「歩道橋の博物館」とも言われている。
* 展示構成:①村の橋 ②変貌する橋とまち ③橋の博物館・多摩ニュータウン
* 橋の目的:①川を渡る ②交通安全(歩道橋)③谷間を渡る(陸橋)
* 昔の橋の種類:①土橋 ②石橋(値段が高い) ③板橋(堅い栗ノ木、水に強い松ノ木)
* 今の橋の種類:①桁鉄 ②床版橋 ③ラーメン橋 ④アーチ橋 ⑤トラス橋
⑥斜張橋
* 多摩村の橋:野猿街道から関戸の渡しへ行くには「宝蔵橋」が必要だった。
貝取村と乞田村の間には「大橋」や「釜沼橋」が必要だった(1770年頃)。
* 明治以降に橋に名前を付けるようになる(それまでは字○○村橋)。
* 字木曽免橋は明治27年明治天皇が連光寺に来た時に「行幸橋」と名づけられた。また今の川崎街道を“行幸通り”にしようとの考えも有った。
* 岩倉具視と大隈重信は聖蹟記念公園の桜を見に行こうとしたが、関戸の渡しが馬に乗って渡れなかったので諦めたとのエピソードが有る。
* 殿田橋は地元の中和田、上和田の村民はお金を出さず、離れた他の村の人がお金を出して作られている。但し管理・修理は地元の村民が遣っていた。
* 江戸時代から橋の統計データーもなく研究もされてこなかった。
* 昭和12年ごろ府中から多摩方面に行くために「関戸橋」が出来た。是政橋と競合したが先に「関戸橋」が作られた(多摩聖蹟橋と命名する案も有った)。府中から多摩方面への下り方向にはバルコニーが付いている。
* 橋の道普請(整備)は春、秋のお彼岸に行われていた。
* 多摩村は水道普及率が非常に高かった。
* 永山駅近郊の丘陵を渡る陸橋はデザイン性が高く、特に50年代以降は景観を意識した橋が多い。
* “せせらぎ橋”の答え:元々は橋の下を水が流れ別の経路で大栗川に合流していた。
* 長池見附橋は四谷見付にあったヨーロッパ風の橋を移したが、橋の下部にあるトラスは11個有ったが復元する為に2個は検査に使用したために8個となっている。橋の上部の鋳物部材も型を取って復元している。
* 多摩市には160基の橋が有るが、S41~S58年に124基作られている。
* 落合に有る「恐竜橋」は募集により命名された経緯が有る。
* 多摩ニュータウン通りから尾根幹通りに向かう鎌倉街道には「さんかく橋」しかないのは街道沿いに個人宅が多く区画整理により土地の買収が出来なかった為。 (橋本 孜 記)
2011.09(第125回) 市道山・臼杵山
2011年9月17日
戸倉三山は、臼杵山、市道山、刈寄山を合わせて呼ばれている。三山を歩くコースが一般的であるが、7時間を超え高低差もある山道なので、今日は刈寄山を省き二山のコースとなった。このコースは今年の6月に計画されたが天候不良で中止、再チャレンジだ。
武蔵五日市駅から溢れる人たちは、殆ど9時発の数馬行きのバス停に並んでくる。乗車できるか不安であったが、臨時が2台増便され、僕らは係の誘導で3台のバスに分乗し、全員座る事ができ同時に出発した。
25分程の笹平のバス停は、思っていた以上に大勢のハイカーで溢れていたが、パーティの数は僕らを入れて3パーティであった。
徒歩開始、林道を緩やかに登って行く。暫く林道を登って行くと、先行のパーティが道端に大勢集まっていた。ここが登山口であったのを見過ごしてしましい、かなり進んだ所から引返すことになった。結局、登山口に着いたのは、2、30分の所、1時間も過ぎてしまった。身仕度を整えていよいよ登山開始、澄みわたった渓流を渡り、よめとり坂と呼ばれる急坂を登る。暗い森の下にはヤマホトトギスの花が至る所に咲く路だ。風はなく湿度が高い。登りは更に続き汗が滴る。 ≪杉暗きヤマホトトギス仄なり≫
今日のコースのメンバーは、川俣あけみさん・依田敬一さん・橋本孜さん・上杉雅好さん・金子宏二さん・長張紘一の6名。依田さんの参加は久しぶりである。12時少し前にようやく市道山山頂に辿り着いた。
上空には黒い雲の塊がゆっくり北に向かっている。山頂から下界の景色を見せるため、一部遮る樹木が刈られ狭山ドームが見えていた。新宿副都心やスカイタワーは見えなかった。
台風12号は超スローペースで列島を跨ぎ、各地に多量の雨による甚大な災害をもたらした。その後にくるジョギング並みの速さで列島に近づく14・15号の影響が気になる。今朝未明にも強い雨が振り出し、今日は中止にすべきか迷ったが、天気予報では日本列島で東京のみ雨マークはない。とはいえ、雨が降り出す恐れがあり、早々と12時半過ぎに市道山を下り、隣の臼杵山を目指した。最初の急坂を下ると緩やかにはなるが、アップダウンの連続が始まる。戸倉三山は北高尾山稜と共に、都内にある本格的登山のトレーニングコースの一つであり、きつい山である。
杉と檜の植林地帯には、先日の台風の影響でちぎれ飛んだ小枝が至る所に落ちていた。
植林された杉や檜の中に赤松の大木が混じっている。大木は巨大で枯れているものが多かった。皮が剥がれ四方に散っている。いずれ朽ちて倒れる運命にあるが、何故、杉や檜の森に残されてきたのか解らない。山道は静かで登山口から出会った人は2人だけであった。
ツルリンドウがあらわれ川俣さんがいち早く見つけた。どれにも蕾が沢山ついているが、花の時期には少し早そうである。その中に数株僅かに咲いているツルリンドウを見つけ感動する。 ≪山路ゆく友が指差すツルリンドウ≫
ツリフネソウやキバナアキギリは至る所に見ることができた。2時半ごろ最後の急坂を登り、842mの臼杵山山頂にたどり着いた。市道山より50m程高い。ここも一部山林が切開かれ下界の景色が見られる。ハイカーへのサービスだろう。眼下には五日市の街並み、その背後にある鉄塔の多い丘は横沢入りの緑地である。
これでもかと言わんばかりに急坂が続く、膝が笑いだし踏ん張りが効かない。橋本さんは、数日前左足を捻挫してかばいながら下山している。山道に覆い被さる野草で足元が見えない。にわか雨にでも遭ったか少し濡れており、滑りながら下って行く。川筋にそって真っ直ぐに下ると、4時20分、突然車道に出た。出た所には元郷のバス停があり、バスはまもなく2台連ねて入って来た。後ろのバスに乗り、全員座って武蔵五日市駅に行くことができた。台風が近づき雨降りを心配したが、降られることもなく山道を楽しむことができた。 長張 記
※句二首 金子
ワセスポ・秋の陣 好発進! 庭球部が学生選手権で全種目制覇
八月末に開幕した今年の「全日本学生テニス選手権」は台風12号の影響で大会の運営にも大変苦労したと聞きましたが決勝戦は首尾良く当初の予定通り9月4日(日)に有明コートで行われて「オッカケたい」は依田さんと筆者(湯浅)が応援にかけつけました。
その結果、何と学生テニスの個人戦のタイトルを昨年に続き早稲田が独占しました。
例年ですとこの時期は残暑が厳しく選手はもとより観客の熱中症が心配ですが今年は台風のせいでに雨のため試合途中で中断があったものの木陰の風が涼しく快適でした。
決勝戦はシングルスが10時30分から隣接するコートで同時進行でが行われました。
男子は片山(4年)対田川(2年)の早稲田同士、女子は桑田(3年)対川崎(園田女子大)の対戦でした。片山は一昨年が優勝、昨年が準優勝で今年は第2シードの学生テニス界屈指の強豪です。片や第13シードの田川は準決勝で昨年の優勝者・伊藤主将(第1シード)をストレートで破り昇り調子です。両者共得意なフォアハンドの思い切りの良い打ち合いは息を呑む迫力で圧巻でした。田川はサーブも強力でサービスエースを取り、ラリーでも攻めまくり6-3、6―3で制して見事初優勝を飾りました。
一方女子の桑田は早実出身で高校時代はベスト8止まりでしたが大学入学後に成長して昨年優勝しました。今年は第1シードで順調に勝ち進み決勝は強力なフォアハンドストロークを武器に第6シードの川崎に6-0、6-3と圧勝して2年連続女王となりました。
続くダブルスは男子の第5シードの伊藤(4年)、広田(3年)のペアが第2シードの奥(日大)、長尾(上武大)組に2-6、7-5、6―3で逆転勝ちしました。
女子は第1シードの田中(4年)、大竹(3年)組が第2シードの伊藤(4年)、岩崎(3年)組を6-3、7-6で破り初優勝しました。実はこの両者は昨年決勝で対戦して伊藤組が勝ったので今年は田中組にとりリベンジ達成になりました。ダブルスは男子がレベルが違いすぎますが女子は我々にとっても参考になる部分が多く一つでも出来るところから見習いたいと思いました。
大学テニスは団体戦が9月の関東大学リーグ戦、10月の大学王座決定戦と続きます。
早稲田は男子の7連覇と女子の6連覇に挑戦します。アベック優勝は長い大学テニスの歴史の中で他にには過去早稲田と慶応が各一回記録しただけなので是非連覇記録を更新して無敵振りを発揮してもらいたいと期待しています。(文責・湯浅)
2011年/稲門祭オリジナル記念グッズをご紹介します。
10月16日(日)です。例年通り、オリジナルの記念グッズが販売されます。
写真は一例です。
全商品、下段のURLでリンクできます。
商品は、稲門祭のためにデザインされた期間・数量限定の記念品です。記念品販売の収益金は全額「稲門祭奨学金」として地震被災学生を強力支援します。
皆様のご協力をお願い申し上げます。
2011稲門祭記念品は、次のいずれかの方法でご購入いただけます。
- ・ 2011年稲門祭記念品販売係
![rimowa_ph1_1[1]](http://tama-tomon.net/admin/wp-content/uploads/2011/08/rimowa_ph1_11.jpg)
- 株式会社デューク・コーポレーション内
担当: 田中良典 (たなか・りょうすけ)
TEL: 03-5646-5920
FAX: 03-5646-5921
お問合せメールアドレス: info@waseda-shop.com
受付時間: 10:00~18:00(土日祝日、夏季休業を除く)
- ・ 店頭でのお買い求め
- 早稲田大学オフィシャルグッズショップ<Uni.Shop&Cafe125>
早稲田キャンパス内大隈講堂横
営業時間: 8:30~17:00(夏季休業を除き年中無休)
※詳しくは、お問い合わせください。
- Webサイト<WASEDA-SHOP>でのご注文
- FAXでのご注文
- (稲門会幹事の方向け)総会時販売セットのお申込
- 早稲田キャンパス内<Uni.Shop & Cafe 125>でのご購入
- 稲門祭当日、現地でのご購入
商品をWEBで見る:http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/kinenhin.html#g04
今年も野沢温泉でブナを植えてきました。
2011年7月7日、東村山市の萩山小学校6年生約80名が野沢温泉村の上の平でブナの植林を行うのを村の方々と一緒になりお手伝いしてきました。
多摩稲門会から櫻井さん、川面さん、依田が参加し温泉と食事を楽しみながら野沢温泉村の皆さんと交流を深めてきました。
今年で9年目となるこの行事も、お隣の稲城市では小学校全校が参加して夏休みを利用し延べ700名ほどが4泊5日で実施しています。
100年構想なので将来が楽しみです。
この件に関するお問い合わせは:
依田敬一:yodak1jp@yahoo.co.jp
« Older Entries Newer Entries »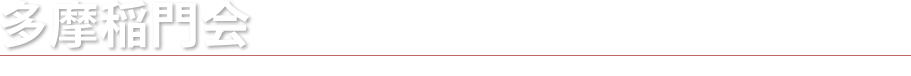


















![tennis[1]](http://tama-tomon.net/admin/wp-content/uploads/2011/09/tennis1-300x226.jpg)
![kashizara_ph1[1]](http://tama-tomon.net/admin/wp-content/uploads/2011/08/kashizara_ph11.jpg)