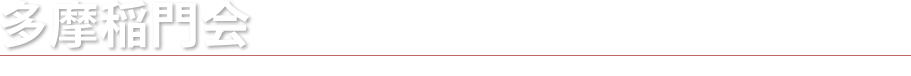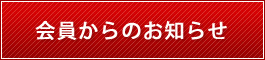Author Archive
2008.07(Bコース) 狛江散策
2008.07(第 95回) 大岳山
奥多摩の山の中で最も目立つ山は大岳山であると思う。その独特の姿は何処から見ても見間違える事はない。遠く横浜から見ても同じかたちに見えていて親近感のある山である。
今日は、金子さん・川面さん・橋本さん・山岸さん・川俣さん・柴田さんと何時ものお馴染のメンバーだ。7月の奥多摩の山は暑くて閉口する。特に晴れた風のない日は蒸し暑く厳しいハイキングとなる。今朝も熱帯夜を引きずって既に蒸し暑く感じられる。御岳駅に9時36分に着き素早くバスに乗り込みケーブル下まで、更に、流れに従ってケーブルに乗り御岳山駅に着いた。ここにも多くのハイカーがみられる。この高度になると湿気は少なくなっているような気がする。10時20分徒歩開始となる。
御嶽神社に寄り、その脇の小道を下り天狗の腰掛け杉を通る。一昨年、ここから奥の院まで登っている。今回は、その裾を巻いた高低差の少ない綾広の滝方面に進む。アクバ峠に近づくに従って徐々に急坂となる。峠には大勢の年配の団体が休んでいた。大岳山までは人気コースなだけにかなりの賑わいである。
やがて岩場もある急坂となり古びた大岳山荘に着いた。山荘の上部には神社があり、杉の大木に囲まれている平らな広場がある。最後の急坂は岩場で、鎖も整備されている。
大岳山山頂は思ったほどの広さはなく、多くのハイカーが既に食事をしている。頂上からの展望は樹木に覆われパノラマとはいかない。大岳山は周りから眺められる山で、眺めの良い山ではないことがわかった。平らの場所を探し12時30分食事をとった。
食事後は、大岳山荘まで同じコースを下る。岩が湿って滑りそうで慎重に下る。大岳山荘から大岳山の裾を巻きながら進むと、やがて馬頭刈尾根上部にでる。道の両側には笹が茂り、人一人がやっと通れる幅に迫っている。日差しは生い茂る樹木に覆われ根元まで届かない。尾根道から右の白倉に下りる道を過ぎ、やがて左の養沢に下りる道に達する。馬頭刈尾根から一気に下る道は急であり長かった。高度が下がるに従って植物相が変化する。球状の白色の蕾を多数つけたギンバイソウの群生が広がり、疲れを癒してくれる。更に下ると杉林の中に入る。
道は更に下りやがて沢にでる。清流はしぶきをあげながら岩を滑り、流れに長く手を入れていられないほど冷たく澄んでいる。大岳沢の大滝である。滝の最上部は丸く岩がえぐられ、大量の水がやかんの口から注ぎ出るように落下していく。木の階段が滝壺まで下っており、滝壺の間近でみる滝の全容は壮観であった。
滝でしばらく休憩を取ったが、バスの発車時間まで後1時間ほどになり先を急ぐ。道は舗装された車道となり、ただひたすら平凡な道路を下っていく。道路はT字路となった所が養沢のバス停である。
スケジュール通り4時25分発のバスに乗り武蔵五日市駅まで、そして立川で下車し、何時もの居酒屋のビールと日本酒「喜正」で歓談した。今日のコースは、全体に直射日光の届かない樹木の下を通り、割合涼しく真夏向きの奥多摩コースであった。 長張 記
2008.07(特別企画) 入笠山
2008.06(特別企画) 百蔵山・扇山
百蔵山・扇山の連山は、中央本線の四方津・梁川駅・鳥沢駅を過ぎた辺りから大きく北側の車窓に広がる馴染みの山である。鳥沢駅を過ぎ大月駅の一つ手前の猿橋駅を9時過ぎに下車する。
今日のメンバーは、川面さんと私2人である。駅から早速タクシーに乗車し、百蔵山登山口までそこから徒歩開始した。今回は、8月に控える甲斐駒ケ岳登山の訓練も兼ね、「山歩きの会」では2度目の試みで少々ハードなコースであると云うことであったが、前日の晩から大雨が振り中止となった。その日は曇り空ではあったが雨も止み、高幡不動尊の紫陽花祭りの見学に切り替わり、金子夫妻・川面さん・山岸さん・川俣さん・柴田さんらと楽しんだ。当日、梅雨の中の晴れ間を利用し同コースをトライしようということになった。
金子さんの作成したダイヤは、平日のダイヤと違う事は承知していたが、高尾駅でまさに乗車直前にドアが閉まってしまい乗車できず、川面さんを乗せた電車は去ってしまった。現役時代を過ぎ時間に対する感覚が衰えてきている。すっかり弛緩モードになってしまった。遅れること20分猿橋駅で落ち合ったが恐縮至極であった。
車を降り9時半に歩行開始する。しっとりとした深い森の山道を川面さん先頭でゆっくり登っていく。上左写真は猿橋の街並みで、桂川の蛇行が見渡せる。(上右写真)さらに高度を増すにしたがって赤松林の中に入る。1時間ほどで百蔵山頂上に着いた 。
頂は比較的広く樹木が茂っていた。そのまま進む扇山方面は、急傾斜の下山である。道際に腐生欄のオニノヤガラの穂状の花を見ることができた。初めてみた植物である。
コタラ山・カンバノ頭を巻き、今日の最大の難所である大久保山への急坂を登る。ここで初めて下山してくる若いカップルに出あった。大久保山は頂というより尾根の一部のようであった。さらに老人1人に出会うが、今日のコースで出会った最後のハイカーであり3人目であった。川面さんの新しい熊避けの鈴の音は、遠くまで響いているようであった。
大久保山の急坂を登りきると、そこからは平坦なコースが続く(上左写真)。
扇山の頂には1時少し前に着いた。広く平坦であり明るく周りに樹木がある。富士山方面に展望が開けているようであるが、霧が立ち込み視界はなかった。霧のかたまりが時々梢の間から流れて出てくる。駅からみた山頂はガスがかかっていたが、同じ状況のようである。
虻に悩まされながら食事を済ませ1時20分に、元の道を引き返す。しばらく尾根道を下るが、鳥沢駅方面への分れ道で尾根道から一気に沢へ下る。
大久保山の急坂を予想したが、下り道は急斜面をジグザグになった林道で綺麗に整備されていた。木の根もなく歩き易く快適な下りである。水呑杉の場所は、大木の根元から水が湧き出ており、直ぐにわかる。根が水場を跨ぐように構えている。さらに下り沢にでて久々の小休憩をとる。
山の神という所で、さほど冷たくはないが雨上がりの多くの水量が流れている。ここから一気に山道を梨の木平まで下り、そこから車道になりゴルフ場を回りながら休むことなく歩き続け、4時少し過ぎに鳥沢駅に着いた。人気の少ない快適な山歩きを楽しむことができた。20分ほど遅れた電車で八王子まで、何時もの居酒屋はまだ開いてなく、一階下の居酒屋でビールを飲んで、今日の成果を話し合うことができた。 長張 記
2008.06(Bコース) 高幡不動尊
2008.06(Bコース) 高幡不動尊
2008.05(Bコース) 早稲田大学
・
2008.05(特別企画) 武甲山
秩父盆地の表玄関に聳える武甲山は、山肌を大きく削られ山の姿を一変させてしまった。江戸時代から漆喰原料、明治以降もセメント原料として平成に入った今でも石灰岩採掘は続き山肌が削られているためだ。削られた岩肌は頂上にまでおよび、標高は数十mも低くなったそうである。秩父駅からの眺めは急勾配の斜面が痛々しくも見える反面、荒々しく力強い風格をも感じさせる。奥多摩の山から望む武甲山は、頂しか見ることができない。多摩市から比較的近い山であるにもかかわらず、今日まで登るチャンスに恵まれなかった。登山口までのアクセスが悪いためだが、訪れてみたい山の一つでもあった。
八高線東飯能駅で西武線に乗り換え、終点秩父駅に9時過ぎに着いた。駅広場からは、猛々しく構えた武甲山が見渡せる。さすが秩父盆地のシンボルである。頂は霞んでいた。
タクシーで横瀬駅まで戻りそのまま生川の登山口まで、そこは武甲山の秩父駅側の反対側である。こちら側は岩肌が剥き出す荒々しい姿はなく静かな山の姿であった。
今日のメンバーは金子さん・川面さん・橋本さん・長張の4人となった。本来の第3土曜日は、高尾山の清掃登山を控えている等の理由により中止となった。山岸さんや川俣さんから苦情がでたが、前日に決行する事になった。二人は翌日同じコースを行かれたようである。登山口から一気に標高差800mを上る。途中不動の滝・杉の大木・植林された登山道がつづく。
登山口の一丁目から山頂の五十二丁目まで丁目石が置かれている。樹木の緑も芽吹きだし眺望が遮られる時期になってきた。
一気に上り昼までに山頂に着く事ができた。登山には寒からず暑からずの絶好の季節であり、快適に頂上まで登る事ができた。
山頂近くになると登山道の両側は鉄柵で囲まれている。その囲いは頂上部分の広場を一周している。北側は断崖絶壁で秩父の市街が霞を通して見渡せる。南側も急斜面ではあるが何故か鉄柵で遮られていた。少し前に訪れた羊山公園の芝桜の絨毯模様は、眼下の霞のせいか消えていた。頂には一組の老夫婦が食事をしていた。我々もここで昼食をとる。
山頂直ぐ下には御嶽神社があり、半月前にここで山開きの儀式が行われた。新緑の中の境内にはニリンソウが咲き誇っている。多摩丘陵より1ヶ月以上遅れているようだ。ウグイスカグラの花も今が盛りでこれも遅れている。登山口近くにオドリコソウ・ラショウモンカズラ・ヒメレンゲ・チャルメルソウ・ミツバコンロウソウ・クワガタソウ等の花が咲き誇っていた。高尾山周辺の植生と似ているが、山に入らなければ見ることのできない植物ばかりである。石灰岩地帯の特有の植物があるようだが、見あたらなかった。
山頂からは西の方向にひたすら下るだけの静粛な路が続く。途中のカラマツの林は、高尾近辺にはない雰囲気であった。急坂をひたすら更に下ると沢に出る。丸太の橋と云う場所のようだが、透き通る豊富な水が岩肌をなめ、いくつもの小さな滝となって流れている。秩父の絶景を見入る事ができた。ハイキングコースは良く整備され歩き易く快適であった。
西武浦山口駅には予定より早く着いた。ひと電車早く御花畑まで2駅、西武秩父駅から3時過ぎの電車で帰途についた。八王子駅前での旨いビールを飲むには丁度良い時間となっている。 長張 記
2008.04(第 94回) 陣馬・景信・高尾山
「春に3日の晴れ間なし」最近の天気は三寒四温、一昨日から雨模様であったが、予報では一日中曇り空が続き、夕方から雨の確立が高いとのことである。最近の温度差は10度もあり今日の気温はどうなるか。雨の降りそうな朝は、家を出る時悩んでしまう。今日はリーダーの金子さん・川面さん・橋本さん・山岸さん・長張の男性5名である。
藤野駅でのタクシーはスムーズで、全員が一台で乗車することができた。詰めた車内は狭かったが、左右の新芽の緑が走り去るドライブは、気持ち良いものである。和田峠には9時少し過ぎに着いた。峠の店は開いている様子であったが客はいない。これまでの峠からのコースは、階段路の脇にある登山道をゆっくり登っていたが、今日は、良く整備された木の階段を、ひたすら上る最短コースである。階段は空の良く見える明るい尾根道である。予報に反して一時的にも日差しがでてきた。
陣馬山山頂にも他のメンバーは見られなかった。遠くの山並みには雲がかかっていたが、道志方面の山並みの襞は、前日の風雨で空気が澄み細部にわたり見極めることができた。陣馬から影信への道は、高低の緩い樹木に覆われた幅広い尾根道をすすむ。気温は低く快適なコースで他のハイカーはここでも見られなかった。
景信山山頂には12時前に着いた。山頂際の樹木は広い範囲で伐採され、関東平野が一望できていた。昼食は風が少し強く寒かったが、ベンチに一列に並んで下右の景色を見ながらの食事である。遠く筑波の山並みの手前に西武ドームが白く光っている。
澄み渡った空気を通して、江の島や東京湾・房総丘陵・横浜・新宿のビル群・多摩のベネッセビル・2つ並んだ聖ヶ丘の給油塔、等々、皆で所在を確かめ合いながら、楽しい時間が過ぎていった。体が休まると冷えてきて寒くなってくる。寒い時期の昼食は、早々に済ませて歩き出すのが常である。
小仏峠を経て1時少し過ぎ、城山山頂に着いた。黒い雲が出ているが、雨の心配は無さそうである。一丁平のサクラの並木も足早にやり過ごす。
写真は、一丁平に咲くサクラの花と遠くの街並みである。高尾山のサクラは終わりに近づいていた。ソメイヨシノは散ってしまったがヤマザクラはまだ残っている。登山道に残る白い花びらの光があまりにも強く、雪の上を歩いているような錯覚になる。道の下に隠された石や根の存在が消され、慎重にならざるを得ず目まいが起きそうになる。
モミジ台近くでBコースの櫻井さん・新井さん・湯浅さんのメンバーと遇々出会う。
奇遇とエールを交換し、しばらく同行したが見晴台下で、我々は先を急ぎ4号路から蛇滝に下りるコースをとり、小仏街道へと歩を進める。
街道の手前のハイキングコースに入りしばらく川筋に沿って下ったが、直に街道に出てバス路を下った。懇親会に間に合うよう途中でタクシーを拾い、高尾駅の予定の電車に乗ることができた。京王クラブには川妻さん・甲野さん・中川さん・福田さん夫妻も加わり4時から懇親会が始まった。帰途の歩道は雨がぱらつき濡れていた。有意義な一日であった。幹事さん他一同に感謝・感謝 長張 記
2008.03(第 93回) 茅ヶ岳
茅ガ岳は1700m程のさほど高い山ではない。深田久弥はこの山頂の展望を目前にして倒れ、そのまま亡くなり有名な山となった。この山を101名山と呼ぶ人もいるようだ。特急「あずさ」を韮崎に下りたのは9時半過ぎ、今日はリーダーの金子さん・川面さん・伊藤さん・山岸さん・柴田さん・長張の6名である。予報通り前日から早朝にかけてかなりの雨量があった。久しぶりのお湿りだが、その後の好天は一斉に花粉が飛び散り悩ませてくれるのが常である。韮崎駅ホームから、雲ひとつない八ヶ岳連峰が望まれ、同時に今日の対象の茅ガ岳を目前にすることができる。茅ガ岳の山々は雪こそかぶってないが、山容が酷似していることから「にせ八ツ」と言われる理由も分かる。韮崎駅から深田記念公園までタクシーで上る。公園に佇む記念碑には、「百の頂に百の喜びあり」と彼の言葉が、磨かれた石碑に刻まれていた。
そこから緩やかな広い林道を上ってゆく。アカマツやコナラ等の林の中を1時間ほど進むと間もなく巨大な岩が立ちふさがり、岩の間から清水が流れている。
女岩と呼ばれる岩だ。しばしの休憩をとり清水で口を潤す。女岩を右側に捲きながら崖の上へ出ると本格的な登山道に入る。
かなりの急坂をしばらく進むと尾根筋に出た。北側が開かれ空の下に金峰山の山容が突然迫っていた。深田久弥の終焉の碑がそこにあった。
山頂には予定通り12時少し過ぎに着いた。ゆったりとした頂は、360度の大展望であった。遠くに北や中央のアルプス連山や、そして南アルプス連山が、間近に見渡せる一級のパノラマである。
鳳凰三山の連山の背後に、北岳・仙丈・右端の甲斐駒ガ岳の雄姿は抜群であった。北岳から90度左は富士山方面。右側は八ヶ岳であるが、茅ガ岳の双耳峰の金ガ岳が一部を隠している。更に右に金峰山など奥秩父の山並みが続く大パノラマを満喫する。山頂で昼食を始めた時は、われわれメンバーだけで独占することができた。腰を下ろして食べる時を惜しみ、立食で歩き回りながら全方向の眺めに感動し楽しんだ。
茅が岳から直ぐ隣に聳えている金ガ岳へは、先ず下ってから上るコースである。茅ガ岳下山は北斜面で雪が残り、凍結もあり皆慎重に下る。上りは南斜面で雪は無かった。石門をくぐりの金ガ岳の頂上に着く。期待した八ヶ岳の全景は樹木の間からしか見ることができない。開かれた部分は先ほどの茅ガ岳、その向こうに富士山の方向だけてであった。
ここからは茅が岳を大きく回りながら下るコースが続く。爆裂火口跡からの八ヶ岳の全容は雄大である。
明野ふれあいの里からタクシーで韮崎駅に戻り、「あずさ」特急で八王子駅に出てビールで乾杯。滅多に見られない大パノラマの機会に感謝。深田久弥の詩に「空の茜を顧みて、一つの山を終えりけり、何の俘(とりこ)のわが心、早も急(せ)かる次の旅」。色紙に書いた四行詩には最初「山」が三つもあり、妻志げ子の指摘でその中二つを「空」と「旅」に直され、文学碑の陶板になったそうだ。山好きのわれわれには理解できる詩である。 長張 記
« Older Entries Newer Entries »