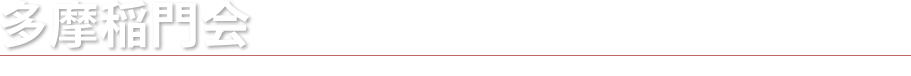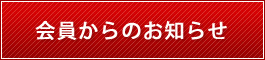Author Archive
2009.03(第101回) 筑波山
筑波山は、万葉の時代から「西の富士・東の筑波」と崇められてきた東国の信仰の山である。標高は877mと富士山と対比させるのはおこがましいが、その姿形は決して富士に劣るとは云えないことかららしい。深田久弥の100選に選ばれているが、その中でも高度の一番低い山でも有名である。
つくばエクスプレスが4年前に開業し、秋葉原から45分で筑波駅に着くことができ、筑波山へのアクセスが大分良くなった。この日我々も11時15分前に筑波駅に到着した。シャトルバスで筑波神社前まで小一時間、筑波神社前に到る。神社までの参道を登る。拝殿で登山の無事を祈願し、ケーブルの宮脇駅へ行く。
筑波山頂駅に8分で着いた。山頂駅は下界を見渡す御幸平にある。昼食の時間は既に過ぎているが、男体山頂まで足を延ばす事にした。10分少々で達した山頂の風は少し冷たかった。
山頂には男体山御本殿や気象施設のコンクリートの建物が、狭いスペースの中に構えていた。また、女体山方面には無粋な幾つかの電波塔が林立しているのは少し気になった。
狭いスペースを利用して昼食をとる。山頂からのパノラマは、流石100名山に価する。関東平野に対峙する西の端から都心を通して、空気の澄んだ日に、遠く望む事ができた時は感激するのが常である。
今日は、昨年の秋に企画されたが天候不良で中止されたコースである。気軽にハイキング気分で楽しめることで、AB合同企画となり、そのためメンバーは多彩となった。櫻井さん・柴田さん・湯浅さん・星野さん・川面さん・青木さん・依田さん・橋本さん・白井さん・浅井さん・金子さん・長張の12名となる。
今日の天気は比較的暖かく晴れてはいるが、大気は霞んでいて良好とはいえない。地平線の上は白い霞だけである。多摩方面の山波は、霞のなかに入り視界に入ってこない。
食事を済ませ、自然研究路に入り、時計周りに中腹を一周するコースをとった。スミレが咲いていた。又、カタクリの株があちこちに群生していて蕾も見られるが咲いている花はまだない。季節がもう少し遅ければ、色々な野草が楽しめる散策路のようである。周回路は平坦ではなくかなりアップダウンがあり、所々に展望台が設けられ絶景が見渡せる。
男体山を周回するコースを離れ、女体山へ向う両山の鞍部には多数の売店が並んでおり、大勢の観光客で賑わっていた。
女体山の頂は更に狭小で、その上、御本殿の「天皇成婚記念、天の浮橋」設営工事中であるため、山頂に入るには順番待ちで長い列が続いていた。女体山御本殿が建つ岩山も、霞ヶ浦を遠く望める絶景スポットである。大勢多数の人が順番を待つのもうなずけることができる。乳飲み子を抱えながら、岩山を登る若い母親の姿が多く見られるのは驚きであった。
狭い頂の岩山からの眺めは、多摩地区の山からの眺めとは違い、下界は低い平野が一面に広がっている。877mの低い山とは思えないボリューム感に圧倒される。
ロープウェイの駅に着くと、周りの景色を楽しむ間もなく直ぐに出発し、5.6分でつつじヶ丘駅に着いた。広い駐車場には地元ナンバーの車で満車状態であった。地域の人の気軽な人気スポットのようである。
新宿駅を下車し、恒例のお疲れさん会。山歩きの会は100回目を迎え、この山の会の第一回から参加の櫻井さんの参加で記念すべき山行ができたことを祝し、大ジョッキで乾杯! 霊山筑波山のガマの気を受けた12名は実に実に意気軒昂、次回を期して散会。 長張記
2009.02(第100回) 伊豆ヶ岳
西武秩父線沿線の山並みは多摩の山並みとは一味違う雰囲気が漂っている。それは、奥武蔵・秩父の独自の歴史かも知れない。その中で伊豆ヶ岳は、奥武蔵の銀座通りといわれるほどハイカーに人気がある。正丸駅から直ぐに登山口となる気楽さも起因しているようだ。
今日の参加者はリーダーの金子さん・山岸さん・柴田さん・長張の4名である。朝の冷えた空気が漂う正丸駅を9時24分に降りた。4.5日前、静岡では夏日を記録した。その反動で一変し寒波が勢力を増し縮み上がる寒さであるが、冬の山はこのような気候が似合っている。正丸峠までの道のりは、冷気が漂う風のない沢に沿った斜面である。
土石流で少し荒れてはいたが1時間ほどで峠の尾根筋に着くことができた。尾根筋に沿って子の権現までのルートには幾つかの山の峰を通り、アップダウンの繰り返しが続く。
全行程の累計の高度差は、千メートル弱の5時間10分となり健脚コースでもある。2時間ほどで雪の積もった小高山を通過し伊豆ヶ岳に着いた。その頂上の南側の風のない場所で、少し早やめの昼食をとることにした。金子さん持参の簡易コンロでの、暖かいおでんは、冬の寒い昼食には大変なご馳走である。山頂は何組ものハイカーで賑わっていた。
12時に行動開始。古御岳へは急斜面を下り、また急斜面を登る。古御岳は樹木に覆われた頂から、葉のない梢を通して山並みが見渡せる。先ほどの二子山の奥に見えていた武甲山の階段状の頂は、山の影になっていた。
古御岳までは、まだ全行程の3分の1ほどでこれからの長さが実感できる。次の頂は高畑山である。この辺りから、頂の間隔が長くなってくる。急勾配が続くコースと云っても、尾根筋には平坦な気持ちの良い山道も続いている。
1時少し過ぎに高畑山に着いた。この頂も、周りは樹木に覆われているが、梢越しに先ほど通過した古御岳・伊豆ヶ岳が見渡せる。
次の目的地の天目指峠までは、なおもアップダウンを繰り返しながら徐々に下ってゆく。
根回り2m以上のモミの大木が並木のように続く道もあり、古い山道である。関東ふれあいの道にも指定され、道標や道も整備されて、歩きやすい道である。
天目指(あまめざす)峠は、竜神の伝説が残る峠で県道が横切っていて、そこからまた上りとなる。天目はこの付近の方言の豆柿のことであり、指とは焼畑のことであると、説明書きが掲げられていた。下ってきた尾根道を巻くような車道は、車の気配もなく寂しい場所であった。休む事もなく2時に通り越し、また山道を登る。
子の権現は武蔵野33観音32番札所である。正しくは大鱗山雲洞院天龍寺と呼ぶ。
天台宗の古刹で、足腰の病に霊験あらたかといわれ、鉄のわらじや高下駄がまつられている。我々は山門を逆コースで進んでいるため背中の向こう側に仁王像・子の権現がある。
3時少し過ぎ、子の権現からは吾野駅まで下りだけである。山道からそれて山道を下るが直に車道となり、1時間強で吾野駅に着き、4時27分の電車に余裕を持って乗り込むことができた。八王子駅に出て、山歩き後の席を設け、大いに歓談した。久しぶりの柴田さんも元気で一日楽しめたようである。子の権現のわらじのお陰であろう。
山岸さんらにより「山歩きの会」の記録を遡って調べて頂いた。今回は99回目となるそうである。次回の100回目は、筑波山の予定となっている。日本100名山の一つであるが、その中で標高が一番低い名山としても有名である。 長張記
2009.01(第 99回) 九鬼山
今年最初の山歩きは、都留市の九鬼山である。昨年の夏、高川山の山頂から、富士急線の向こう側に構える九鬼山を望んだ時に是非登ってみたいと思っていた。両山の山頂直下にリニアのトンネルが掘られている。高川山の頂上から周りの景色を眺めていると、九鬼山の山腹のトンネルから小さく見えるリニアの車体が現われ、瞬く間に足下に入り込む姿が印象的であった。今日の参加者は橋本さん・山岸さん・長張の3名である。リーダーの金子さんや何時もの川面さん、川俣さんは用事が重なり参加されていない。9時12分禾生駅を降りた。正月の暖かさから一変して寒波が勢力を増していたが、2・3日前から緩み始めている。
駅前の国道を左折し、しばらく進むと落合水路橋のレンガ造りのアーチに出合う。桂川の上を跨ぐ水路は100年前の建造物と、上部の背後に見える橋はリニアの橋脚である。
民家のある車道をしばらく上って行くと、杉山新道への岐路に出る。右に折れるとやっと山道になってきた。所々雪が残っている。スギの人工林からアカマツ林と代わる頃は高度も増し、鈴ヶ音峠からの尾根道に合流すると展望が開けてきた。
眼下のリニアの線路はまだ真下ではないので頂上がどの辺りか検討がつく。高川山も同様に頂上直下を貫かれている。山頂まで後2分と表示されている広場は、富士の裾野まで広がるビューポイントであり、この場所以外で全体を見ることはなかった。都留市の秀麗富嶽12景の一つであるが、真っ青な空に、真っ白な富士とはいかず、湿気があるのか少し靄っている。富士の裾左側手前は御正体山で、右側の都留市の街並みは氷河の流れのように見えた。
富士の見える広場は、5・6人のパーティが数組昼食の用意をしていた。11時を少し過ぎた頃であるが、我々もこの場所で昼食をとることにした。この時期は震えながら食事をとることが多かったが、今回は、風もない暖かい場所での昼食であった。
山頂には丁度12時、北側は開けているが、南側は樹木が多く富士の一部が望めるだけである。山頂からの最初の下りは北斜面で残雪があり凍結している。アイゼンを装着して、慎重に岩場の急斜面を下りて行く。
予定コースは、札金峠手前の分岐で多野倉駅に下る事になっていたが、天気や風・雪の状況が良いので、札金峠から足を延ばし尾根に沿って猿橋駅に向うことになった。1時間半ほど長くなるが快適なハイキングが望めそうである。
尾根道の登りは南斜面で雪が無く春の山であったが、下りは雪の残る北斜面の繰り返しであり、アイゼンは猿橋の街に入るまで装着したままであった。札金峠には1時に着いた。太い樹木に覆われ暗く、いかにも昔の峠道である趣のある古道が東西を横切っていた。
尾根道には幾つかの山頂があり最初の馬立山へは、また幾つかの上り下りがある。橋本さんは2本のストックを上手く使いこなして進んでゆく。標識は整備されてはいるが、進路を塞ぐ倒木が多い、しかし気持ちの良いハイキングコースである。
馬立山山頂は15人の高齢者の団体で一杯になっていた。猿橋駅までその団体は、我々の少し前を歩いていた。
御前山に到着した時も、15人の団体で狭い山頂は賑わっていた。我々が到着すると場所を開けるためか、先に向っていく。
残された山頂は元の静けさが戻ってきた。我々はしばらく山頂からのパノラマを楽しむことができた。山岸さんは、中央本線の北側に続く登頂済の山々を目の当たりにして感動し写真を撮っていた。猿橋駅には3時半過ぎに到着。八王子駅で乾杯し、今日の成果を語り合い、次回予定の奥武蔵・伊豆ケ岳に元気で参加を約し散会した。長張記
2008.12(第 98回) 高尾山・城山
年末に開催される「山歩きの会」は、「シモバシラの花を見る会」と定例化されたのは会発足近くからのことであるらしい。山は高尾山と決まっている。十数年間のこのコースのメンバーの顔ぶれは変わってきており歴史を感じさせる。高尾山は近年のミッシュランの星を得てから、何号路と呼ばれるコースは土日の週末は、街並み程の賑わいとなる。今日の参加者は櫻井さん・鈴木さん・川面さん・依田さん・山岸さん・金子さん・長張の7名である。一週間程前に縮みあがるほど寒い日があったが、今年は全体に平年より温かい日が続き、今回も氷の華に出会うことはなさそうである。
高尾山口駅を8時40分に降り、冷気に満ちた稲荷山コースを登る。急な階段を登ると直ぐにお稲荷さんがある 。
休憩の度に一枚づつ上着を脱いでゆく。時間が過ぎるに従って、ハイカーも増え、次々に我々を追い越して行く。尾根道の途中にある展望園地には大勢の中高年の人たちが休んでいた。すっかり葉の落ちた落葉樹が多い尾根路から遠くの景色が見渡せる。
今日は風も無く穏やかな天候に恵まれ遠くの富士山が間近に見渡せる。富士隠しと云われる大室山は高尾山まで来ると左側にそれている。(下写真)左側遠方には10月に登頂した滝子山の先の尖った頂が望め、その左側更に遠方に南アルプスの白い連山が見えていた。
城山山頂のベンチは皆座れる適当な場所がなく、一段下がった芝生の上で早やめの昼食となった。風の無い暖かい場所であったが、少し込み入っていた。帰路は、同じ尾根道のコースをとらず、大平林道を辿るコースとなった。城山から南へ大垂水方面への急勾配を下り、途中にある一丁平の尾根道と並行した林道に入る。他のハイカーにも出会うことが無い静かな中腹の山道で、起伏の緩やかな車も通れる車道を散歩気分で進むことができた。
春になるとこのコースは、野草の宝庫であるが、今の季節では花は望めない。その中で、木や草の実を捜す楽しみがある。特に真っ赤に色づいた実は、冬の緑の少なくなった場所で引き立っていた。ミヤマシキミは稲荷山コースでも見られ、イイギリの赤い実は、高い樹木一杯になっている。サルトリイバラの真っ赤な実は、棘のある太めの蔓の至る所に、放射状につけており、ツルリンドウの実は一株だけ見つけることができた。ミヤマフユイチゴの実の甘酸っぱさは食後に活力を与えてくれる。その他マルバノホロシ・サネカズラ・ノイバラなど皆で赤い実探しを楽しむことができた。
白い長毛を髪の毛を振り乱した鬼女に見立てたキジョランは、ガガイモ科のつる性のものであり欄ではない。上写真の出会いに恵まれるのは希である。種の集合体が、まさに風に乗って外界に飛び出す寸前の姿である。多くの中高年のひと達が、足場の悪い斜面で眺め感動していた。大平林道から尾根筋に出て、琵琶滝のコースを下る。時間の余裕もあるので琵琶滝によってみた。
3年前は氷の華が同じコースの至る所で見られた。シモバシラというシソ科の野草で群生している。
4時から「悠々の会」と合流し、京王クラブで甲野さんの乾杯音頭により忘年懇親会が催しされた。 長張記
2008.11(Bコース) 巾着田・高麗神社
・
2008.11(第 97回) 三頭山
11月に入れば奥多摩の山では冬の気配が感じられる。三頭山は、大岳山・御前山と奥多摩三山と呼ばれている最高峰であり、これも裾野を大きく広げた存在感のある山の一つである。今日は6時間を越える歩行で、また、陽も大分短くなり、朝の出発は何時もより2時間ほど早い出発となった。今日の参加者は川面さん・山岸さん・川俣さん・金子さん・長張の5名である。奥多摩駅、7時50分発のバスに乗ったが、峰谷橋で下車するべき所、終点の峰谷まで行ってしまい、そのバスで折り返し目的の峰谷橋まで戻ることになった。信号に隠れた山がイヨ山で、目指す最初の頂である。9時半ここから徒歩開始となる。
赤い橋の向こうのトンネルを抜けると奥多摩湖に浮かぶドラム缶の浮橋を見下ろすことができる(下写真)。ドラム缶の浮橋を一列に渡るが結構揺れる。
浮橋には釣り客が数人腰を下ろし楽しんでいた。誰のビクにも公魚の釣果が入っていた。浮橋から対岸に上がり道路に出るが登山口(下写真)まで辿り着くのに手間取ってしまい、バスの下車場所ミスと合わせて1時間近くもロスしてしまった。
登山口までは手間取ってしまったが、ここからは気持ちの良い山道が続いていた。
峰谷橋からほぼ真南に進む北斜面で、気温は10度前後で日影ではかなり寒さを感じるが、上り進むうちに体は汗ばんでくる。最初の急坂のイヨ山まで1時間10分。背景の眼下には奥多摩湖が木陰の間に見渡せる。隣の大寺山の仏舎利の白い塔が、右側に高度が上がるにしたがって、全容がハッキリしてきた。2番目のピークは糠指(ヌカザス)山でさらに50分。深く積もった乾燥した落ち葉を踏みしめ進んで行く。鳥の鳴き声も無く、皆のお喋りも少なくなった静かな山道の中で、枯れ葉を踏みしめる皆の足音、それに、川面さんの熊よけの鈴の規則的な音を聞きながら、ひたすら上る事のみを考える。
イヨ山を過ぎ、常緑の樹木から落葉樹に変わり、所々に現われるカエデの紅葉は、息の上がった状態からホットした気分にさせてくれる。
第3のピーク入小沢の峰の頂きの手前の難所、おつねの泣き坂(下写真)は長く、落葉樹の根っ子を掴りながら、上へ上へと高度を上げていく急峻であった。久しぶりに経験した一番の難所であり、某氏曰く、夏の甲斐駒より厳しいと。樹木の葉は、高度が増すにしたがって無くなり、冬の景色となる。
急峻を上りきった緩やかな平な場所が、入小沢ノ峰である。既に12時を回っていたのでランチタイムとする。今の季節の食事は、ほてった体が直ぐに冷え込み始め、食事を早々に済ませ、誰とはなしに出発の支度を始める。
三頭山山頂に近づくと他のハイカーに出会う機会が増えてきた。中央峰と呼ばれる山頂は比較的広く緩やかで、小さな子供もいる家族連れで賑わっていた。都民の森からは高尾山気分で気楽に登れるコースがある。西峰と呼ばれる山頂が隣に座し3mほど標高は高い。ここにも家族連れや、中高年のハイカーの団体で賑わっていた。下山は、笹尾根を西原峠まで下るコースを計画していたが、朝の時間のロスや天候が悪くなってきた理由で、最短時間で下ることができる鞘口峠から都民の森に下る事にした。
都民の森の駐車場には2時半ごろ着いたが、バスの出発まで小1時間待つことになった。曇り空は更に厚い雲に覆われ、霧が時々流れ出してし、3時前でも薄暗くなってきた。
1時間ほどバスに揺られ武蔵五日市駅まで、何時もの立川駅の居酒屋「味工房」で、今日一日の労を美酒でねぎらい、次回での健闘を誓いあった。 長張記
2008.10(第 96回) 滝子山
定例の「山歩きの会」は久しぶりの開催である。先月の筑波山行きは台風の影響で中止となった。6月も山歩きが天候不良で中止され、変わりに高幡不動尊見学となった時の話題の中で、候補の一つとして今日の滝子山が選ばれた。滝子山からの富士の眺めは大月市の秀麗富嶽十二景の一つで、扇山・百蔵山・岩殿山と中央線の北側に沿った山並みにある。
秋の天気は変わりやすい。一日中雨模様の日が2日ほど続けば今度は、これ以上の日本晴れはないという正に絶好の登山日和となる。今日も三日ほど続いた快晴・乾燥・無風と三拍子揃った登山日和となるはずである。今日の参加者は川面さん・山岸さん・川俣さん・金子さん・長張の5名である。滝子山登山口は笹子駅に近いが道証地蔵までの1時間強を稼ぐため、大月駅からタクシーを利用することになった。
朝の清々しい冷えた空気を吸いながら、9時少し前に大月駅から1台のタクシーに5人全員乗り込んだまでは良かったが、運転手は道を知らず降ろされた場所は、道証地蔵の先の林道の終点であった。30分かけて車で登った道を徒歩で下り、道証地蔵に着いたときは10時少し前になっていた。暗い林道に沿ったズミ沢は所々滝が出現する。
薄暗い道を更に沢に沿って進むが、俄かに道は険しく難路となりやがて前進不能となった。急な斜面を登ってみるも山道らしきものは見あたらず。ついに再度、難所を引き返し、沢沿いのルートを避ける捲き路を辿る。路は再びズミ沢に出る。ナメ滝が連続する沢は見事である。
山路で迷ったと思ったら、直ちに元の路を戻ることの鉄側を、体験する事ができた。
しばらくカヤトの間の快適なハイキングとなる。トリカブトの真っ青な花が所々に咲いており、花の時期が終わったフジバカマの大群落が、道の両側一面に種を飛ばす直前の姿となっている。大谷ヶ丸への分岐からまた急な道となる。
為朝伝説の鎮西ヶ池を経て山頂の到着は12時半を過ぎていた。
山頂は広くはないが大勢の登山客が食事をしていた。富士は霞んでいたが近くの山肌は紅葉の縞模様で美しく、今の季節でしか見られない景色となっている。狭い山頂は次々に登山客の食事の場となっていたが、我々は1時少し過ぎに下山開始する。最初の急坂は直ぐに緩やかになり、女坂を下り檜平に出た。そこから間近な三つ峠の横に、大月市秀麗富嶽十二景である富士の姿が、薄く霞んで見ることができた。川俣さんは以前、伊藤さんとお二人でこのコースを笹子駅から歩かれたそうである。
道中一人も出会うことがなく、暗い山道は大変心細かったと話してくれた。しかし、この日はかなりの人が入っており尾根に沿った緩い下りは、笹尾根に似た趣があり快適だ。しばらくして尾根から外れ急斜面を下り沢沿いの路に出る。辺りは薄暗くなる。加えて雨が降り出したというから、女性2人では確かに心細く感じたのはわかるような気がする。
下ること2時間半、中央自動車道をくぐり笹子川を渡り国道20号線に着いた。20号線から遠く高く滝子山の全景を見ることができた。一同、立川駅の居酒屋「味工房」で、今日一日の成果を喜び語り合うことができた。 長張記
2008.09(Bコース) 愛宕山緑地
2008.08(特別企画) 甲斐駒ヶ岳
「山歩きの会」で、南アルプスの名峰「甲斐駒ケ岳」に登るチャンスに恵まれるとは思ってもみなかった。一年ほど前から川面さんから『「甲斐駒」に登ることができれば一生悔いるものはない』と提案され準備されてきた。今回の参加者は金子さん・鈴木さん・川面さん・依田さん・多摩稲門会メンバーではないが、金子さんの郷里の友人である木村さん・長張の6名となる。
初日は、甲府駅着11時27分、駅前から広河原経由でバスを乗り継ぎ、2時40分過ぎに北沢峠着いた。当日はここからが徒歩開始となり、1時間ほどで仙水小屋に着き、ここで宿泊することになる。山小屋は都会にある工事現場の事務所と同じであった。2階の部屋が与えられた寝場所である。一人分のスペースは一畳ほどあり、手足を伸ばして眠ることができそうである。夕食は戸外に用意され、4時半には一斉に食事がはじまった。木村さんから地元の「越乃寒梅」の差し入れ等、持参したご馳走で歓談の時を過ごしたが、他の客は早々に引き上げてしまったので、一同就寝することになった。7時前である。
翌朝、徒歩開始して2時間半ほどの駒津峰からの尾根筋を進んでいる。
更に一時間ほど上り続ける巻き道の途中である。山肌はむき出しになり草木はない。岩肌の表面は風化しもろくなり、靴で擦ると削ることができるが、意外と滑りにくい花崗岩の岩山である。好天に恵まれ空は真っ青で白い山肌とマッチしている。
山頂近くになると富士の位置が、鳳凰三山の右裾から真上になってきた。摩利支天の頂きも見下ろす高さになっている。まだ朝の8時半前で何時もの山歩きの時間帯とは、3・4時間前倒しされており、時間のゆとりは十分にある。
山頂には8時半到着し、軽量のパンで早やめの昼食をとる。
山頂での集合写真の背景は、北岳・間ノ岳・塩見岳などで南アルプスを串刺しするように見通せる。山頂は広く大勢の登山客で賑わっていた。360度の展望は遮るものはなく、北・中央アルプスの連山や、八ヶ岳連山がたなびく雲海の上に突き出ている。隣の仙丈ヶ岳は大きく左右に山裾を広げて目前に雄大に構えている。頂の一部以外は緑の肌で覆われており、男性的といわれる力士のような肌を出した甲斐駒とは相対していた。
9時半には下山に入る。花崗岩の砂礫の山肌をゆっくり下る。
六方石から駒津峰辺りはハエマツの潅木で覆われている。登る時の駒津峰からの薄白かった朝の山容とは違い、3時間後の白い岩肌が陽に照らされた別の姿を見ることができた。
上った時と同じガレ場の道を下る。ハエマツの潅木から森林限界に入り森の中に入ると、甲斐駒の姿は見えなくなり、樹木の間から見える摩利支天がより大きく威圧するように迫ってきた。甲斐駒の中腹に超大なコブが貼りついたような姿は、一度見たら忘れることができない。1時過ぎに仙水小屋に着き、預けていた荷物をまとめ北沢峠まで疲れた足でさらに下山した。峠には既に大勢の帰路を待つ登山客で溢れていた。1時間半ほどバスを待ち広河原から乗合タクシーで甲府駅まで、6時過ぎの列車で八王子駅に向った。念願を達成し満足した顔は、一同真っ赤に日焼けしていた。一日良く頑張った。 長張 記
2008.08(特別企画) 御前山
8月の「山歩きの会」は、例年休みとなっている。ところが、最近この会は熱が入っており、特に今月21日に甲斐駒登山を控え、真夏の最中ではあるがトレーニングのための特別企画を催すこととなった。今回の参加者は、京王クラブの懇親会場で決まった金子さん・川面さん・山岸さん・長張の4名である。
御前山は奥多摩三山の1つで三頭山・大岳山の間にあり、裾まで雄大に広く構え、姿は何処からでも眺めることができる山である。先月の大岳山ハイキングは、炎天下でありながら比較的涼しい山歩きであった事を期待して、続けての奥多摩ハイキングである。大岳山コースと同様の、立川発8時47分発ホリデイ快速おくたま3号に乗り、9時50分終点奥多摩駅に着いた。沢山のハイカーをよそに早々にタクシーに乗り込み、境橋から栃寄沢に入り駐車場まで、そこから徒歩開始である。
境橋バス停留所から沢に沿って本来は歩いて上る坂道であるが、車で行ける終点はまで行った。
舗装された車道はそのまま続いているが、なぜこの場所で下ろされるのかわからない。運転手に聞こうと思ったが、愛想が悪そうなのでやめてしまった。20分程舗装道路を登り体験の森入口に出る。山道はここから始まる。
夏の木々は生い茂り日影をつくりその下は比較的涼しい。曇り空の予報に反して陽がさしているが、木陰は涼しい。
高度が上がるに従って、開花しているレンゲショウマが散見されてきた。隣の御嶽山は、レンゲショウマの群生地として有名であるが、先月は開花には早すぎた。
また、御正体山でも見られたソバナの花も所々で群生していた。ここは、ハイカーが少ないせいか、いろいろな野生植物が豊富に残っているようだ。
森の中の急坂は長かったが、道はしっとり湿り歩き易かった。やがて御前山避難小屋に出る。尾根筋にある小屋には入ることはできないが、新しく立派なものである。正午まで少し時間があるので、そのまま休まず山頂に進んだ。
山頂に近づくと辺りは霧が立ち込めてきた。山頂も高い樹木が生い茂っていた。
尾根筋に沿った長円の山頂は広く、大き目のベンチが10ヶ所ほど点在している。2・3組のハイカーが食事をとっていた。我々もあちこちのベンチでそれぞれ食事をとった。
惣岳山は尾根筋の一部で頂には見えなかった。そこから小河内峠に向かう分岐があるが、真っ直ぐダムに向う大ブナ尾根の斜面を下る。急勾配のガレバのよう道は続くが、傾斜のない広く草刈された公園内の道のような場所もある。サス沢山も山と云うより下る尾根のほんの一部のような場所であった。
奥多摩湖を見下す展望台からの眺めである。急斜面はさらに続きやがてダムの広場に着いた。ダムの広場は別世界である。アソファルトで敷かれた平らな広い場所には、大勢の観光客が見られる。遠い対岸に2台続いたバスが通り過ぎるのが見えた。われわれは次の3時37分発のバスで奥多摩駅行きに乗車し、奥多摩駅前の店で喉の渇きを生ビールで癒すことができた。 長張 記
« Older Entries Newer Entries »