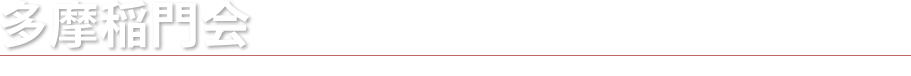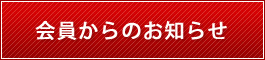Author Archive
7月の俳句同好会
2017-07-23
第43回となる俳句同好会の7月例会は21日午後、多摩市の永山公民館で行われたが、いつもの通りメンバー8人がメールで投句した。うち5人は句会に出席。選句後は合評、作者の自句自解などとなった。
合評の中で原句を直したものが何句もあった。<サクランボ>と片仮名の表記では軽くなるとして平仮名に変えた。また<緑児のごと紫陽花の咲き初むる>は<紫陽花の>を<七変化>として児の成長と変化を感じさせる句とし、さらに<薫風に>と<牛の臭い>が作為的な印象を与えるとされた句の上5は<南風吹く>と直した。
また<実梅落ち>は<実梅落つ>と切って間を置き、<まず>は<まづ>と表記、その他にも「説明や報告になってしまっている」「言い切ってしまって想像の余地がない」などという指摘もあり、推敲の必要があるなどという句も少なくなかった。俳句教室になった句会であった。
(文責・川面)
選句の結果は以下の通り。カッコ内は選句者名、特選句は◎で表記。
蜥蜴一閃路地も荒野に続きけり 辻野多都子(川面◎、萩尾◎、宮地◎、川俣、長張)
世を遠く筒鳥の声いざなへる 川俣あけみ(又木◎、川面、辻野、平松、宮地)
でで虫の時空さぐれる角の先 川俣あけみ(長張◎、川面、萩尾)
月山や照る日重ねてさくらんぼ 川面忠男(川俣◎、辻野、平松)
「バベルの塔」展鑑賞後の上野から
スカイツリー電波乱れず梅雨雲に 川面忠男(辻野◎)
小ささに手も添えかねる蛇苺 宮地麗子(平松◎)
犬連れて子なき女(ひと)坐す青野かな 辻野多都子(川俣、萩尾、又木、宮地)
糊少し固めの甚平まづ一献 萩尾昇平(川俣、平松、又木)
まづ声の登り来たるや草刈女 川俣あけみ(萩尾、又木、宮地)
夏の月しばし眺むる誕生日 宮地麗子(川面、辻野)
実梅落つ過ぎにし恋の数多なり 又木淳一(川俣、辻野)
緑児のごと七変化咲き初むる 又木淳一(長張、宮地)
山背から守る霊木出羽の塔 長張紘一(平松)
荒れ梅雨や故郷(さと)の涙も奪ひをり 萩尾昇平(又木)
梅雨鰯酢の香滲みいる酒の味 辻野多都子(長張)
緑陰のベンチにラジオ今朝も鳴り 川面忠男(長張)
南風吹く牛の臭いも里地かな 長張紘一(川面)
久闊を叙す青蔦の校舎かな 又木淳一(萩尾)
恒例となった納涼カラオケ会
2017-07-23
 カラオケのサークルは第3火曜日の7月18日、例会場である多摩市関戸のスナック「麗」で行われたが、12人が浴衣やアロハの納涼スタイルで参加した。ここ数年、7月は「納涼いねの会」と銘打っている。
カラオケのサークルは第3火曜日の7月18日、例会場である多摩市関戸のスナック「麗」で行われたが、12人が浴衣やアロハの納涼スタイルで参加した。ここ数年、7月は「納涼いねの会」と銘打っている。
当日は乾杯の後、「早稲田スポーツおっかけタイ」長の湯浅さんが早稲田実業の清宮幸太郎選手には早稲田の野球部に入り技術とともに人格を磨いてほしいといった趣旨の発言をした。このように「いねの会」はカラオケに限らず多摩稲門会の会員が情報を伝えたり意見を交換したりする場でもある。
「いねの会」は歌い、飲み、お喋りも楽しむが、最近は「健康にも役立つから」という意識が高まっている。
Aさんの場合、持病にはカラオケがいいと奥さんに勧められて参加するようになり今では常連だ。Bさんは気が向いた時だけ参加してきたが、これまた常連になった。高齢化に伴い誤嚥性肺炎にかかりやすくなるが、それを防ぐには喉を鍛えるカラオケが効果的ということが言われるようになったことも理由だ。
どんな唄でも歌えば効果があるらしいが、とりわけ石川さゆりの「津軽海峡冬景色」がいいという説がある。Cさんは五木ひろしの唄をよく歌うが、当日は第1曲目に「津軽海峡冬景色」を歌った。
北島三郎の「函館の人」も誤嚥性肺炎の予防にはいいとう噂を聞いて筆者も歌った。腹から声、さらに高い声を出すのがいいのだろう。
店のママが「皆さん、日本酒よりも焼酎を飲むようになりましたね」と言った。日本酒は旨いが、血糖値が上がらないようにと気をつけているのかもしれない。「稲の会」は酒の持ち込みが自由で、いつも誰かが酒を差し入れするが、当日は筆者も大分県の麦焼酎をカウンターに置いたところ空になった。
誰かが歌うと手拍子を取ったり、合いの手を入れたりして盛り上がった会になった。デュエットはいつもの通りだが、昭和15年に世に出た「高原の旅愁」を選曲したCさんが「知っている人は一緒に歌いましょう」と呼びかけたので筆者も応じた。長老のDさんは筆者の好きな「東京ワルツ」を歌い、これには筆者も勝手にマイクを持ち、Dさんと肩を組んで歌った。
歌って、飲んで、喋って、そして健康を保とう――これを「いねの会」の謳い文句にしたいと思う。
(文責・川面)
2017.7(第167回)町田市里山散策
2017-07-16
7月11日は町田市の里山散策。町田市西端の八王子市と市境の尾根道。市境は草戸山まで細長く延びて、草戸山山頂の三角点に鋭角に交わっている。八王子市と相模原市の間を割り込み、境川源流まで土地帰属に拘ったように思える。
 集合場所は京王線高尾駅の改札口である。JR南口は普段あまり利用せず、JR北口からバスやそのまま八王子城址方面に進む。案の定間違えて北口に向かったメンバーもいた。
集合場所は京王線高尾駅の改札口である。JR南口は普段あまり利用せず、JR北口からバスやそのまま八王子城址方面に進む。案の定間違えて北口に向かったメンバーもいた。
南口ロータリーから舘ヶ丘団地行きのバスで終点まで。乗客は次々に降り、終点で降りたのは僕らだけとなった。
 バスを降り、少し進むと町田街道にでる。恋路峠と呼ばれる南と北に下る峠である。
バスを降り、少し進むと町田街道にでる。恋路峠と呼ばれる南と北に下る峠である。
向いの駐車場の入口に、解りにくいが尾根道の遊歩道入口がある。入口付近の急登は直ぐに比較的なだらかな遊歩道となる。樹木の茂った日影は涼しかった。梅雨の最中ではあるが、数日前から猛暑が続いていた。尾根道を通る風もあり快適である。
 今日のメンバーは櫻井和子さん、中西摩可比さん、中川邦雄さん、小林勲さん、白井昭夫さん、長張と6名である。
今日のメンバーは櫻井和子さん、中西摩可比さん、中川邦雄さん、小林勲さん、白井昭夫さん、長張と6名である。
ここは多摩市からさほど離れた場所ではない。あまり馴染みがないが、南大沢の戦車道路に、更に多摩の横山の道に繋がる多摩丘陵の主脈にある。尾根道の遊歩道は緩やかで快適である。権現平で休憩、更に雨乞い場の碑に向う。雨乞い場の碑の前には、強い日差しを遮る木々の下に、全員で食事のできるテブールが用意されていた。
 僕ら以外には誰もいない広場は静かであった。拓殖大学の広大な敷地の西側沿いのコースは、高尾山口駅から四辻経由草戸山まで、中川さんは良く利用されるそうである。今日は大学の東側沿いのコースで、同じような樹木の多いコースが続く。どちらも人が少なく、お薦めのコースである。
僕ら以外には誰もいない広場は静かであった。拓殖大学の広大な敷地の西側沿いのコースは、高尾山口駅から四辻経由草戸山まで、中川さんは良く利用されるそうである。今日は大学の東側沿いのコースで、同じような樹木の多いコースが続く。どちらも人が少なく、お薦めのコースである。
 食事の後、全員の集合写真を撮り下山する。高低差のない丘陵であるが、尾根筋を下ると風が無くなり蒸し暑くなってきた。
食事の後、全員の集合写真を撮り下山する。高低差のない丘陵であるが、尾根筋を下ると風が無くなり蒸し暑くなってきた。
若宮八幡社を大きく周りながら下り、正面から真っ直ぐに下る急な石段を下ると人家が見えてきた。長閑な田畑が広がりここも東京都の農家と一体となった貴重な里山の景観を残している。
 人家の通りはカンカン照りで、道にそった川の水は澄んでおり、小さな魚が群れている。西側の源流方面に向かって行くと、広い第1駐車場に入る。さらに進んで行くと湿地緑地の木道になる。若い母子のカップルがシートを敷いて休んでいる。
人家の通りはカンカン照りで、道にそった川の水は澄んでおり、小さな魚が群れている。西側の源流方面に向かって行くと、広い第1駐車場に入る。さらに進んで行くと湿地緑地の木道になる。若い母子のカップルがシートを敷いて休んでいる。
道脇の崖のむき出しの地層に「小仏層」の解説板が設置されている。この地層は1億年前の地層であると説明されている。地層の一部を摘むと容易に薄く剥がれる。若い多摩丘陵はこの時代には海の中であり、丘陵との境に位置する。
 大地沢青少年センターは、休館のようであったが、寝具の入替え作業をするために業者が出入りしていた。ここは町田市唯一の宿泊できる施設と聞いている。
大地沢青少年センターは、休館のようであったが、寝具の入替え作業をするために業者が出入りしていた。ここは町田市唯一の宿泊できる施設と聞いている。
中に入ってみると冷房が効いて涼しく、一人二人と徐々に僕らは勝手に靴を脱ぎ、トイレを利用してロビーでくつろいでいたら、係の者が現われ閉館あると、出されてしまった。御陰で体は冷えてきた。
 青少年センター入口を通り、大戸観音堂から、法政大学のバスターミナルに向かう。
青少年センター入口を通り、大戸観音堂から、法政大学のバスターミナルに向かう。
町田街道は車が多く、蒸し暑い日影のない歩道を一列となってひたすら歩く。辛抱が必要であった。
法政大学バスターミナルからめじろ台駅へ、駅前のコンビニでアイスクリームで体を冷やしてから、聖蹟桜ヶ丘駅の京王クラブに直行、浅井隆夫さんが加わって生ビールで喉の乾きを潤すことができた。近場を活かした暑い暑いハイキングを楽しむことができた。
長張 記
第7回“ボウリングを楽しむ会”のご案内
2017-07-09
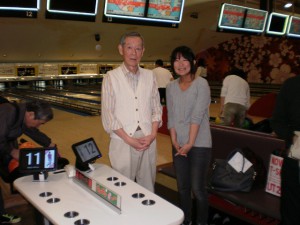 夏を迎え、暑さをひしひしと感じます。ボウリングの会も暑さに負けず、元気いっぱい10本のピンに向かいます。今回も基本に忠実にSKILL UPをはかる会です。楽しいですのでぜひご参加ください。初参加の方も歓迎です。
夏を迎え、暑さをひしひしと感じます。ボウリングの会も暑さに負けず、元気いっぱい10本のピンに向かいます。今回も基本に忠実にSKILL UPをはかる会です。楽しいですのでぜひご参加ください。初参加の方も歓迎です。
記
開催日 2017年8月26日(土)午後3時から6時10分
(集合は午後2時30分)
場 所 永山コパボウル(京王/小田急 永山駅より徒歩約1分) (多摩市永山1-3-4 ヒューマックスパビリオン6F TEL:042-339-9966 )
主 催 多摩稲門会 「ボウリングの会」
<ボウリングを楽しむ会> 午後3時~5時
3ゲーム投げます。当日の事情により変更があることがあります。
募集は9~12名程度。
<懇親会> 午後5時10分~7時10分(2時間)
近くの飲食店で懇親会を行います。
参加費は男性5,000円、女性4,000円。プレー費、貸靴料、懇親会費用を含んでいます。参加費は当日支払いですが、お申し込みの方で当日キャンセルは受け付けません。
<お問い合わせ及びお申込先>(8月12日(土)申し込み締め切りです。)
幹事 稲垣友三 〒206-0041 多摩市愛宕2-4-1-102 TEL:090-2498-0689
メール:yinagaki@e-emotion.jp(参加お申し込みはメールでお願いします。)
囲碁サークル 「多摩白門会」(中央大学)との交流会のご案内。
2017-07-09
先月、6月24日(水)に第2回の交流会を「京王クラブ」にて、多摩白門会(中央大学)3名、稲門会は私、平松の4名と少人数での開催でした。
土砂降り天候の中、開催がどうかと思われたが、さすがに囲碁好きな集まりで、4人全員総当たりで楽しんだ。
参加者 白門会 下六段(囲碁部OB)、宮坂1級、吉原1級、多摩 平松三段
第3回は、7月27日(木)、午後1時30分より、「京王クラブ」にて
囲碁会には、今のところ井石四段、私平松が参加予定。
白門会は、下さん以外は級位者で誰とも楽しく囲碁を打てる相手を探しています。
希望者は会員だけでなく囲碁を楽しみたい人は大歓迎ですので、平松までご連絡を待っています。
(囲碁会無料。懇親会各実費)
(文責-平松和己)
多摩稲門会グルメの会の皆様
2017-07-02
66回目のグルメの会は7月26日(水曜日)午後5時10分から多摩市落合の尾根幹線に近い鰻店「四季の詩」で開きます。
味に定評がある同店での開催は3回目。「土用の丑の日」の翌日に日本酒持ち込みを自由にしてくれたため、銘酒もたっぷり楽しめます。
お店の座敷の広さから募集は12人までとさせていただきます。
早めにお申し込みください。
記
日時: 7月26日(水)午後4時40分、京王多摩センター駅中央改札口前集合。
バスでお店まで移動します。直行される方は必ず世話役の浅井にご連絡ください。
午後5時10分メドで開会します。
会場: 「四季の詩」(多摩市落合6-12 、電話042-310-0747)
会費: 6千円(日本酒の銘酒を世話役が持ち込みます)
連絡先: 携帯電話 090-8877-8865(世話役 浅井)
メールアドレス fwkp7426@nifty.com
申し込み受付は7月24日(月)18時に締め切ります。
“多摩稲門会「第38総会・第64回文化フォーラム・懇親会」開催
2017-07-02
日 時:平成29年6月24日(土) 13時~18時
場 所:京王クラブ(多摩市関戸)
1.「第38回総会」 13時00分~13時30分
大学より、鈴木地域担当部長、稲城、狛江、調布、府中、町田、日野、八王子の近隣稲門会と多摩三田会のご来賓をお迎えし、「第38回定例総会」を開催した。参加者47名。
先ず、藤井副会長より挨拶。依田会長が病気で不在の中、日頃の協力への御礼とともに、現役員が協力し、来年の任期まで努めることを報告。
続いて来賓の紹介。大学より鈴木地域担当部長が来られ、祝辞と大学の動向について話があった。
議長に加来前副会長を指名し、議事進行。長張幹事長が前年、平成28年度(2016年)の活動報告。主要内容。
① 「総会」「賀詞交歓会」等の定例、「文化フォーラム」は3回開催。
② 会報「杜の響き」は3回発行。
③ 11サークル活動中。各活動助成金として、¥5,000円支給。
④ 会員は期首159名、期末会員150名。漸減傾向がつづくものの、準会員の増加でカバーしている。
⑤ 校友会関係は例年通り三多摩支部大会を含め、近隣稲門会等に各出席。
⑥ 寄付金は、従来のWASEDAサポーターズ倶楽部に¥50,000円、稲門祭、広告協賛¥25,000円。新規に役員会の同意の上、早稲田アリーナ募金に¥50、000円寄付。計¥125,000円。
続いて、尾ノ井副会長より会計報告。
① 会員からの会費納入は会員の漸減傾向で予定より減少。
② 「杜の響き」の内製化、催事の減少などで、前期繰越金約¥420,000円から期末に¥620,000円と約¥200,000円増加。
各、報告を異存なく承認。
続いて、長張幹事長より、平成29年度(2017年)活動方針提案。
例年の各行事はほぼ従来通り推進、参加。
① 「文化フォーラム」年2回、「杜の響き」は3回発行予定。
② サークル助成金は従来の¥5,000円から¥10,000円に増加。
③ 寄付金は今年度と同じく、WASEDAサポーターズ倶楽部¥50,000円、稲門祭、協賛広告¥25,000円、早稲田アリーナ基金¥50,000円、計¥125,000円寄付予定。
④ 3年毎の「会員名簿」の作成。
尾ノ井副会長より、予算案説明。
① 会費収入は漸減傾向にあるものの、今年度と同水準を予定。
② 支出は、組織活動、会報のカラー化、外注化、サークル補助費の増額、名簿作成費などを予算化。
③ 当初の繰越金は約¥620,000円から、期末は約¥32,0000円となる見込み。
活動方針、予算案について異議なく拍手で承認。総会終了。
2「第64回文化フォーラム」.講演会 14時00分~15時40分
講演者: 牧久氏 元日本経済新聞社副社長
テーマ: 「昭和解体」(国鉄分割・民営化30年目の真実)発行の意義。参加者 53名。
フォーラム担当の尾ノ井副会長より、今日の講演者を日経同期の川面さんからの紹介によるものであり、牧さんの多摩稲門会での講演は3回目。皆さんにとって馴染みの方となっている。
 今日の講演内容は、氏にとって3作目となる歴史ドキュメントで、4月に講談社より発行された。講演の前に4ページに亘る書評が配布され、説明された。定価が¥2,500円と高価、また厚い上製本にも関わらず、6月末で第5刷、計10,000部と硬い内容の物にもかかわらず多くの人の関心を集めている。
今日の講演内容は、氏にとって3作目となる歴史ドキュメントで、4月に講談社より発行された。講演の前に4ページに亘る書評が配布され、説明された。定価が¥2,500円と高価、また厚い上製本にも関わらず、6月末で第5刷、計10,000部と硬い内容の物にもかかわらず多くの人の関心を集めている。
 国鉄民営化がなぜ昭和の解体なのか?著者によれば戦後の社会体制、労使関係、イデオロギーの争いの場等、その仕組みが「国鉄民営化」により解体、イデオロギーの終焉、労使関係の変遷により、時代を画する→昭和解体に繋がっていると説明された。中曽根元首相を始め、これに関わった当事者によるインタビューによる肉声で、新聞、テレビなどではわからない人間関係が白日のもとにさらされた。政労使間の力関係、更に関係者間のすさまじい折衝の連続、いくつかの経過を辿りながら、現在のJR6社体制となった。
国鉄民営化がなぜ昭和の解体なのか?著者によれば戦後の社会体制、労使関係、イデオロギーの争いの場等、その仕組みが「国鉄民営化」により解体、イデオロギーの終焉、労使関係の変遷により、時代を画する→昭和解体に繋がっていると説明された。中曽根元首相を始め、これに関わった当事者によるインタビューによる肉声で、新聞、テレビなどではわからない人間関係が白日のもとにさらされた。政労使間の力関係、更に関係者間のすさまじい折衝の連続、いくつかの経過を辿りながら、現在のJR6社体制となった。
あらゆる改革には常に陽と陰があり、現在も各社の経営体質、運営、労使関係に問題を抱えながら進行している状態である。講演の後、質問が相次ぎ、会員の間でもこのテーマに対する関心の強さを改めて感じた。
3.懇親会 16時00分~18時00分
冒頭、副会長の平松より開会挨拶、続いて辻野元副会長の乾杯でスタート。益田幹事の司会で懇親会開始。
来賓の多摩三田会加島会長よりご挨拶。続いて、「カラオケ」「歴史に遊ぶ会」「俳句の会」世話人の川面幹事より、活動状況、特に「津軽海峡冬景色」が健康に良い、「おっかけタイ」の湯浅さんの早慶戦、「囲碁」サークルについて平松より、多摩白門会(中央大学)との交流開始。中村さんよりバンド「タマヒカル」の紹介が各あった。
続いて、新人、森悦美さんの紹介挨拶、総会初参加の中保さん紹介。各自、今後積極的な参加を表明された。各サークルでの活躍を期待したい。更に現役の大槻さんを紹介。彼女は法学部1年生で将来弁護士を目指している。浅井さんからはグルメをさておき、近況の政治の動きについて、益田さんからは「大学情報」などが紹介された。等々、時間があっという間に過ぎた。会員同士の話は尽きない。
尾ノ井副会長より、〆として多数のご参加による今日の御礼を述べられた。この後、全員で「都の西北」を声高らかに斉唱、エールの交歓で和やかな内にお開きとなった。
(文責―平松和己)
来 賓 : 早稲田大学地域担当 鈴木嘉久、多摩三田会会長 加島正道、稲城稲門会会長 石井正之、同副会長 山田弘子、狛江稲門会副会長 堀田弘嗣、同常任幹事 大竹英一、 調布稲門会幹事長 芦沢友雄、同副幹事長 中野慶子、八王子早稲田会会長 加瀬明彦、 府中校友会会長 大野正昭、 町田稲門会会長 志村 宏、同幹事長 武田喜和、 日野稲門会副会長 坂本昭夫
会員参加者: 浅井隆夫、新井正子、石井卓治、尾ノ井光昭、有福典夫、加来健一郎、 川面忠男、菊沢光江、子幡嘉之、小林 勲、菊池恵子、白井昭男、白鳥金丸、辻野多都子、田辺繁友、土谷靖雄、浪久圭司、長張紘一、野田豊實、野宇 進、中神尚男、中保 穂、 中村昭夫、平松和己、広田 進、星野英仁、藤井國男、前田光治、益田幸児、又木淳一、 松本靖子、茂木良之、森 悦美、湯浅芳衛、吉川啓次郎、高原 浩、大槻栞佳、 計50名。
山歩きの会 7月例会のご案内
2017-06-25
町田市里山散策
町田市の西端に当たり、八王子市との市境の尾根道を歩きます。この尾根は多摩丘陵の主稜で多摩川水系と境川水系に分ける尾根道です。前半は木々の多い日陰の山道を歩きます。大地沢青少年センターに下ると田畑の広がる長閑な車道から、次第に車の多い車道となり、法政大学キャンパスに入ります。ご検討の上体調にあわせてご参加をお待ちします。
1.日時 7月11日(火)
2.予定コース
八王子市と町田市の市境を歩きます(歩行3時間程度)
○集合 (10:00)京王線高尾駅改札口(JR高尾駅南口)
高尾駅バス(10:10)~館ヶ丘団地バス下車
徒歩開始 舘ヶ丘団地〜清掃工場入口〜権現平~段木入~大地沢青少年センター~
青少年センター入口~大戸観音堂~法政大学
法政大学バス~JR相原駅~JR・京王線橋本駅
○持ち物・装備
・昼食、水、間食等 服装(長袖シャツ等)、帽子、軍手、タオル等、雨具(折り畳み傘)、ストック
○雨天の場合は中止します。迷うような場合は、メールか電話でお尋ね下さい。
参加ご希望の方は、長張(tel 042-337-1792、
e-mail nagahari@ttv.ne.jp)にまでにお知らせください。
第42回俳句同好会
2017-06-18
俳句同好会は毎月第3金曜日、6月は16日午後1時半から多摩市永山の公民館和室で開かれ、8人が投句と選句を行った。投句は各人3句、選句は各人5句で、うち1句は特選句だが、特選句はなくてもよいとした。今回は2人が特選句なしとした。
多摩稲門会のサークル「歴史に遊ぶ会」は5月30日に静岡市の駿府城址公園、久能山東照宮などを散策したが、俳句同好会のメンバー3人が参加して嘱目句を詠んだ。歴史探訪が吟行となったわけで吟行地に対する挨拶句が4句、そのうち<神廟の蹴揚げは高し葵草>、<真つ直ぐに本丸堀の立葵>、<起立せる葵の先は櫓なり>の3句が選に入った。
<実桜の落ちて吉野は遠きかな>は特選句にはならなかったものの5人が選ぶ高得点句になった。選句者の1人が桜の実を持参、「サクランボのように食べたものです」と言った。鳥が桜の実を食べ、糞の種が吉野を桜の山にしたなどと話が弾んだ句会になった。
選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名、特選句は◎で表記。
短夜や夢もつじつま合はぬまま 萩尾昇平(又木◎、辻野、平松、宮地)
青嵐子牛泳げる草の波 川俣あけみ(萩尾◎、川面、辻野、長張)
傷つけしみみずに詫びて鍬休め 萩尾昇平(宮地◎、辻野、長張)
麦秋や日照雨(そばへ)上がりし行幸道 川俣あけみ(川面◎、辻野、長張)
影二つ茅花流しの夕道に 川面忠男(長張◎)
万緑に寝そべりたきや今一度 宮地麗子(平松◎)
実桜の落ちて吉野は遠きかな 川面忠男(川俣、萩尾、平松,又木、宮地)
神廟の蹴揚げは高し葵草 長張紘一(川面、川俣、辻野、又木)
名曲喫茶まだ竹針や外は梅雨 萩尾昇平(川俣、平松、宮地)
起立せる葵の先は櫓なり 又木淳一(川面、川俣)
瀬を速み青葉舟唄最上川 長張紘一(萩尾、平松)
真つ直ぐに本丸堀の立葵 川面忠男(川俣、又木)
大関の名をば惜しめと五月晴れ 平松和己(萩尾)
夏蝶や覗くを待ちて長居せり 宮地麗子(萩尾)
慕情とは矢車草の蒼き風 辻野多都子(川面)
いずれ行く道の介護や梅雨に入る 宮地麗子(又木)
ジャコウアゲハ箸もて拾う幼虫 辻野多都子(宮地)
椎落葉釣り人の目は一点に 又木淳一(長張)
(文責・川面)
2017.6(第166回)由木地区散策・平山城址公園
2017-06-18
6月13日は八王子市由木地区散策の5回目、平山城址公園駅から多摩モノレール中央大学・明星大学駅まで。雨対策のスパッツをまとった中西さんは丁度1時の電車を降り全員集合した。櫻井和子さん、川俣あけみさん、中西摩可比さん、西村 弘さん、川面忠男さん、白井昭夫さん、林 譲さん、浅井隆夫さんと長張の9名である。
 一週間ほど前に関東地方は梅雨入りしたが雨は少なかった。今日は朝から雨模様である。中止したらとのご意見もあったが近場の里山で急坂も少ないこと等で実施となった。
一週間ほど前に関東地方は梅雨入りしたが雨は少なかった。今日は朝から雨模様である。中止したらとのご意見もあったが近場の里山で急坂も少ないこと等で実施となった。
雨の中の「山歩きの会」の実施は、私の知る限りでは初めてである。駅から城址公園までは何回か実施しているので、宗印寺に寄らず右側のコースから丘陵を上る。
 30分程で公園に入り、トイレ前の休憩所で一休み、全員の集合写真を撮ってから、背後にあたるクヌギの道方面に下り、東京薬科大学のキャンパスに向かった。地続きのキャンパスへの出口はフェンスで塞がれていた。
30分程で公園に入り、トイレ前の休憩所で一休み、全員の集合写真を撮ってから、背後にあたるクヌギの道方面に下り、東京薬科大学のキャンパスに向かった。地続きのキャンパスへの出口はフェンスで塞がれていた。
 北門まで大回りしてキャンパス内に入った。北門の守衛さんの説明は、キャンパス内は禁煙となり、学生たちの公園内の喫煙が多く、近所の住民からの非難でフェンスが設置されたそうである。緑に覆われた園内の小道から、樹木の多いキャンパス内に入り下って行くと、大きなため池がある。池の大半がスイレンでおおわれていて、赤い蕾や花が水面に広がっている。
北門まで大回りしてキャンパス内に入った。北門の守衛さんの説明は、キャンパス内は禁煙となり、学生たちの公園内の喫煙が多く、近所の住民からの非難でフェンスが設置されたそうである。緑に覆われた園内の小道から、樹木の多いキャンパス内に入り下って行くと、大きなため池がある。池の大半がスイレンでおおわれていて、赤い蕾や花が水面に広がっている。
 キャンパス内の大通りを右折して薬用植物園に入る。植物園の入り口で備え付けの記名帳に会名と来園者の在住別の数を記入して中に入る。園内に作業者が数人見られるが、他の来園者は見られなかった。
キャンパス内の大通りを右折して薬用植物園に入る。植物園の入り口で備え付けの記名帳に会名と来園者の在住別の数を記入して中に入る。園内に作業者が数人見られるが、他の来園者は見られなかった。
東京薬科大学の歴史は古い。初の私立薬学教育機関で、創立は早稲田大学の2年前の1880年となる。
 植物園は平地の公園の花壇のような見本園と、その背面の自然観察路で構成されている。丘陵斜面の緑に覆われた自然観察路に沿って、色々な薬草が育成保護され、それぞれ植物名の銘板が立っている。今の時期の花の数は少ない。一番高い場所にベンチが用意され、休憩場所となっている。
植物園は平地の公園の花壇のような見本園と、その背面の自然観察路で構成されている。丘陵斜面の緑に覆われた自然観察路に沿って、色々な薬草が育成保護され、それぞれ植物名の銘板が立っている。今の時期の花の数は少ない。一番高い場所にベンチが用意され、休憩場所となっている。
 雨は大粒ではないが、休みなく小雨が降り、靴下が雨で浸みてきている。丘陵を降りて、再び見本園を観察する。植物はすべて薬用植物で管理されている。説明を一つ一つ読んで行くと時間は過ぎ、先を急ぐことにする。雨に濡れた若葉は新鮮である。温室設備もあるが中には入らず先を急ぐ。キャンパスは大きな丘陵の南斜面に位置しており、中央に大学の棟が並んでいるが、遠く離れると周りの丘陵の自然の緑の中に入り込んでいる。
雨は大粒ではないが、休みなく小雨が降り、靴下が雨で浸みてきている。丘陵を降りて、再び見本園を観察する。植物はすべて薬用植物で管理されている。説明を一つ一つ読んで行くと時間は過ぎ、先を急ぐことにする。雨に濡れた若葉は新鮮である。温室設備もあるが中には入らず先を急ぐ。キャンパスは大きな丘陵の南斜面に位置しており、中央に大学の棟が並んでいるが、遠く離れると周りの丘陵の自然の緑の中に入り込んでいる。
 薬草園には何時も寄らず通過していたが、川俣さんの以前からの要望で寄って見た。年間を通して見学をお薦めしたい所だ。
薬草園には何時も寄らず通過していたが、川俣さんの以前からの要望で寄って見た。年間を通して見学をお薦めしたい所だ。
キャンパスの正門を出て、そのまま真っすぐバスターミナルを過ぎ、車道を渡り小道に入り左折する。小道はこの辺りの丘陵に沿った古い農道である。平山通り155号線を渡ると、酪農集落の地域にはいる。この辺りは宮嶽の谷戸と呼ばれる。都内に残る丘陵斜面の周辺の平坦地にある雑木林や農地等の存する貴重な地域で、都の2番目の里山保全地域に指定されている。1番目は五日市の横沢入りの里山である。