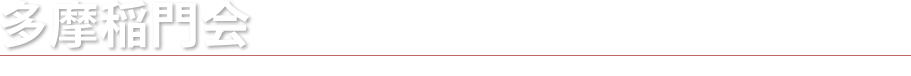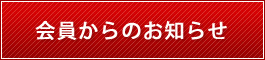Author Archive
早明ラグビー満員プロジェクトの申し込み速報
2013-10-06
参加のご連絡を頂いた方は10月5日現在ではお蔭様で20名となりました。
15日の申し込み締め切りまでまだ日数はありますので何卒よろしくお願いし申し上げます。
9月29日の対筑波大戦に出かけてきました。
筑波は昨年の対抗戦グループでは1位(早稲田は4位でした)の強豪です。
試合は17対17の大接戦となりましたが、早稲田が後半ロスタイム2分の最後のワンプレーで左タッチライン際からの角度のある難しいペナルティーキックを見事にゴール成功して20対17とサヨナラ勝ちしました。
これで弾みをつけて11月3日の対帝京戦・23日の早慶戦を勝ちきり、全勝で早明戦を迎える期待が高まりました。
早稲スポ・オッカケたい(文責:湯浅)
第50回文化フォーラム「山岸起一郎氏講演会」摘録
2013-10-06
9月28日(土)14時~18時迄、聖蹟桜ヶ丘駅近くの「京王クラブ」にて記念すべき50回の文化フォーラムが開催され会員・一般の方を含め鉄道ファンが多数参加された。
・「文化フォーラム」
 長張紘一幹事長の開会挨拶後、湯浅芳衞副会長の司会で、依田敬一会長挨拶、本日の講師多摩稲門会幹事である山岸起一郎氏の紹介があった。
長張紘一幹事長の開会挨拶後、湯浅芳衞副会長の司会で、依田敬一会長挨拶、本日の講師多摩稲門会幹事である山岸起一郎氏の紹介があった。
「SLバンザイ!!!蒸気機関車讃歌」という演題で、「文部科学大臣賞」受賞写真集を中心にSLにかける青春時代から現在に至るまでの思いを熱心に語られました。
山岸氏は富士フィルム在職時代からフォトグラファーとして有名であり、欧米駐在を永年経験され世界のSL・鉄道情報にも通暁されています。プロジェクターには「文部科学大臣賞」受賞写真集から抜粋された黒白画面が次から次へと紹介され、参加者はシンプルかつ一瞬勝負の名画面を食い入るように見詰めていた。
 蒸気機関車は、「人間が発明した人間に一番近い機械」「生きているから息をする」「毎日石炭を食べ 水を飲む 排泄もする」、と素朴な語り口で表現を擬人化された。
蒸気機関車は、「人間が発明した人間に一番近い機械」「生きているから息をする」「毎日石炭を食べ 水を飲む 排泄もする」、と素朴な語り口で表現を擬人化された。
山岸氏は、SLの写真撮影は厳冬期・積雪期に限る、と述べられたが、墨絵の様な雪原を疾駆する漆黒の蒸気機関車の名画面からもその不思議な魅力がよく理解出来る。
「シュ!シュ!なんだ坂・こんな坂」、と思わず後押ししたくなるようなSLの頑張りが伝わってくる。厳寒期の撮影は心身とも困難な事も多かっただろうと想像される。
氏は又、光を捕らえるのが「フォトグラフ」とも述べられた。意味するところは、英語のフォト(光)グラフ(絵)、写真――写偽(一瞬に場面を切り取る)だからとのことです。
現代のデジカメと違い、一眼レフ撮影は一瞬一瞬が勝負、その為に全身を研ぎ澄まして現場で待機するプロの姿を作品から彷彿できる。
参加各位は、山岸氏のプロ魂溢れた講演に、時を忘れ、青春時代に戻り至福の時間を過ごした。
・「満員プロジェクト」12/1 国立競技場開催 早明ラグビーの概略説明
引き続き湯浅副会長から、国立競技場が2020年東京オリンピックの為改装工事に入り、その為現競技場最後の開催となる、と説明があった。今から早明関係者が必至に努力し、この数年間隙間だらけの観客席を満員にしようと呼びかけられ、今年満員の実績があれば、オリンピック後の早明戦も国立で開催される可能性が高くなる、との見通しを述べられた。
湯浅副会長がラグビー部OBの塩沢泰弘氏、早稲田大学ラグビー部現役の学生(3年)、三村・千年原(ちとせはら)君を紹介された。両君から「勝利を期して準備している」ので是非来場して下さい、との挨拶がありそのチラシが参加者に配られた。
賛同される会員は、是非多摩稲門会「おっかけ隊」湯浅隊長にご連絡を!
国立を満員にしましょう!
・「懇親会」
その後、会場を移動、懇親会の場では、平松和巳副会長による司会、加来健一郎副会長の開会挨拶、櫻井和子さんの乾杯で開宴、山岸氏を囲んで、にわか「鉄ちゃん」諸氏が楽しそうに歓談されていた。
筆者も歓談の場に加わり、撮影時の苦労話・SLの魅力を聞き感動、新幹線のない時代、地方から上京時に利用した蒸気機関車に牽引された夜間急行の思い出等参加各位共通の話題は尽きなかった。
現役ラグビー部三村、千年原君は、ラグビー部の話題もさることながら、3年生の就活の現況を報告してくれた。両君の文武両道の健闘を祈ります。
最後に恒例の平松副会長の音頭で校歌斉唱、ご伴侶をなくされた前田光治先輩にエールを送り、稲垣友三副幹事長の挨拶でお開きとなった。
参加者(敬称略)
浅井隆夫、稲垣友三、尾ノ井光昭、加来健一郎、金子宏二、河合一郎、川面忠男、小暮栄治、子幡嘉之、小林 勲、櫻井和子、塩沢泰弘、白井昭男、長張紘一、西尾公孝、西村幸一、橋本 孜、平松和巳、藤井良夫、前田光治、又木淳一、湯浅芳衞、由井濱洋一、吉川啓次郎、依田敬一、林弥太郎、土谷靖雄、菊沢光江、白鳥金丸、半田正久、笛吹(うすい)清志、(以上31名)
一般参加者(1名)
(尾ノ井記)
12月1日(日)国立競技場最後のラグビー早明戦を先行予約チケットで応援しよう!!
2013-09-29
 2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決定して国立競技場が生れ変ります。今年が国立での最後の早明ラグビー戦になります。その為早明両校ラグビー部が中心になり、この伝統の一戦を盛り上げようとの想いから「国立をホームにしよう」プロジェクトが立ち上がりました。国立を満員にして現役、卒業生が一体となった応援をしよう!と多くの学生サークルが参画し色々とアイデアを出している最中です。
2020年東京オリンピック・パラリンピック開催が決定して国立競技場が生れ変ります。今年が国立での最後の早明ラグビー戦になります。その為早明両校ラグビー部が中心になり、この伝統の一戦を盛り上げようとの想いから「国立をホームにしよう」プロジェクトが立ち上がりました。国立を満員にして現役、卒業生が一体となった応援をしよう!と多くの学生サークルが参画し色々とアイデアを出している最中です。
応援席を早稲田カラー一色にした新しい応援スタイルも楽しみです。
今年の「オッカケたい」はWASEDA CLUBの先行予約チケット制度を利用してバックスタンドA指定席の観やすい席で早稲田の展開ラグビーと明治の強力FWがぶつかり合う伝統の一戦を賑やかに気合を入れて応援します。
多摩稲門会として一括申し込みますので席は隣り合って座れます。ラグビー部OBの塩澤、有田会員も駆けつけます。
・
(申し込み要領等)
①早明戦キックオフ日時・・・12月1日(日)14時
②観覧席・・・バックスタンドA指定席:2,500円(大人、子供同額)
③申し込み先・・・湯浅芳衞 自宅電話:042-374-9140
メール:yuasa1426@alto.ocn.ne.jp
④申し込み方法・・・氏名、チケット枚数を明記の上、メールにて申し込み下さい。
(電話でも結構です。)
⑤申し込み締め切り・・・10月15日(火)
⑥チケット代金支払い方法・・・10月21日迄に下記口座に振込みをお願いします。
(振込み手数料はご負担をお願いします。)
振込み後湯浅宛ご一報をお願いします。(メール又は電話で。)
振込み先:みずほ銀行丸之内支店
口座番号:普通預金 1521285
口座名義:湯浅芳衞
⑦その他
1)チケットの受け渡し方法は別途ご連絡します。
2)締切り後のキャンセルはお受け致しかねますので、予めご諒承下さい。
3)当日の“応援ツアー”の実施要領は後日ご連絡します。
試合終了後は新宿ライオンで「美酒の会」をやります。
“早稲スポ・オッカケたい”(文責:湯浅)
9月のグルメの会 落ち着いた雰囲気と多彩な料理で熱弁も。
2013-09-29
43回目のグルメの会は9月25日、多摩センター駅前の「かごの屋」で開いた。駅から徒歩3分の多摩ニュータウン通り沿いにあり、大きな看板がひときわ目を引く。多摩市では珍しい本格的料理店ながら、料金はまずまずで、居酒屋よりもかなり居心地がよかった。
 夏バテの影響もあって常連の不参加者がいつもより多めで、女性の参加者はゼロ。とはいえ、季節の移ろいは激しく、猛暑から一転この日は秋風が吹いて10人の参加者の多くが長袖姿だった。
夏バテの影響もあって常連の不参加者がいつもより多めで、女性の参加者はゼロ。とはいえ、季節の移ろいは激しく、猛暑から一転この日は秋風が吹いて10人の参加者の多くが長袖姿だった。
まずは元多摩稲門会会長の中川邦雄さんの音頭で乾杯。サントリープレミアムモルツの生ビールがのどをうるおしてくれた。トコロテンやヤマモモ、鴨ロースの前菜に続いて、タイとイカ、甘エビの刺身が出された。このころには、日本酒や焼酎、赤ワインなど各自好みの酒を次々と注文。レンコンまんじゅう、海老の五色揚げや野菜の天ぷら、茶碗蒸しのあと、牛シャブの小鍋がふるまわれた。
「かごの屋」は魚だけでなく、ステーキなどの肉も楽しめる多彩なメニューが自慢で、いずれも味は悪くない。
恒例の参加者全員によるショートスピーチでは、2週間ほど前に決まった2020年開催の東京五輪が話題に上った。元NHKアナウンサーの西村弘さんは1964年の東京五輪を回想し、テレビカメラのレンズが4本からズーム1本に減り、録音機も半分になった、と技術革新の目覚ましさを語った。多摩稲門会の長張紘一幹事長は「あの当時みんながんばったからこそ、現在こうやって飲み食いできる」。
川面忠男さんは高尾山の300回登頂を目指してきたが、「エキサイティングな感覚を持ち続けた方がいい」。中川さんは「死ぬ前の晩まで元気でいたい。とにかく歩くこと」とおふたりとも元気さの秘訣を披露してくれた。
弁護士の河合一郎さんは法律相談の難しさをひとくさり。「2、30分の短時間では回答も方向づけ程度しかできない。私は年ですから分かりません、と言ってしまうことも」と苦笑い。「でも、健康にはいい」そうだ。
話題は広がり、ジャズ、運転免許更新、囲碁、コンピュータ―、弔辞など「多彩」だった。
最後に世話役が、安倍政権が集団的自衛権の行使を目指し、憲法解釈を変えようとしていることに危惧を示した。「戦後68年間の平和が脅かされている」。
宴は大いに盛り上がり、松茸入りのせいろご飯を味わってお開きとした。ひとり5千円で飲み放題だった。
(世話役 浅井隆夫)
「山歩きの会」A・Bコース 八重山(531m)・能岳(543m)
2013-09-29
八重山は、上野原市市街地の北側にある低山です。歩きやすい路や展望台施設などが一帯に整備されていてトレッキングには最適な環境となっています。晴れていれば富士山や丹沢、道志山塊はじめ雨降山、扇山、不老山、倉岳山などの大展望の眺望が楽しめます。ご検討の上、体調にあわせてご参加をお待ちします。また、何時もの山歩きの後の懇親会は、川面さんの高尾山登頂300回記念祝賀会を兼ねて京王グラブで行います。
1.日時 A・B・Cコース 10月19日(土)
2.予定コース
A・Bコース 八重山(531m)・能岳(543m)(歩行3時間)
○集合 (8:20)京王線聖蹟桜ヶ丘下りホーム後寄り
(8:28)急行高尾山口行乗車→(8:45)京王線高尾駅乗換
(9:00)JR高尾発ホリデー快速富士山1号乗車→(9:16)上野原駅着
(9:26)新井方面行きバス(富士急)→大堀バス停着(9:38)
徒歩開始 大堀バス停→(10m)中学校前→(50m)展望台→(20m)八重山 →(15m)能岳(昼食)→(60m)西沢泉橋→(20m)新井バス停(13m)(徒歩の場合は47m)→上野原駅
*新井発バス 13:27 14:00 14:52 15:19
○持ち物・装備
・昼食、水、間食等 服装(長袖シャツ・ウインドヤッケ・ジャンパー等)、帽子、軍手、タオル等、雨具(折り畳み傘)、ストック
○雨天の場合は中止します。迷うような場合は、電話でお尋ね下さい。
Cコース
京王クラブ直行コース
16時から京王クラブ1Fで、川面さんの高尾山登頂300回記念祝賀会を開催します。定員10名ほど。荒天でA・Bコースが中止された場合は、Cコースのみ開催いたします。
参加ご希望の方は、金子(tel/fax 042-374-1525、
e-mail kjkaneko@suou.waseda.jp)にまでにお知らせください。
2013.09(第138回)不老山・高指山
2013-09-29
9月21日、久しぶりに例会が開催された。不老山は今年6月に予定していたが、荒天のため中止した。また、7・8月は特別企画として北・南アルプスの高山を目指し本来の例会は暫くお休みしていた。
今週始めに猛烈な台風が中部・関東に襲い、そして過ぎ去った後の台風一過の秋空が一週間ほど続いていて、この日も好天。
 中央本線上野原駅からバスで終点に近づいた時、一つ手前のバス停脇の路肩に駐車した宇田川さんが歩いていた。バスは停車して彼を乗せ、終点不老下バス停で全員下車した。
中央本線上野原駅からバスで終点に近づいた時、一つ手前のバス停脇の路肩に駐車した宇田川さんが歩いていた。バスは停車して彼を乗せ、終点不老下バス停で全員下車した。
今日のメンバーは、川面忠男さん・橋本孜さん・宇田川登さん・上杉雅好さん・金子宏二さん・長張紘一の6名となった。僕らの外、数人の乗客で出発したバスは直に僕らだけの貸切りとなっていた。
 眩しいほどの秋の日差しを浴びながら、9時10分徒歩開始。彼岸花が道際に咲き誇っている。静かな車道を暫く登って行く。
眩しいほどの秋の日差しを浴びながら、9時10分徒歩開始。彼岸花が道際に咲き誇っている。静かな車道を暫く登って行く。
秋の日差しは強く明るかった。日陰が恋しくなるころ、やっと車道が終り山道となり樹林の中に入ることができた。
 蝉の声が聞こえているが、高度が増すに従って中央高速道路からの騒音が絶える事なく聞こえてきた。数日前の台風により、小枝が足元に散在しているが荒れているほどではない。展望のきく金比羅大権現から一時間弱、11時前に不老山山頂に着いた。思ったより急峻の登りだった。お昼には少し早い時間であったが、他に開けた場所がないのでここで昼食とした。
蝉の声が聞こえているが、高度が増すに従って中央高速道路からの騒音が絶える事なく聞こえてきた。数日前の台風により、小枝が足元に散在しているが荒れているほどではない。展望のきく金比羅大権現から一時間弱、11時前に不老山山頂に着いた。思ったより急峻の登りだった。お昼には少し早い時間であったが、他に開けた場所がないのでここで昼食とした。
 山頂は樹木で覆われていたが、南側は開けていて道志の山並み、その背後の丹沢山塊や富士も、もやのかかった中で一望できる。眼下にはほぼ満車の談合坂の下りサービスエリアがあり、ゴルフ場があり、四方津の街並みが広がっている。涼しい風が吹き上げたかと思うと、熱風に変わって吹き上げる奇妙な風が吹いていた。色々な蝶が目の前の草むらの上を戯れている。
山頂は樹木で覆われていたが、南側は開けていて道志の山並み、その背後の丹沢山塊や富士も、もやのかかった中で一望できる。眼下にはほぼ満車の談合坂の下りサービスエリアがあり、ゴルフ場があり、四方津の街並みが広がっている。涼しい風が吹き上げたかと思うと、熱風に変わって吹き上げる奇妙な風が吹いていた。色々な蝶が目の前の草むらの上を戯れている。
 ベンチに地図を広げ、839mから遠望できる山々の同定を行う。ゆっくり休憩したあと徒歩開始。高指山まで樹林の下で高低差のない尾根道を一列になって進んでゆく。高速道路から休む事なく聞こえていた騒音は不老山に遮られ、静粛な山となった。緩やかな尾根道は山頂に近づくに従い急登となり休み休み進む。数日前の大雨もすっかり乾いており滑る心配はなさそうであった。
ベンチに地図を広げ、839mから遠望できる山々の同定を行う。ゆっくり休憩したあと徒歩開始。高指山まで樹林の下で高低差のない尾根道を一列になって進んでゆく。高速道路から休む事なく聞こえていた騒音は不老山に遮られ、静粛な山となった。緩やかな尾根道は山頂に近づくに従い急登となり休み休み進む。数日前の大雨もすっかり乾いており滑る心配はなさそうであった。
 12時少し過ぎたころ高指山の山頂に着いた。不老山より高く911mは今日の最高度である。山頂の周りの樹木は生い茂り眺望はなかった。雨降山から権現山に続く分岐点でもある。東方向の和見峠に向けて下山開始する。山麓には間伐された杉材はそのままの状態で散在している。中には高枝が絡まり垂直に宙吊りになっている材もあり、その下を恐る恐る過ぎて行く。
12時少し過ぎたころ高指山の山頂に着いた。不老山より高く911mは今日の最高度である。山頂の周りの樹木は生い茂り眺望はなかった。雨降山から権現山に続く分岐点でもある。東方向の和見峠に向けて下山開始する。山麓には間伐された杉材はそのままの状態で散在している。中には高枝が絡まり垂直に宙吊りになっている材もあり、その下を恐る恐る過ぎて行く。
急登をゆっくり下り一時間弱、道幅は急に広い車道となる。車道と言っても舗装はされず斜面を荒削りしたままで、これから整備する林道の様であった。少し進んだ所の標識をみてこの場所が和見峠であると確認できた。高指山頂の分岐にも表示が無かった。この山域の道標が少なく、要注意だ。
 更に下りやがて建物の屋根が梢越しに見え、街並みに近づいてきた。秋の七草の萩や葛の紫の花が印象に残る長閑な田舎道は人通りもない。今日一日の山道は、誰にも出会うことのない山歩きであった。甲東小学校前のバス発には1時間程の余裕があり、街中の日影の平らな広場で休み時間調整。ここにも彼岸花が咲いていた。
更に下りやがて建物の屋根が梢越しに見え、街並みに近づいてきた。秋の七草の萩や葛の紫の花が印象に残る長閑な田舎道は人通りもない。今日一日の山道は、誰にも出会うことのない山歩きであった。甲東小学校前のバス発には1時間程の余裕があり、街中の日影の平らな広場で休み時間調整。ここにも彼岸花が咲いていた。
バス停脇に駐車している宇田川さんと別れた。僕らは駅手前の本町3丁目行きのバスに乗り、そこで上野原駅行きに乗り継いで駅に向かった。
長張 記
日野稲門会「ハイキング同好会」に参加して
2013-09-22
9月21日(土)都立平山城址公園と七生丘陵散策に参加して来ました。
好天に恵まれ、平山城址公園駅に12名(敬称略)(鈴木リーダー、松島サブリーダー、高田会長、中西最年長86歳、鷹尾、高橋、荒井紅一点、英、長谷川、吉原、玉木、青木)が集まった。
 準備体操の後、3時間のハイキングがスタートした。平山城址公園ー季重神社ー六国台ー猿渡の池ー展望広場ー旧多摩テック外周路ー多摩動物園駅ー明星大学ー日野第三中ー高幡台団地ーおふろの王様(入浴の後昼食・懇親会)。
準備体操の後、3時間のハイキングがスタートした。平山城址公園ー季重神社ー六国台ー猿渡の池ー展望広場ー旧多摩テック外周路ー多摩動物園駅ー明星大学ー日野第三中ー高幡台団地ーおふろの王様(入浴の後昼食・懇親会)。
皆様気のよい方々で、全ての方と会話をしながらハイキングを楽しむ事が出来ました。
現在の家に45年も住んでいながら、平山城址公園ははじめてであり、最近1時間弱しか歩いていなかった為小生にとっては、素晴らしい一日になりました。
(文責 青木康成)
第64回日野稲門会ハイキング同好会(報告)
1.実施日 2013年9月21日(土)晴れ
2.行き先 平山城址公園・七生丘陵散策路コース
3.リーダー 鈴木 武彦・サブリーダー 松島 正明
4.参加者 荒井洋子・鈴木武彦・鷹尾清文・高田敏雄・高橋敏夫・玉木雅治・
中西摩可比・長谷川洋文・英 武・松島正明・吉原正・青木康成(
多摩稲門会会員)以上12名(敬称略・五十音順)
5.概要
晴天のハイキング日和に恵まれ、京王線平山城址公園駅前に8時30分に集合
し、JA野菜直売店駐車場に移動し、当日の行程説明、多摩稲門会会員の初参加
もあり参加者全員の自己紹介、準備運動を終え8時45分スタートしました。
先ず都立平山城址公園に向かい丘陵散策路をゆっくりとのぼり公園入り口で休
憩をとる。
休憩後、季重神社に祈願し見晴台である六国台を目指す。六国台は樹木の葉が
繁って遠くの山並みをさえぎり、展望はところどころ見られるだけでした。
9時35分六国台を出発して公園の外周路を猿渡りの池・展望広場を目指す。
平山城址公園は山あり、谷あり、池ありと高低差があり、森林浴も楽しめる場
所でした。公園を10時30分に出発し、一路京王線多摩動物公園駅を目指す。
2名の参加者が午後に予定が入っており、多摩動物公園駅で一次解散した。
11時30分駅を出発し、七生丘陵を最終目的地であるお風呂の王様多摩百草
店を目指し、12時15分に予定より少し遅れましたが無事到着しました。
その後お風呂に入り汗を流しさっぱりとして食堂に移り恒例の反省会を行い15
時10分に今日一日の行程を締めくくりました。
当同好会も年々参加者が減少傾向となり、今年度から新しく多摩稲門会とのハイキング交流が始まりました。
今回のハイキングには多摩稲門会の青木氏の初参加があり楽しく交流できました。
多摩稲門会の企画で参加可能なものがあれば私たちもどんどん参加したいものです。
多摩稲門会グルメの会の皆様
2013-09-11
43回目のグルメの会は9月25日の水曜日に、京王多摩センター駅から徒歩3分の和食としゃぶしゃぶの店「かごの屋」で開きます。今回は定例日の第四水曜日に開催します。前回のグルメの会(高尾山ビアマウント)は開催日を土曜日にずらして若い人が参加し、いつも以上に盛り上がりました。今後、開催日を柔軟に変更してさらに多くの人が参加できるようにしていくつもりです。
かごの屋は、おしゃれな雰囲気の店内で、新鮮な刺身や寿司、牛や豚のしゃぶしゃぶやステーキなどが楽しめます。しかも値段はリーズナブル。ビールなどのノンアルコールドリンクやウーロン茶などのソフトドリンクもありますのでお酒が飲めない人も参加できます。下方にメニューを載せました。
飲み放題で、生ビールは別料金ですが、瓶ビールや芋・麦の焼酎、日本酒、赤・白のワイン、ウイスキー、梅酒、レモン、ライムなどのサワー、ノンアルコールではビールや梅酒、カシスオレンジテイストがあります。
記
日時 9月25日(水)午後5時、京王多摩センター駅中央改札口集合。
会場 「かごの屋多摩センター駅前店」(042ー311-1351)
会費 5千円(飲み放題込み)
参加 参加される方は9月23日(月)までに浅井にご連絡ください。
携帯電話 090-8877-8865
メールアドレス fwkp7426@nifty.com
【しっとり会席プラン】集(つどい)コース
・季節の前菜 ・刺身 ・煮物 ・揚げ物 ・茶碗蒸し ・牛しゃぶ小鍋 ・季節のせいろご飯
・香の物 ・デザート ・飲み放題
ゴルフ会
2013-09-08
 平成22年5月よりスタートさせた「新生多摩稲門ゴルフ会」の第8回は、9月4日(水)開催予定であったが、初めて悪天候に見舞われてしまった。
平成22年5月よりスタートさせた「新生多摩稲門ゴルフ会」の第8回は、9月4日(水)開催予定であったが、初めて悪天候に見舞われてしまった。
初参加の河合さん、中神さん、川畑さんを加え15名の参加者が集まり盛況裡に終了する予定であったが、スタート直前になって予報通りに天候が急変した上、雷まで鳴り出し為第1組のトップバッター中神さんがティーアップしたところで、幹事(上條さん、橋本さん)の好判断で中止とした。
一胆全員(河合、中神、川畑、上條、橋本、白石、稲積、鈴木、尾ノ井、加来、油井濱、藤井、吉田、広田、青木)コンペルームに集まり、懇談をしながら再開催日を10月3日(木)に決定した(上條さんに予約およびフィーの御高配をして頂きました)。「多摩カントリークラブ」で開催。
今度こそは、恒例通りに絶好のゴルフ日和のもと楽しい会となる様に祈念します。
スケジュールのなくなった者6名が、「いねの会」の場所「麗」に集まり、アルコールを飲みながらカラオケで懇親を図った。
(文責:青木康成)
10月のコートのご案内です。奮って ご参加ください!
2013-09-08