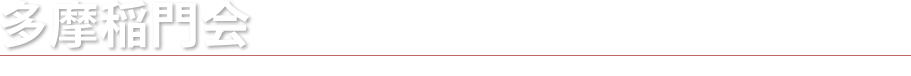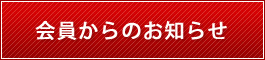Author Archive
多摩稲門会グルメの会の皆様
2013-07-07
今年は梅雨入りが早く、遠からず明ける見込みです。しかも猛暑の公算大。
そこで42回目のグルメの会は7月27日の土曜日に、高尾山にある「ビアマウント」で開きます。定例日の第四水曜日を土曜日にずらしたのは、若い人が参加しやすいようにしたためです。
夏の真っ盛りに生ビールや焼酎などの飲み放題と、中華料理とイタリアン中心の和洋中60種類以上の食べ放題を楽しみながら、暑さを吹き飛ばそうという趣向です。
今年は昨年に比べ、入場料が男性2百円、女性3百円いずれも値上げされましたが、生ビールにサントリープレミアムモルツと一番しぼりのフローズンが新たに加わりました。オランダのハイネケンやスーパードライ、黒生などのいずれも生ビールや焼酎、ワイン、日本酒、果実酒、ハイボール、変わったところではコーヒーリキュールなどの飲み放題を山中で楽しめます。
料理では、その場で切ってくれる生ハムや自家製麺を使ったラーメンと焼きそば、梅や昆布、海苔のお茶漬けなどが増えました。
会場はケーブルカーの終点駅「高尾山」から歩いて4,5分の見晴らしのいい高台にあります。2時間制限制で、男性3千5百円、女性3千3百円です。お手数ですが、端数は必ず硬貨でご用意ください。
「小銭は面倒」という方は、4千円お支払いいただければ、おつりはグルメの会の剰余金として活用させていただきます。
雨天でも、屋根付きの席が300席ほど(全部で約700席)あるので、決行致します。
記
日時 7月27日(土)午後5時、ケーブルカー「高尾山駅」(終点駅)改札口集合。
京王線高尾山口駅から徒歩5分ほどでケーブルカーのふもとの駅「清滝駅」に着きます。そこから終点駅の「高尾山駅」まで上がってください。
登山される方は、午後2時に「清滝駅」改札口にお集まりください。ただし、雨天の場合、登山は中止します。天候不順の場合は、当日午前10時に登山決行か否かを、メールでご連絡します。下記の携帯電話でもお答えします。
場所 「高尾山ビアマウント」(042ー665-9943)
会費 男性3千5百円、女性3千3百円
参加 参加される方は7月24日(水)までに浅井にご連絡ください。
携帯電話 090-8877-8865
メールアドレス fwkp7426@nifty.com
多摩稲門会「第34回定例総会・第49回文化フォーラム・懇親会」
2013-07-07
平成25年6月22日(土)13時から18時、京王聖蹟桜ヶ丘にある「京王クラブ」にて「第34回多摩稲門会定例総会」・第49回多摩稲門会「文化フォーラム」が開催されました。
・「総会」
総会開催に先立ち昨年度に逝去された和田好一殿、甲野善勇殿、按田 弘殿、古屋与志夫殿4名の会員に対し黙祷が行われた。定例総会の部の司会は、加来健一郎副会長が行い、依田敬一会長の挨拶、全来賓の紹介後、大学・校友会から早稲田大学レジデンスセンター課長廣瀬剛氏から大学の近況報告、立川稲門会志村順子会長から来賓代表挨拶と続き、長張紘一幹事長、又木淳一会計幹事から平成24年度活動・決算報告、25年度活動計画・予算の説明・審議に入り、中里保司会員の幹事追加選出と合わせて原案通り会員各位の賛成を得て承認された。
・「文化フォーラム」
引続き第49回文化フォーラムは、湯浅芳衛副会長の司会で進められ、塩澤泰弘氏(元ラグビー部)から紹介があった。OBでもあり元共同通信記者の松瀬学氏を講師に「ワセダスポーツとオリンピック」という演題で、約2時間、取材を通じてヒーロー達の人間像に迫った実話をされた。
ご自身は学生時代ラグビー部で活躍されており、関係分野では、当時指導を受けた大西鉄之佑監督の熱血ぶり、OBで惜しくもイラクで銃弾に倒れた外交官奥克彦氏の人間性などを熱っぽく語られた。
今年のワセダスポーツの成績は低迷、苦悩しており、打開するには早稲田魂の原点(ハングリー精神の復活・創造力の発揮)に帰ることが必要とも指摘された。
帝京大学の強さの秘密は、ラグビーを通じ社会に通用する人格形成力を磨いているからであり、5連覇の可能性も高い。その源泉は個々の力と事前準備の良さ(ストレングス&コンディショニング)とも語られ、納得しきりである。母校早稲田は現状打破のため、謙虚かつ挑戦的な帝京大学の姿勢を見習うべきだ、と思う。
2020年五輪の開催について、東京の開催都市評価が高いが、マドリッドも強敵である。
第1回投票でマドリッドが落選した時は、東京の当選の可能性が強いとの見通しも述べられた。
・「懇親会」
続いて懇親会に移り、平松和己副会長による司会で開宴、大学側・近隣稲門会の来賓・
学生・一般参加25名、当会会員44名と多数の方が参加された。
乾杯の後、来賓を囲んでスポーツ、学生時代の思い出等歓談の輪が広がり和やかに宴が進行した。
早稲田グッズの展示、現役学生の早稲田祭企画説明等があり、OB諸氏の話題も尽きなかった。
最後に恒例の平松副会長の音頭で校歌斉唱、エール交換があり、稲垣友三副幹事長の閉会挨拶でお開きとなった。
来賓者(敬称略):
早稲田大学レジデンスセンター課長 廣瀬 剛、多摩三田会副会長 伊澤 健夫、稲城稲門会会長 河合 一郎、狛江稲門会副会長 長塚 弘、立川稲門会会長 志村 順子、調布稲門会会長 元木 勇、同副会長 小笠原忠八郎、八王子早稲田会会長 松村 光雄、府中校友会幹事 澤田 浩宜、同監査 中村 圭吾、町田稲門会副会長 木内 宗雄、同副幹事長 新村 宏、日野稲門会副会長 小笠原 豊、同事務局長 生川 博、(以上14名)
参加者(敬称略):
青木康成 浅井隆夫 有田幸平 石井卓治 稲垣友三 井上一良 今村次郎 宇田川登 尾ノ井光昭 加来健一郎 金谷勇作 金子宏二 上条喜義 川面忠男 子幡嘉之 小林 勲 佐藤達雄 佐藤喜昭 鮫島総一郎 塩沢三男 白井昭男 田中亮介 田辺繁友 堤 香苗 中神尚男 長張紘一 浪久圭司 西村幸一 橋本 孜 半田正久 平松和己 広田 進 藤井國男 星野英仁 又木淳一 茂木良之 三浦幸一 水谷 求 水野晴行 湯浅芳衞 由井濱洋一 吉川啓次郎 依田敬一 若杉公朋 (以上44名)
校友・学生及び一般参加者(11名)
(尾ノ井光昭 記)
8月のコートのご案内です。奮って ご参加ください!
2013-07-07
8月のコートが確定しました。
●場所:一本杉公園内テニスコート
▼開催日時等:
・8月06日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
・8月13日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
・8月20日(火) 8:00~10:00 Aコート・Cコート・Dコート
・8月27日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
稲垣コーチによるレッスンもあります。是非、コートへお出でください。
お問い合せは:中里 保司/Mail
to ⇒ nkzto@live.jp
布田道と小島資料館
2013-06-23
多摩稲門会のサークル「歴史に遊ぶ会」は6月16日、江戸古道の「布田道」を散策し、町田市小野路の「小島資料館」を見学した。「父の日」の第3日曜になったのは、資料館が開館するのは第1、第3日曜日の午後だけであり、それに合わせたものだ。
当日は午後1時、京王相模原線永山駅前(多摩市)のバス停留所に10人の会員が集まった。浅井さん、尾ノ井さん、川俣さん、櫻井さん、白井さん、長張さん、橋本さん、星野さん、湯浅さん、それに世話役の川面で、鶴川行きのバスに乗車、別所(町田市)で降りた。
布田道は調布市布田と町田市小野路を結ぶが、途中の別所から小野路までは徒歩で30分少々の道のりである。多摩丘陵を里山にする道が続く。崖が切れたところは畑や田になっている。斜面が竹林になっている箇所もある。周囲に現代風の建物がなく、江戸時代に戻っても同じような景観であろう。
遠くで若い女性たちが農作業をしている光景が見られた。道から引っ込んだ場所に駐車していた車に恵泉女学園の文字があったので、女子大生たちの体験学習であろうかと推測した。
急坂になり、切通を下る。右に行けば多摩市の一本杉公園、左に行けば小野路の分岐点になる。小野路は鎌倉時代、鎌倉と府中を結ぶ宿場であった。大山信仰が盛んになった江戸時代は大山街道の宿場であった。
小野路の名主であった小島家の庭は江戸時代には天然理心流の剣術の稽古場であった。幕末には近藤勇が新撰組の隊長になる前、4代目の師範として出稽古に来た。調布が故郷の近藤が布田道を通って来たという。
小島家は現代に残り、併設した「小島資料館」には近藤所縁の品が展示されている。内部は当時のままの母屋で小島館長の説明を聞いた後、資料館を見学した。背に髑髏のマークが入った近藤の稽古着を見た。新撰組資料は100点あるとのことだが、近藤の汗を吸った稽古着はそれらの最たるものであろう。
小島資料館から小野神社に向かった。平安時代の学者、小野篁を祀ったのが由緒になっている。篁の子孫が武蔵の国司となった際に創建したとされる。
雨上がりの日で、布田道は狭いながらも舗装されていたが、所々で泥道になっていた。帰りは小野路と一本杉公園の分岐点まで戻り、丘陵を超えて一本杉まで歩くつもりであったが、舗装されていない山道は悪路になっていると思い、小野路から広い舗装された道を歩いて別所まで戻り、バスで多摩センター駅に行った。駅前の店で4時から懇親した。参加者から楽しかったという声を聞いた。
(川面記)
高幡不動のアジサイ見物
2013-06-16
多摩稲門会のサークル「山歩きの会」は6月の例会日である15日、「あじさい祭り」を開催中の高幡不動尊金剛寺(東京都日野市)を訪ねた。当初は不老山に登る予定であったが、天気は午後から雨になるという予報のため山登りは無理と判断、寺の境内や高幡山という裏山に咲くアジサイ見物に変更した。
午前10時半、京王線高幡不動駅の改札口に櫻井さん、金子さん、長張さん、川面の4人が集まった。参道を通り仁王門をくぐって不動尊の境内に入った。種々様々なアジサイの鉢植えが展示されている。寺僧が現れて説明した。「やまあじさいは咲くのが早い。今は見頃を過ぎて、花が裏返しになっている」。花を見てみると、確かに寺僧の言う通りであった。やまあじさい以外のアジサイは今が盛りで、境内の随所を彩っている。種々様々でアジサイそれぞれの名前は覚えられない。「ここは多摩のアジサイ寺だ」。誰ともなく呟いた。
小ぶりの山門をくぐり、大日堂から先に進むと墓地に入った。高幡山を左に見ながら歩く。「藤蔵の墓」の案内が目に止まる。これは200年前にあった生まれ変わり物語の主人公の墓である。中野村(現在の八王子市)に生まれた子供が8歳になって前世は程久保村(現在の日野市)で6歳の時に亡くなった藤蔵だと言った。まだ藤蔵の家を訪れたことがないのにもかかわらず家の様子を知っているなど話が符号するので人々に信じられたという怪綺談である。
墓地の突当りにエレベーターがあり、上ったところ新墓地に出た。「山歩きの会だから山に上ろう」と道を探した。道はなかなか見つからなかったが、墓地の奥で「あった!」という長張さんの声がした。細い道が斜面に細く見え隠れしている。上の方に人の姿も見えた。その辺りが寺の境内から続く山道であるとわかった。
斜面の道を上ると、途中に平地があり、薄紫色のアジサイをバックに写真を撮っている人たちがいた。さらに階段を上って山道に出た。山道には地蔵が距離を置いて並び、それぞれが札所になっている。これらは四国の88ヵ所巡拝コースに見立てられている。
富士山を展望できる場所に立ったが、天気のせいなのか、あるいは遮蔽物があるせいなのか、眺めることはできなかった。道は多摩丘陵に続くが、平地の方角に向かった。下方から雅楽の笛の音が聞こえて来た。
階段を下りると、アジサイの道になる。道の片側にアジサイが咲き、それらのアジサイは間を置かず続いている。写真を撮る人たちが多い場所である。
歩き始めて1時間半が過ぎていた。境内を出て門前のすし店に入りビールを飲み、すしを食べながら懇親した。蒸し暑い日で、汗をかいたせいか、ビールが旨かった。話題は多岐にわたったが、多摩稲門会のサークルは会社人生を終えた人たちの居場所として最適であるという点で意見が一致した。
(川面記)
紫陽花の色とりどりに花きそう(長張)
7月のコートのご案内です。奮って ご参加ください!
2013-06-09
7月のコートが確定しました。
●場所:一本杉公園内テニスコート
▼開催日時等:
・7月02日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
・7月09日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
・7月16日(火) 8:00~10:00 Aコート・Cコート・Dコート
・7月23日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
・7月30日(火) 8:00~10:00 Cコート・Dコート
なお、7月16日は、3面を使って、当テニス会員である佐藤喜昭さんの所属クラブ(STC)との対抗戦を予定しています。
是非、コートへお出でください。
お問い合せは:中里 保司/Mail
to ⇒ nkzto@live.jp
第34回定例総会、第49回文化フォーラム・懇親会のご案内
2013-06-09
新緑の候、会員、校友の皆様にはご清祥にお過ごしのこととお慶び申し上げます。
さて、表記の会を開催しますのでお繰り合わせのうえご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。
記
日 時:平成25年6月22日(土)午後1時〜1時45分 定例総会
2時〜3時40分 文化フォーラム
4時〜6時 懇親会
会 場:京王クラブ 多摩市関戸2-43-12
聖蹟桜ヶ丘駅東口より徒歩5分(042-337-3478)
総 会:平成24年度活動報告、決算報告、平成25年度活動計画及び予算案審議が議題
第49回文化フォーラム 『松瀬 学氏 講演会』 (入場無料)
演 題: 『ワセダスポーツとオリンピック』
講師略歴: 修猷館高から早稲田大学社会科学部へ。大学時代ラブビー部で活躍、81・
82年早明戦、早慶戦、全国大学選手権に出場した。83年卒業後共同通信社入社し、
運動部記者として国内外で取材活動を行い健筆を揮った。
現在はノンフィクションライターとして幅広く活躍している。
早稲田学報編集委員等を歴任し、日本文藝家協会会員、東京学芸大学非常勤講師。
代表著書に「早稲田ラグビー再生プロジェクト」改題)、他著書多数。
懇親会 (会費 懇親飲食代4千円)
講演会後に同所にて懇親会を行います。ご出席下さいますようお願い申し上げます。
<お問い合わせ及びお申込先>
幹事長 長張紘一 〒206-0001 多摩市和田1719-12
TEL:042-337-1792 メール:nagahari@ttv.ne.jp
尚、年会費(3,000円)と懇親会ご参加の方は会費(4,000円)と合わせてお振込み下さい。
以上
「2013年ブナの植林のご案内です。」
2013-06-02
野沢温泉村の上ノ平高原にある日本有数のブナ原生林が、冬の厳冬期から目覚めいよいよ活動を開始します。樹齢数百年のブナ林の静寂とその存在感を確かめてみませんか。
今冬は積雪量が多く春の息吹も遅めでしたが、例年通りブナ林も含め色々な新緑を眺めながらの山歩きが楽しめそうです。
 東村山市立萩山小学校の生徒と一緒にブナの植林をしてみませんか。
東村山市立萩山小学校の生徒と一緒にブナの植林をしてみませんか。
ブナの植林は、野沢温泉村とNPO法人体験学習支援センターが、ブナ復活の100年計画として取り組むプロジェクトですが、かつての牧場跡地をブナ原生林の自然に返す運動を始めて今年で10年目になりました。植林の汗の結晶が後世に残ります。
 野沢温泉村は山菜の宝庫です。ちょうどこの時期、山に入ると根曲がり竹がたくさん取れます。
野沢温泉村は山菜の宝庫です。ちょうどこの時期、山に入ると根曲がり竹がたくさん取れます。
ツアーの昼食に、この根曲がり竹をはじめたくさんの山菜料理をキャンプ地で楽しみましょう。
皆様のご参加をお待ち申し上げます。
<実施日> 平成25年7月3日(水)~7月4日(木)
<交通手段> 車に分乗の予定
<宿泊先> 旅館「さかや」 〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村9329
<費 用> 参加費18,000円 (往復旅費、1泊2食お酒込)
お申し込み、お問合せは : 依田敬一 yodak1jp@yahoo.cojp
Aコース 不老山(839m)・高指山(911m)
2013-06-02
大きな山容の権現山や扇山の傍らに位置する縁起の良い名前の不老山は、丹沢の同名の山と区別するため甲州の東にあることで甲東不老山と呼びます。登山口は、中央高速道の談合坂SAの直ぐ近くにあります。標高も比較的低く、天気が良ければ富士方面の山並みの景色が楽しめます。ご検討の上、体調にあわせてご参加をお待ちします。
1.日時 Aコース 6月15日(土)
2.予定コース
Aコース 不老山・高指山 (歩行3時間30分)
○集合 (7:45)京王線聖蹟桜ヶ丘下りホーム(7:55)発特急高尾山口行き乗車(8:13)高尾駅着(8:20)発JR高尾発普通列車乗車(8:37)上野原駅着 不老下方面行きバス(富士急)発(8:42)→不老下バス停着(9:07)
徒歩開始 不老下バス停→(20m)登山口→(30m)金比羅大権現→(50m)不老山→(30m)高指山(昼食)→(60m)和見峠→(20m)甲東小学校前バス停 (24m)340円→上野原駅
甲東小学校前発バス 15:27 16:26 17:32
○持ち物・装備
・昼食、水、間食等 服装(長袖シャツ・ウインドヤッケ・ジャンパー等)、帽子、手袋(軍手)、タオル等、雨具(折り畳み傘)、ストック
○雨天の場合は中止します。迷うような場合は、電話でお尋ね下さい。
Bコースは、定例総会と関連の委員会など、行事が重なりますのでお休みです。
参加ご希望の方は、金子(tel/fax 042-374-1525、
e-mail kjkaneko@suou.waseda.jp)にまでにお知らせください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
稲門会の予定 6月22日(土)定期総会・文化フォーラム・懇親会
古刹とビール工場を見学
2013-05-26
多摩稲門会のサークル「山歩きの会」Bコースの5月例会は府中市のサントリー武蔵野ビール工場を見学した。風薫る23日午後1時、京王線分倍河原駅前に世話役の長張幹事長をはじめ9人が集まった。分倍河原の古戦場跡である駅前には鎌倉攻めの英雄、新田義貞の銅像が建っており、歴史が感じられる街である。
山歩きの会はAコースが山登り、Bコースが低山歩きか街歩きとなっている。サントリーの工場まではシャトルバスで5分余りだが、バスは利用しないで歩いた。
 工場見学の午後3時までは時間があったので駅に近い高安寺を訪れた。ここは田原藤太秀郷の館跡に建てられた見性寺であったが、足利尊氏が安国利正の祈願所として再建、高安護国禅寺となった。当時は鎌倉の建長寺の末寺で臨済宗であったが、その後は北条氏の庇護を受けたり兵火に遭ったりして変遷を重ね、現在は曹洞宗の寺になっている。
工場見学の午後3時までは時間があったので駅に近い高安寺を訪れた。ここは田原藤太秀郷の館跡に建てられた見性寺であったが、足利尊氏が安国利正の祈願所として再建、高安護国禅寺となった。当時は鎌倉の建長寺の末寺で臨済宗であったが、その後は北条氏の庇護を受けたり兵火に遭ったりして変遷を重ね、現在は曹洞宗の寺になっている。
境内には弁慶硯の井戸がある。これは源義経と弁慶が寺に立ち寄り、写経するために硯で墨を摺ったが、その水を汲んだ井戸と伝えられている。
 龍山門という額がかかる山門には四天王ではなく「奪衣婆」の像があり、不気味な目を見開いている。寺の人の説明によると、死者は三途の川を渡る前に奪衣婆に白い衣を奪われる。婆は衣の重さで生前の罪業を判断し、閻魔大王らに報告する。その報告により死者は極楽に行くか地獄に堕ちるか運命が決まるという。奪衣婆というものが見られるのは高安寺だけであろうと寺の人は言っていた。
龍山門という額がかかる山門には四天王ではなく「奪衣婆」の像があり、不気味な目を見開いている。寺の人の説明によると、死者は三途の川を渡る前に奪衣婆に白い衣を奪われる。婆は衣の重さで生前の罪業を判断し、閻魔大王らに報告する。その報告により死者は極楽に行くか地獄に堕ちるか運命が決まるという。奪衣婆というものが見られるのは高安寺だけであろうと寺の人は言っていた。
下河原緑道に出る。ここは南にある「郷土の森公園」まで真っ直ぐに道が伸びている。公園の先は多摩川が流れている。昔は多摩川の砂利を運ぶ鉄道が走っていた。その後が下河原緑道なのである。
 緑道歩きを楽しんだ後、郷土の森公園まで行くとサントリーのビール工場の見学時間に間に合わなくなると判断し、工場に向かった。工場の手前に「御茶屋街道」の石碑が立っている。府中市本町にあった府中御殿でお茶をたてるため、多摩川から水を運んだ道という。府中御殿は正保3(1646)年に大火で焼失したと記されている。
緑道歩きを楽しんだ後、郷土の森公園まで行くとサントリーのビール工場の見学時間に間に合わなくなると判断し、工場に向かった。工場の手前に「御茶屋街道」の石碑が立っている。府中市本町にあった府中御殿でお茶をたてるため、多摩川から水を運んだ道という。府中御殿は正保3(1646)年に大火で焼失したと記されている。
ビール工場では45分ほど案内の女性の説明を聞きながら製麦、仕込み、発酵、貯酒、ろ過、缶詰めといった工程を見た。
 その後の試飲会が楽しみであった。時間は15分と限られたが、1杯目はカップ一杯の「ザ・プレミアム・モルツ」を飲んだ。2杯目はまだ酵母が生きているもので、工場でしか飲むことができない非売品である。3杯までサービスしてくれるが、参加者9人の多くは時間的に2杯までしか飲めなかった。
その後の試飲会が楽しみであった。時間は15分と限られたが、1杯目はカップ一杯の「ザ・プレミアム・モルツ」を飲んだ。2杯目はまだ酵母が生きているもので、工場でしか飲むことができない非売品である。3杯までサービスしてくれるが、参加者9人の多くは時間的に2杯までしか飲めなかった。