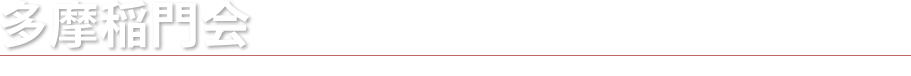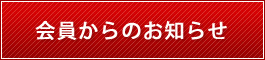Author Archive
「9月度ボウリングの会練習会」実施
コロナが下火になったと思ったら今度は台風の直撃を受けた9月の第4土曜日、9月24日にボウリングの会練習会が永山コパボウルで行われた。外の陽気は「秋分の日」を過ぎて、雨のせいかめっきり涼しくなっていた。
ボウリング場内は熱気ムンムンの満員御礼。レーンを予約していなかったら確実に30分~1時間待ちになっていた。3連休の間の日で外は雨ということもあって若い人たちが多かった。ボウリングは手軽なレジャーとして若者たちの間で定着しているようだ。プレーヤーはマスク着用をし、大声を出さないように気をつけていた。コロナも一時の爆発的な感染より下火になったが、まだまだ油断はできない。
今回参加者は4名。午後2時40分集合、3時開始で約2時間プレーを行った。
参加者は、尾ノ井光昭さん、藤原雅博さん、野宇進さん、そして稲垣の4名である。
今回は女性陣の欠席が寂しいところではあった。

1レーンに4名が入り、1人3ゲームずつ行った。藤原さんは最初から快調に飛ばし、200点越えを見せた。ストライクはもちろんスペアーも安定してクリアしていた。尾ノ井さんはストレートのボウルを投げ、コントロールも抜群だった。ストライクも随所で取っていた。野宇さんもいくつかストライクを取り、素直なボウルを投げていた。稲垣は下半身の不安定さが投げるボウルに投映し、1本2本の残りピンのスペアートライを外しまくり、不本意な結果となった。ボウリングのボウルの重さが重たく感じられ、ボウルスピードが遅くなっていることがわかった。現在14ポンドのボウルを使っているが(マイボウル)、13ポンドのボウルにしようと考えている。
ゲームは午後5時に終わり、永山駅近くにあるすし屋『銀蔵』で懇親会を行った。 個室で4人ゆったりと座り、“季節のコース料理”を堪能した。生ビールで乾杯の後、日本酒、焼酎、を酌み交わし、世間話や身の上話、近況報告などで盛り上がった。 多摩稲門会『ボウリングの会』は2か月に1回練習会を開くことになっていて、次は11月26日(土)に実施予定です。
(世話人 稲垣友三)
「求む早稲田バカ」
「早稲田学報10月号」では、このような見出しで早稲田愛に溢れたOB・OG達を紹介しています。
さて、正月三ケ日の楽しみはいろいろありますが、我々OB・OGの一番の楽しみは何といっても箱根駅伝です。現地での応援が叶わずともテレビ観戦は必見です。
しかしながら、今年の母校チームは立川で行われる予選会からの挑戦になりました。シード復活をかけた激しいレースが予想されます。多摩稲門会としても有志を募って現地での応援をしたく思います。いちずな早稲田愛を思い切り選手たちに注ぎませんか?
皆さんのご参加を立川でお待ちします。
詳しくは続報にてご案内します。
9月25日 おっかけ隊長 竹内二郎
多摩稲門会長 尾ノ井光昭
第105回俳句同好会
多摩稲門会の「俳句同好会」の9月例会は16日午後開かれ、メールにより投句、選句した人を含め7人が参加した。サークルとして月に一度の開催だが、活動を開始してから休むことなく続き9月が第105回目となった。 投句、選句とも5句ずつだが、投句された35句のうち半数以上の20句が選に入った。当日の最高点句は〈宿坊の朝の緊りや新豆腐〉で〈緊り〉には「しまり」とルビが振ってある。大きな寺に泊まった朝の引き緊まった雰囲気が伝わる。寺は朝から勤行をし、僧の読経が響いていたのだろう。朝食は肉や魚ではなく豆腐、新しく収穫した大豆が原料だ。清涼感もある秋の句だ。 1人が特選句としたものの意味がよくわからないと評されたのが〈啄木よ我は野に寝て天の川〉。これは石川啄木の〈不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心〉という短歌を踏まえての句だ。野に寝て天の川を見たのは多摩稲門会の「こそばの会」というサークルの活動で新潟県の妙高高原に出かけた際のことだった。
・
選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名、特選は◎で表記。
・
宿坊の朝の緊りや新豆腐―――川俣あけみ(川面◎、又木◎、辻野、宮地)
山荘の魚籠に挿さるる紅葉の枝―――川俣あけみ(長張◎、松井◎、川面)
芒原匿はれたるおもひ草―――辻野多都子(川俣◎、長張、宮地)
ゆきあひの雲流れきて篠薄―――辻野多都子(宮地◎、又木)
啄木よ我は野に寝て天の川―――川面忠男(辻野◎)
酔芙蓉町内の人皆老いて―――川俣あけみ(川面、又木、松井)
翡翠色のどんぐり拾ふ下山道―――宮地麗子(川俣、長張)
初秋刀魚戦火の民に詫びながら―――辻野多都子(川俣、又木)
白芙蓉素てふ熟語の二つ三つ―――又木淳一(辻野、宮地)
山頂は絹の雨なり葛の花―――宮地麗子(川俣、松井)
雨音をリズムに真夜の秋思かな―――川面忠男(川俣、松井)
はつとする色に露草抜け出でて―――松井秋尚(長張)
八月を少し残して新学期―――又木淳一(松井)
白と黄と縺れ高きへ秋の蝶―――松井秋尚(又木)
つぎつぎと生ゆる愛妹花芙蓉―――又木淳一(辻野)
濁音の声引き摺つてちちろ虫―――松井秋尚(辻野)
温暖化進む我が星雁渡し―――川俣あけみ(宮地)
雨多き庭にひときわ女郎花―――辻野多都子(長張)
萩のもと盗人萩も咲き誇る―――長張紘一(川面)
同胞の妹は彼方に秋彼岸―――又木淳一(川面)
(文責・川面)
第104回俳句同好会
俳句の日という8月19日、多摩稲門会のサークル「俳句同好会」の第104回目の句会が関戸公民館の学習室で開かれた。同日はお盆明けとあって御霊を送る俳句が投句されたのが例月と違った特徴だ。〈送り火の尽きて残れる地のほてり〉、〈五人乗する脚を太めに茄子の馬〉、どちらも特選句となった。
また8月15日の直後ということもあり、終戦日を季語にした〈吾が喜寿は令和四年の終戦日〉も当日の高得点句となった。戦後77年が過ぎた今年に77歳の誕生日を迎えた個人の感慨だ。メンバ-には同年齢の人もいて共感したようだ。終戦の年に生まれ、先の戦争を知らず、戦後の復興、高度成長時代に生きた世代だが、ウクライナ戦争が続き、中国が示唆する台湾制圧には日本も巻き込まれ怖れがある今日だけに実感が伝わる。終戦日という季語が効き、個人の感慨を超えて広がりのある句になっている。〈暑気払ひ戦の星を憂ひつつ〉も不戦を祈る句だ。
・
選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名、特選は◎で表記。
・
送り火の尽きて残れる地のほてり―――川俣あけみ(又木◎、松井、宮地、辻野)
吾が喜寿は令和四年の終戦日―――又木淳一(川面◎、川俣、松井)
五人乗する脚を太めに茄子の馬―――川俣あけみ(宮地◎)
四十雀独りよがりの鳥語かな―――長張紘一(松井◎)
仰向けのひとつに降れる蝉時雨―――川面忠男(長張◎)
喪服脱ぎ檸檬一片口中に―――川俣あけみ(川面、辻野、宮地)
なぜ此にただ夕蝉の一人部屋―――又木淳一(川面、辻野)
風来たる奥の社の片かげり―――宮地麗子(川俣、長張)
茄子焼いて夫在りし昼思ひける―――辻野多都子(松井、宮地)
朝日差す無人スタンド秋茄子―――川俣あけみ(長張、又木)
刈られたる吐息ぞ強き草いきれ―――宮地麗子(川面、長張)
救急車去りて沸き立つ蝉しぐれ―――辻野多都子(川面、松井)
秋立つや雲みな鳥のかたちして―――宮地麗子(辻野、又木)
送り梅雨ぬるりと触るる柱かな―――辻野多都子(宮地)
暑気払ひ戦の星を憂ひつつ―――川面忠男(川俣)
里山をやには響もす草刈り機―――長張紘一(辻野)
片蔭の噂話の尾鰭かな ―――川俣あけみ(又木)
雑音に聞こえてきたる蟬時雨―――松井秋尚(長張)
秋暑し鍵まだ開かぬ会議室―――松井秋尚(又木)
秋立つや家居の庭に風一陣―――又木淳一(川俣)
煌めいて群がる蜻蛉田水満つ―――長張紘一(川俣)
(文責・川面)
稲城稲門会 秋の山歩きの会(令和4年)
厳しい暑さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか? さて、コロナ禍いまだ止まずとはいえ、秋の山歩きの会として10月1日(土)、武蔵五日市駅からバスで行く三頭山(みとうさん。1531メートル)登山を企画してみました。
「都民の森」(標高1000メートル)から出発する登山道も軽快な初心者向け山歩きです。歩行時間は軽昼食時間を入れて4時間ほど、標高差は約500メートルです。
注: 悪天候での中止の場合は当日朝に決定、連絡いたします。
1.日 時 : 10月1日(土曜) 8時00分
2.集 合 : JR立川駅 1、2番線のホーム前方(奥多摩方向)
<青梅線(ホリデー快速)8時12分発乗車、武蔵五日市駅8時38分着予定>
3.コース アクセス:
JR武蔵五日市駅(西東京バス)9:00発 → 都民の森10:20着 →三頭山頂12:20着(軽昼食)12:50出発 → 都民の森 14:20着 → 都民の森(西東京バス)14:35発 → 数馬の湯(15:00~)16:08発 →JR武蔵五日市駅17:21発 → 立川駅で解散(18時00分ころ)
<括弧内の時間は目安です>
*実質3時間30分の歩き。
コース紹介サイト:http://jac.or.jp/oyako/f15/d206020.html
4.入浴・懇親会 「数馬の湯」 http://kazumanoyu.net/
東京都西多摩郡檜原村2430 TEL: TEL.042-598-6789
5.持参品 軽昼食、飲料水、雨具、防寒具、タオル、着替え、帽子、マスク他
参加希望の方は、9月25日(日)までに下記メールでご連絡ください。
Mail:kojinet.taka@zf7.so-net.ne.jp (高橋)
幹事: 高橋 090‐9131‐7337(携帯)
What’s JAZZへの招待 vol.61
What’s JAZZライブを楽しみにされている方々 各位
創立88周年を迎えた名実ともに日本一のビッグバンド登場。グレンミラー、ベニーグッドマン、カウントべーシー、デユークエリントン、ペレスプラード、ザビアクガードなどのキラ星のごとくヒットパレードをお楽しみください。
2022年9月9日(金)
・昼の部 13:30開場 14:00開演
・夜の部 17:00開場 17:30開演
・出 演 スインギー奥田 & ザ ブルースカイオーケストラ ・曲 目 昼の部 、夜の部共 スイング、ラテンの名曲
・場 所 聖蹟桜ヶ丘駅前 関戸公民館8F ヴィータホール
・入場料 昼の部、夜の部それぞれ2,500円、完全入れ替え制。
前売券は、8月8日(月)午前10時から9月8日(木)迄 ヴィータ7F多摩ボランティア市民活動支援センターで発売、※なるべくお釣りのないようにお願い致します。 当日券(残余ある時)は当日13時から受付で発売。
・定 員 230名(感染状況により定員変更の可能性があります。)
※当日はマスク着用、チケット半券に住所.氏名.電話番号を記入して下さい。
※次回vol.62は、12月1日を予定しております。入場料は1,500円です。
・主 催 What’s JAZZ実行委員会・関戸公民館
実行委員長 山中康廣 Tel 042-371-4084
会費納入のお願い
2022年8月14日
会員各位
酷暑の中、またコロナ感染症第7波が猛威を振るう中、皆様にはご健勝でお過ごしの事と拝察致します。
日頃は、多摩稲門会の運営にご支援・ご協力を頂き厚く御礼を申し上げます。 お陰様で今年度の定例総会は、6月25日に3年振りに対面にて開催する事が出来ました。例年であれば、文化フォーラム・懇親会も併せて皆様と大いに懇親を図る機会ですが、安全対策上中止せざるを得ませんでした。誠に申し訳なく忸怩たる思いです。
さて、
今年度年会費の入金状況(事務局調べ)をご報告します。8月11日現在納付者82名、金額240,000円(予算では118名,340,000円)予算対比70.58%となっております。
多摩稲門会の運営には、皆様からの年会費(3,000円)のご支援が不可欠です。今年度も未納の会員に於かれましては、是非ともご協力を宜しくお願い申し上げます。
コロナ感染が落ち着き次第、文化フォーラム・新年賀詞交換会等開催を検討致したく存じます。
皆様、暑さに負けずご体調には十分気を付けてお過ごし下さるよう祈念しております。
※ 振込用紙は5月にお手元にお送りした「第43回総会議案書」と共に同封しております。ご不明の場合は事務局までご連絡下さい。
幹事(会計補佐)白井昭男
Eメール:saty1516@din.or.jp ℡ :090-5554-1821
多摩稲門会
会長 尾ノ井 光昭
『早稲田学報』ご協力のお願い
校友会支部ならびに登録稲門会ご担当者様
>
>平素より早稲田大学ならびに早稲田大学校友会へご支援いただき、誠に有り難く厚く 御礼申し上げます。
>早稲田大学校友会事務局・早稲田学報編集室の安國と申します。
>
>『早稲田学報』2022年10月号では、早稲田が好きで好きでたまらない方々を紹介する 「早稲田バカ(仮)」という特集をおこないます。 >「早稲田バカ」を「早稲田が好きで好きでたまらない人のことを敬意と愛情を込めて 呼ぶ言葉」と定義し、表紙にも明記いたします。 > >その特集内で「早稲田愛の修羅場」という投稿企画を行うのですが、下記内容につき まして投稿、周知や拡散にご協力いただけるようであればたいへん助かります。
>
>【「早稲田愛の修羅場」投稿および拡散のお願い】 > >『早稲田学報』10月号では、早稲田が好きで好きでたまらない方々を紹介する「早稲 田バカ(仮)」という特集をおこないます。その特集内、「早稲田愛の修羅場」企画で は、在学生や卒業生の皆さまから母校愛あふれるエピソードを募集し、掲載させていた だきます。「スマホの着メロが紺碧の空」「3代にわたって早稲田」など身近なものか ら、300字程度までの深く壮大なものまで、涙あり、笑いあり、感動ありのさまざまな 愛の形をご投稿いただきますと幸いです。投稿募集の締め切りは7/11(月)を予定して います。
>
>▼校友用『早稲田学報』10月号「早稲田バカ(仮)」特集 投稿フォーム
> https://my.waseda.jp/application/noauth/application-detail-noauth?param=RKKLmcq5PMVWVGtsvzyQYA
> >【Facebook】 > https://www.facebook.com/wasedaalumni/posts/pfbid02LeaQKYroTo
HBEZjyChPizoxd2qTExE3Ee1fWrCbc83oPZFLi5mjEZQ6xbL11m78Zl > >【twitter】校友向け >https://twitter.com/waseda_alumni/status/1536184915402063873
>
>以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
令和4年度「第43回定例総会」の報告
多摩稲門会令和4年度定例総会は6月25日(土)午後1時から多摩市関戸の「京王クラブ」で行われた。梅雨最中であるが猛暑のなか23名の出席者であった。総会は2年に亘り新型コロナウィルス感染拡大のため、書面による総会となったが、3年振りの対面総会を開催することとなった。しかし、従来の校友会、近隣稲門会等の来賓招待はなく、また、総会後の文化フォーラムや懇親会のない内輪の総会となった。

定例総会
午後1時、多摩稲門会第43回定例総会が長張紘一副会長の開会の辞で始まった。尾ノ井光昭会長の挨拶のあと、吉川啓次郎監査が議長に選出され議事が進行された。 幹事長代行として尾ノ井会長が令和4年度多摩稲門会活動報告、同決算報告が行われた。コロナ感染拡大第5波、第6波の影響を受けて、文化フォーラム・懇親会等は中止、総会も書面にて実施した。会報「杜の響き」は、5月、12月計画通り発行することができた。サークル活動に関しては休止の多いなか、一部世話人の判断により定期的にあるいは時宜に応じて開催された。サークル活動補助費の支給は3年振りに復活することができた。会員数に関しては、期首146名から131名と減少した。決算に関しては期首759千円から期末906千円となった。いずれも異議なく承認された。
引き続き、令和4年度多摩稲門会活動方針案、予算案、新役員を発表した。コロナ感染症の収束を期待し、ほぼ例年通りの活動計画案は、異議なく承認された。 野宇進会計幹事の音頭により、参加者全員でマスクをかけながら、校歌「都の西北」3番まで斉唱し、又木淳一副会長の閉会の挨拶で閉会した。
・
出席者(敬称略) :浅井隆夫 石川良一 稲垣友三 尾ノ井光昭 加来健一郎 川面忠男 菊沢光江 白井昭男 堤 香苗 戸張傳二郎 長張紘一 浪久圭司 西村 弘 野宇 進 野田豊實 平松和己 福田 宏 藤原雅博 前田光治 益田幸兒 又木淳一 湯浅芳衛 吉川啓次郎 (以上23名)
(長張紘一 記)
第102回俳句同好会
多摩稲門会のサークル「俳句同好会」の6月定例会が17日午後、多摩市の関戸公民館・和室で開かれた。今回が102回目。メンバー8人のうち7人が出席、欠席した1人も事前に投句と選句を世話人に伝えていた。その結果、投句数はいつもの通り40句となった。出席者は選句とともに21句を選び句評を述べ合った。連衆となって句座を続けているわけだ。
兼ねて吟行をしようと申し合わせていたが、ほぼ一週間前に7人が多摩市の「からきだの道」を歩いた。散策が主目的だったが、吟行も兼ねることになり、その後の句会こそ開かれなかったものの当日の嘱目句が第102回目の俳句同好会に投句されたので初の吟行句会ということになったと言える。高得点句となった〈攻め寄する藪蚊を払ふ砦跡〉をはじめ〈山路めく上り下りの七変化〉、〈湧き水の音流れくる木下闇〉、〈夏落葉厚く踏み行く砦山〉などは「からきだの道」を散策して詠んだ吟行句だ。
・
選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名(特選は◎で表記)。
・
黒雲の湧きて下山やかたつむり―――宮地麗子(川面◎、川俣◎、辻野、長張))
攻め寄する藪蚊を払ふ砦跡―――川俣あけみ(柴田◎、長張◎、川面、松井)
尾を上げて苔食む列や夏の鴨―――長張紘一(辻野◎、川面)
生かされて金魚に餌やる朝まだき―――辻野多都子(宮地◎、川俣)
梅雨寒や昼カラオケの追悼歌―――川面忠男(又木◎)
山路めく上り下りの七変化―――川面忠男(松井◎)
泰山木開き彼の世の声集む―――川俣あけみ(川面、辻野、宮地)
湧き水の音流れくる木下闇―――宮地麗子(川俣、又木、松井)
委蛇(いい)として丘陵蒼き梅雨入かな―――又木淳一(川面、松井、宮地)
何処までも纏はる藪蚊払ひつつ―――松井秋尚(柴田、長張、又木)
草も木も茂りて昏き径となる―――松井秋尚(長張、又木)
亡き友を友と語らひ冷し酒―――川面忠男(柴田、松井)
夏の蝶まひまひ井戸の底ひより―――川俣あけみ(辻野、宮地)
北国の廃線跡や虎杖伸ぶ―――辻野多都子(宮地)
灰色の雲間に滲む梅雨の月―――柴田香代子(川俣)
摘みたての青紫蘇添へて朝餉かな―――宮地麗子(辻野)
炳として騰がる物価や六月来―――又木淳一(柴田)
夏炉辺の軽き縁や雨を来て―――川俣あけみ(長張)
夏落葉厚く踏み行く砦山―――松井秋尚(又木)
傘となり驟雨を和す大欅―――長張紘一(柴田)
梅雨寒や降りる人なき山の駅―――柴田香代子(川俣)
(文責・川面)
« Older Entries Newer Entries »