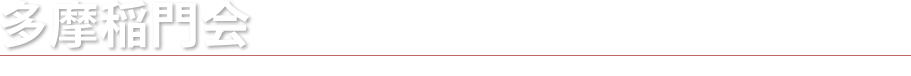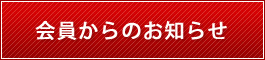Author Archive
吟行の「からきだの道」
多摩稲門会のサークル「俳句同好会」の7人が6月9日午後、「からきだの道」を歩いた。「からきだの道」は多摩市唐木田の丘陵地が散策路として開発されたもの。俳句同好会としては活動を開始して以来、初の吟行ともなった。

同日午後2時前に唐木田駅前に集合し、循環バスに乗って土橋公園で下車、「からきだの道」の西端入り口へ。「からきだ百本シダレ」という枝垂れ桜の名所から階段を上り尾根径に出た。標高が160㍍で最高地点という標識を見てから砦山という四阿のある場所に立った。
同行の又木さんが参加者に事前に配った「からきだの散策ガイド」という資料によると、砦山は「唯一富士山が見える地点」だ。南側の展望も開け、市街地の向こうに「多摩よこやまの道」、さらには奥州古道、武相観音巡礼古道もイメージできる。

その先は上り下りを繰り返す階段の道になる。足が重いが、季節の花のアジサイに目を癒しながら進む。少し休むと藪蚊が襲う。再び歩き出しても蚊がまとわりつく。
山道を歩いている気分になるが、左の石の塀の向こうはゴルフ場の府中カントリークラブだ。ゴルフの球を打つ音が聞こえてくる。右側には道路が見え、その向こうに住宅地が広がっている。
「おしゃもじの森」という案内板のある箇所に立った。読んでみると要するに昔は祠があり、しゃもじを供えて祈ると病気が治ったことから「おしゃもじ様」と呼ばれることになったとある。その先の「寺ノ入の湧水」という小さな池では自然の湧水の音がしたが、一部は乾いている。やがて「からきだの道入り口広場」に出た。反対側の入り口からアクセスしたので入り口広場が出口になる。
最寄りのバス停から唐木田駅へ戻り、6人が小田急多摩線で多摩センターへ。午後4時頃だが、開いている店を探し、生ビールで乾杯、懇親した。
吟行は出発した時点からの景を詠む。嘱目句とも言う。いくつも句ができた人もいれば、そうでない人も。どんな句が選ばれるか。それはほぼ1週間後の17日に開かれる俳句同好会でわかる。
(文責・川面)
多摩丘陵の古街道展を見学
多摩稲門会のサークル「歴史に遊ぶ会」は6月5日、多摩センターのパルテノン多摩・市民ギャラリーで開催中だった「多摩丘陵の12古街道展」を見学した。参加者は8人。同会の活動はコロナ化などのため活動を休止していたが、3年ぶりの再開となった。
「多摩丘陵の12古街道展」は歴史古街道団(本部多摩市、宮田太郎代表)が開催した。今年2月末にも町田市鶴川の和光大学の施設で開催され、12古街道に関する説明を図示した資料が用意されたが、パルテノン多摩では資料がカラー化されていた。また各資料が「古街道シアター」としてプロジェクタースクリーンに映され、宮田さん自身が午後2時過ぎから3時近くまで説明した。
鎌倉街道上ノ道は府中ではなく分倍河原の近くを通っていたとか奥州古道は誰もが歩けたが、古代東海道は正式には朝廷の許可がないと利用できなかった等々といったことだ。
古街道展の見学に参加したのは荒井さん、湯浅さん、尾ノ井さん、川俣さん、白井さん、辻野さん、宮地さん、川面の8人。見学後、7人が多摩センター駅からバスで愛宕まで行き、鎌倉街道の裏街道とされる恋路原通りを歩いた。遊郭があり恋路という名の遊女がいたという伝説がある。さらに稲荷塚古墳、恋路稲荷を見た後、東寺方の総合体育館の近くまで歩き、今に残る鎌倉裏街道の一部を確かめた。
再び総合体育館前からバスに乗り一の宮ストア前で下車。小野神社を見ながら宮下通りの「一ノ宮渡し」のモニュメントを見た。多摩丘陵の12古街道の一つ、古代甲州道の資料の内容を踏まえ道のなぞり歩きを試みたのだ。
古代甲州道について資料には次のように記されている。「相模川左岸の川尻遺跡から多摩丘陵に向かい、内裏峠を越え、縄文の集落が多数ある大栗川沿いに進み、最終的には多摩川を渡って府中へ繋がっていたと思われます」。モニュメントには一ノ宮渡しの想像図が描かれている。
多摩市には金毘羅宮があるが、それは川を渡る舟の無事を祈るためでもあると同行の荒井さんから道々教えていただいた。
(世話人 川面忠男)
「5月度ボウリングの会練習会」実施
初夏のような陽気の5月最終土曜日、ボウリング好きが集まった。 多摩稲門会『ボウリングの会』5月度練習会が26日(土)、永山コパボウルで行われた。
ボウリング会場はコロナ禍前の一時の人気を取り戻したかのようにほぼ満杯で予約を取っていなかった世話人は少し慌てたが、1レーンだけ空いていたので取ることができた。満杯だったらかなりの時間待機することになっただろうと思われる。その後の懇親会の会場予約時間のこともあり、取れて安堵した。今はそれだけコロナの収束感が出てきており、特に若い人たちは積極的に外に出て楽しみたいという気持ちが強くなっている感じが場内を見渡してもした。しかし、ボウリング場はマスクの着用を義務付けていて、プレーヤーはすべてマスク着用でのボウリングプレーとなった。

今回参加者は4名。午後2時30分集合、3時開始で約2時間プレーを行った。 参加者は、尾ノ井光昭さん、藤原雅博さん、菊池恵子さん、そして稲垣の4名である。
1レーンに4名が入り、1人3ゲームずつ行った。それぞれストライク、スペアー、スプリット、ガーターなど百花繚乱オンパレードで、ストライクやスペアーを取った時はプレーヤーを皆が拍手で讃えた。これがボウリングのいいところで、本人と参加者がともに喜びをわかちあい、湧き上がる全員の一体感が生ずるところである。スコアは藤原さんが3ゲームのアベレージが180あたりで、本人は200アップのゲームがなくて不満そうだったが、180近辺を常時出せるというところはさすがである。尾ノ井さんはハウスボールで一直線にヘッドピン脇のストライクポケットを狙う豪球派で、投げられたボウルが“ビューン”と音を出して飛んでいくように見えた。菊池さんは女性らしい静かなスローイングから正確な道筋をとったボウルのコースを描き、安定したボウリングだった。練習次第では200アップも望めそうな投球内容である。稲垣は体重が落ちたこともあり下半身が安定せず、従ってスコアも安定しなかった。これもこれからの2カ月ごとの練習で下半身を強化し、再び200アップを狙えるようになると自分では思っている。
ゲームは午後5時に終わり、近くの居酒屋『塚田牧場永山店』で懇親会を行った。
懇親会から野宇進さんも加わり、5人で鶏料理などをつまみに、ビール、日本酒、ハイボール、焼酎、を酌み交わし、世間話や身の上話、近況報告などで盛り上がり、ボウリングの成績はそっちのけで楽しい時間を過ごした。
多摩稲門会『ボウリングの会』は2か月に1回練習会を開くことになっていて、次の7月は30日(土)、に実施します。
(世話人 稲垣友三)
手の込んだ和食に舌鼓
84回目のグルメの会を5月24日、京王・小田急多摩センター駅近くの和食店「かごの屋」で半年ぶりに開いた。コロナ感染者数の減少傾向が続いていたものの、なお反転の兆しが出たりして不安定。募集人数を10人に絞って感染防止策をとり、開催に踏み切った。男性8人、女性2人が参加した。

まず浪久圭司さんが音頭をとり、生ビールで乾杯。竹の子煮や木の芽真薯(しんじょ=すり身料理)、穴子八幡巻き、ミルク豆腐、蒸し鶏など8点が盛られた前菜がまず運ばれた。手が込んでいるだけあって、3日以上前でないと予約は受けないそうだ。
参加が遅れたひとりが加わって、飲み放題のピッチは上がる一方。日本酒や焼酎、ワイン、サワーなどが次々と注文され、宴は盛り上がった。
料理はマグロ、ホタテ、甘エビの刺身のあと、煮物やサワラの焼き物、菜の花天、エビあられ揚げなど4点の揚げ物が続いた。
ロシアのウクライナ侵略戦争をめぐって活発な議論が巻き起こり、連日このテーマを取り上げて戦争の真相を探るBSフジの大型報道・討論番組「プライムニュース」が取り上げられた。この番組の反町理キャスターは多摩稲門会文化フォーラム講師を務めたことがあり、エネルギッシュな進行ぶりに話題が集まった。「戦争の犠牲者は常に庶民」という声があがると、日本の77年前の敗戦責任にまで議論は広がり、辻野多都子さんは「昭和天皇は退位すべきだった」と主張した。
牛シャブ鍋に舌鼓を打ったころには2時間の飲み放題の時間切れが近づいた。川面忠男さんが毎朝綴って多摩稲門会の多くの会員に配信しているメールに書いた「老化を考えたテレビ番組」を世話人の奨めで解説、長生きの可能性を探った。お店の配慮で宴会が30分延長され、家族問題や老後も楽しむサッカー、雑誌で紹介された活動など話題は多岐にわたった。
尾崎隆教さんは次回から辻野さんとともにグルメの会世話人を引き受けてくださると表明、この世話人を12年務めた浅井が協力に感謝した。
最後にシラスのおこわを味わってお開きとなった。
(世話人 浅井隆夫)
第101回俳句同好会
毎月第3金曜日に実施されている多摩稲門会のサークル「俳句同好会」は5月20日に開かれたが、第101回となった。発足10周年に向かってさらに活動を続ける。当日はメンバーの8人が出席、あらかじめ各人が投句しておいた5句について選句を行った。
特筆してよいのは、川俣あけみさんの4句が特選となり、残り1句も並選唯一の3点句となったことだ。俳句同好会は俳句を楽しむのが主目的のサークル活動で結社の枠を超えた集まりだ。先生も頼まないまま活動してきたが、合評の場で川俣さんが数句を添削するなど勉強の場にもなっている。
例えば〈背に馴染み飴色帯ぶる籐寝椅子〉は、原句が〈飴色の肌に馴染みし籐寝椅子〉だが、〈馴染みし〉という過去形を〈馴染める〉と今のことにし、さらに飴色は肌の色と受け取られるので籐寝椅子に直接かかるように直した。
・
以下は選句結果。カッコ内は選句者名(特選は◎で表記)。
・
躁も鬱も包みて真蒼若楓―――辻野多都子(川面◎、長張◎、柴田)
改葬の父母にまみゆる余花の寺―――川俣あけみ(辻野◎、川面、又木、宮地)
伽羅蕗や一人の刻の充てる色―――川俣あけみ(又木◎、辻野、松井、宮地)
ましぐらに走り来る子や新樹光―――川俣あけみ(宮地◎、辻野、又木)
墓地の奥の小さき古墳五月闇―――川面忠男(柴田◎、川俣、宮地)
天と海つなぐ棚田や初蛙―――川俣あけみ(松井◎、又木)
青空に羽音残して鳥巣立つ―――柴田香代子(川俣◎)
夏潮や海境(うなさか)を見る龍馬像―――川俣あけみ(辻野、又木、松井)
白衣の背追ひつ花愛で遍路道―――宮地麗子(川俣、柴田)
ぽたりぽた書斎の窓の青葉雨―――川面忠男(長張、松井)
顔(かんばせ)の欠くる地蔵や朧なる―――川面忠男(柴田、宮地)
眼間に桜蘂降る祝ひ膳―――辻野多都子(川面)
母の日や施設を母の家と言ふ―――柴田香代子(川俣)
何もかも綺麗さっぱり春驟雨―――又木淳一(長張)
里山の林冠の際緑立つ―――長張紘一(辻野)
てらてらと色盛り上がる樟若葉―――松井秋尚(長張)
花過ぎて戸外に返す鉢の数―――長張紘一(川俣)
背に馴染み飴色帯ぶる籐寝椅子―――柴田香代子(松井)
海からの夏めく風に髪湿る―――柴田香代子(川面)
何処へでも仲間に入る姫女苑―――松井秋尚(長張)
母の日といふ遠き日のありにけり―――松井秋尚(川面)
自転車の坂下る風若葉風―――宮地麗子(柴田)
(文責・川面)
第100回俳句同好会
多摩稲門会の俳句同好会は2014年1月にサークルとして発足して毎月第3金曜日に句会を開き、8年が過ぎて4月15日の例会が第100回目となった。事前にメンバーの8人がメールで投句、1人は欠席したものの選句を伝え、7人が午後2時から多摩市の関戸公民館を利用した会場に出席し、選句と合評を楽しんだ。
投句は句会が百回になったことを寿ぐ挨拶句の一方、ロシアのウクライナ侵攻を思って詠んだ句があり、4月の特徴となった。
句会後は会場を最寄りの寿司店に移し第100回記念祝賀会を催した。稲門会の尾ノ井光昭会長のお祝いの言葉で乾杯、これまでのこと、これからのことを話し合った。
・
当日の選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名(特選は◎で表記)。
・
踏青や押し来る力確かむる―――宮地麗子(柴田◎、長張◎)
裸婦像の踵の雫花の雨 ―――松井秋尚(川俣◎、辻野◎)
花は葉に痛み和らぐ時を待つ―――長張紘一(又木◎、川面、川俣、辻野、宮地)
重ね来て百花の春の句会かな―――又木淳一(宮地◎、川俣、柴田、松井)
ツルゲーネフ樹下に開けば春埃―――川俣あけみ(川面◎、辻野)
また共に見たき人をり初桜―――宮地麗子(松井◎)
芽柳の雨にほぐるる色淡き―――松井秀尚(川俣、長張、又木)
花冷えや衣重ねて旅支度―――辻野多都子(川面、柴田、宮地)
旅衣整へし間の落花かな―――宮地麗子(川俣、辻野、松井)
青空に咲いて夜風に舞ふ桜―――柴田香代子(川面、松井)
囀りや深く息吐き胸突きへ―――川俣あけみ(長張、宮地)
半生を古木の花に語りたる―――川面忠男(又木)
花盛り十八歳の通学路―――川面忠男(長張)
鳥雲に籠入る病癒え願う―――長張紘一(柴田)
目交ひの川面に触れむ花万朶―――又木淳一(辻野)
墨色の枝包み込む老桜 ―――長張紘一(松井)
春の闇戦火逃るる人ひとヒト―――柴田香代子(又木)
突然の脚の縺れや桜狩―――川面忠男(柴田)
ひこばえの桜開きて幼顔―――辻野多都子(長張)
外つ国の地獄見るべし鳥雲に―――川面忠男(宮地)
たんぽぽの踏まれさうなる所にも―――松井秋尚(又木)
百回の百花繚乱春句会 ―――又木淳一(川面)
(文責・川面)
「3月度ボウリングの会練習会」実施
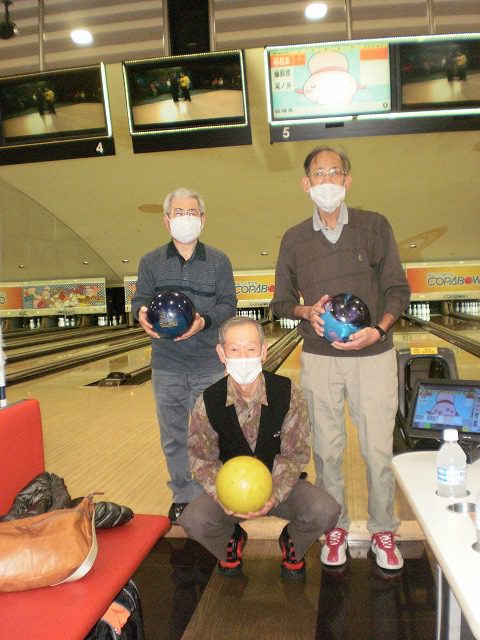
まだまだ新型コロナウィルスに気を許せない3月下旬、多摩稲門会『ボウリングの会』有志による練習会が行われた。
3月26日(土)、永山コパボウルで練習会を行った。
会場は若い人が多く、みなマスクをして騒ぐこともなく、淡々とボウルを投げていた。
今回参加者は3名。午後2時30分集合、3時開始で約2時間プレーした。 参加者は、尾ノ井光昭さん、藤原雅博さん、稲垣の3名である。
1レーンで3名が使用した。藤原さんは地元で3日に1回ボウリングの練習をしているが、尾ノ井さんと稲垣は久しぶりのボウリングで、なかなかボウルの行方が定まらず、安定した得点の獲得が難しかった。それでも尾ノ井さんは3ゲーム、藤原さんと稲垣は4ゲーム、苦労しながらもわきあいあいと久しぶりのボウリングを楽しんだ。
ゲームは午後5時に終わり、近くの居酒屋で懇親会を行った。約2時間、ビールジョッキ片手に楽しく懇談した。
多摩稲門会『ボウリングの会』は2カ月に1回練習会を開き、次の5月は28日(土)、に決まっている。原則、第4土曜だが会員の要望で前後の土曜日に変更になることもあります。年6回の練習会開催は堅持していこうと思っています。
(文責:世話人 稲垣友三)
第99回俳句同好会
多摩稲門会のサークル「俳句同好会」の3月例会が18日午後、多摩市の関戸公民館和室で開かれ、8人があらかじめ5句ずつ合わせて40句を投句したが、当日は4人が出席、残り4人はメールなどで世話人に選句を伝えた。高得点を得たのは、春の耕しという季節を詠んだ句。〈農具出番を待つ〉という句は田や畑に出たいが、体調が整わず思うようにならない作者の気持ちを農具に託した句だ。〈農具置く谷戸の田んぼ〉の句も耕しを待つ季節を詠んでいるが、こちらは季節感だけでいま一つ。〈休耕田に名草の芽〉という句だが、これは後継者不足などのため耕す人がいなくなった田にも草の芽が育つという自然の力を詠んでいる。〈草餅を食むや画面に戦の火〉は、戦火に苦しむウクライナの人々を思いながら平和な日本の日常生活を詠んだ。時事俳句ではあるが、共感を呼んだ。
・
選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名、◎は特選を表記。
・
あたたかやバス停で読む一頁――― 宮地麗子(又木◎、松井◎)
春暁や手慣れし農具出番待つ ―――長張紘一(川面◎、川俣、辻野)
温みたる水に差し足鷺一羽――― 長張紘一(柴田◎、辻野、又木)
頬杖の虚ろ心や花ミモザ ―――川俣あけみ(辻野◎、宮地)
青み帯ぶ日を集めたる福寿草――― 松井秀尚(長張◎、又木)
梅が香を丹田に置く一日かな――― 又木淳一(宮地◎)
色褪せし休耕田に名草の芽――― 長張紘一(川俣◎)
完解を告げられし朝初音聞く――― 川俣あけみ(川面、柴田、長張、宮地)
蜂飛ぶや佳境の頁指しをり ―――川俣あけみ(長張、又木、宮地)
草餅を食むや画面に戦の火――― 川俣あけみ(川面、辻野、又木)
咲かぬ梅散る梅のある梅見かな ―――宮地麗子(柴田、松井)
玩具めく電車の渡る橋おぼろ ―――辻野多都子(川俣、長張)
日燦燦と斜りの息吹き菫草―――川面忠男(松井、柴田)
下萌や忘却語る友のいて―――辻野多都子(長張)
落椿急流下り渦に消ゆ ―――柴田香代子(松井)
薔薇の芽の放つ光の息づかひ――― 松井秋尚(柴田)
過去断ちて迷ふ間もなく梅盛り―――辻野多都子(松井)
農具置く谷戸の田んぼの斑雪かな――― 川面忠男(川俣)
白寿翁その剪定のリズミカル―――又木淳一(川俣)
節分草二輪の風に揺れ止まず――― 松井秋尚(宮地)
春浪のひたすら寄する能登の果て――― 辻野多都子(川面)
籠り居の母と娘の雛祭り ―――柴田香代子(川面)
幾年ぞ妻のハミング花ミモザ ―――又木淳一(辻野)
(文責・川面)
What’s JAZZへの招待 vol.60
What’s JAZZライブを楽しみにされている方々各位
・
好評のバイオリニスト、里見紀子さんを迎え、昼の部はクラシックジャズと映画音楽
夜の部はラテンと映画音楽をブルースカイーカルテットでお贈りします。 ご家族ご友人お誘いあわせの上お越し下さい。
・
2022年4月8日(金)
・昼の部 13:30開場 14:00開演
・夜の部 17:00開場 17:30開演
・出 演 里見 紀子(vn) 神村 晃司(p) 菅井 信行(b) スインギー奥田(ds)
・
・テーマ
昼の部 第1部:クラシック カルメンハバネラ 他 第2部:映画音楽 時の過ぎゆくままに 他
夜の部 第1部:ラテン エストレリ-タ 他 第2部:映画音楽 ムーンリバー 他
・
・場所:永山公民館5階 ベルブホール(永山駅徒歩5分)
・
・入場料 昼の部、夜の部それぞれ1,500円、完全入れ替え制。前売券発売期間は3月8日(火)10:00から4月7日(木)17:00迄。
ヴィータ7F多摩ボランティア市民活動支援センターで発売。 ※なるべくお釣りのないようにお願い致します。
当日券(残余ある時)は当日13時から受付で発売。
・
・定 員 72席(新型コロナの感染状況により、変更されることもあります。)
※当日はマスク着用、チケット半券に住所.氏名.電話番号を記入して下さい。
問い合わせ 山中康廣 y.y@abelia.ocn.ne.jp
第98回俳句同好会
多摩稲門会のサークル「俳句同好会」の月例会が2月18日午後、多摩市関戸の公民館和室で開かれた。メール参加を含め8人が5句ずつ投句、選句したが、冬の季語、春の季語が入り混じったのが2月の句会の特徴と言える。暦の上では立春が過ぎたが、寒さが戻る日が多いという季節感の表れだ。
8人の選句を発表した後、出席者4人の合評となった。2人が特選とした〈ひと畝に萌黄吹き出づ春浅き〉は早春の景がすっと浮かぶ句と評された。高得点句となった〈老松を伐りて寂しき年始〉は、〈老松を伐りて〉という措辞と〈年始〉の取り合わせが新鮮であり、〈寂しき〉という感情表現もこの句の場合は生きていると鑑賞された。〈吹かれゐる山盛りの絵馬梅明かり〉の絵馬は、合格祈願だけでなく母の病が回復する奇跡を祈るのもあったと作者が自解した。
当日の句会が第98回目だが、2か月後の4月に第100回目を迎える。
・
選句結果は以下の通り。カッコ内は選句者名(特選は◎で表記)
・
ひと畝に萌黄吹き出づ春浅き―――松井秋尚(長張◎、又木◎、川俣)
老松を伐りて寂しき年始―――辻野多都子(川俣◎、宮地、長張、柴田)
吹かれゐる山盛りの絵馬梅明かり―――川俣あけみ(松井◎、長張)
独り居の豆撒かぬ夜の幾度か―――宮地麗子(柴田◎、又木)
早咲きの花菜の風を吸ひにけり―――川面忠男(宮地◎)
この星に着地叶はぬ春の雪―――宮地麗子(川面◎)
走り根の走れる先や笹子鳴く―――川俣あけみ(川面、辻野、又木、松井、宮地)
寒紅梅塞げる胸の内に咲け―――宮地麗子(川俣、柴田、辻野、又木)
亡き人の吐息か梅の二三輪―――川俣あけみ(辻野、松井、宮地)
文字小さき古書肆(こしょし)の本や春寒し―――川俣あけみ(辻野、松井、宮地)
風抜ける道となりきる枯木立―――柴田香代子(川面、長張)
探梅や宝探しの子らと会う―――柴田香代子(川俣)
四肢伸ばし蒲団通して冬陽浴び―――長張紘一(辻野)
三寒と四温過ぐれば病癒ゆ―――柴田香代子(長張)
自転車のタイヤ押す指春隣―――又木淳一(川俣)
日を溜めて枝混み合へる濃紅梅―――松井秋尚(又木)
中尊寺雪の嵩抱く曲がり松―――辻野多都子(川面)
古民家に添ひ立つ梅の見映えよき―――川面忠男(柴田)
紅椿いざ鎌倉と馳せし道―――川俣あけみ(川面)
白銀の富士を真中に建国日―――又木淳一(松井)
水音のリズム戻りて寒明くる―――松井秋尚(柴田)
(文責・川面)
« Older Entries Newer Entries »