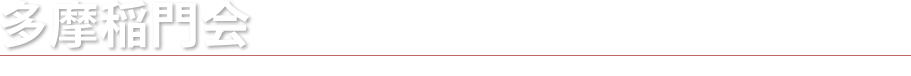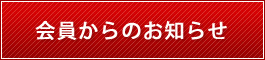Author Archive
2011.05(第123回) 大持山
2011年5月21日
奥武蔵の三山は、武甲山、武川岳、大持山と云われており、多摩市からも遠くに等間隔に望むことができる。大持山は一番左側に見えるが右側の武川岳には10年2月に男性3名で実施されている。
今日のメンバーは、川俣さん・前回と連続参加の辻野さん・上杉さん・金子さん・長張の5名となった。京王八王子駅からあわただしく10分後のJR八王子発八高線に乗り込み一同集合した。
東飯能駅前のバス停には大勢の学生も見られたが、名郷行きのバスに乗り込む客は少なく全員ゆったり座ることができた。下車した名郷は、晴れ渡った山奥の里山であった。しばらく車道を登って行く沢沿いには、キャンプ場が点在している。 
大場戸を過ぎ JFEミネラル鉱業と書いてあるセメント工場に着いた。その脇に白岩登山口がある。
セメント工場施設の近くの地下を採掘しているようである。登山道を登るに従って工場は眼下となり、次々と以前工場で働いていた人たちの住居施設の廃屋が現われる。工場から敷かれたトロッコの鉄道は、直ぐにトンネルの中に入る。採掘現場は山の裏側にあるらしい。山の上には白岩の岩壁が望める。
杉や檜林の中は日差しが遮られているが、急坂の山道に大汗をかいた。2・3日好天に恵まれ、埼玉県の天気予報は29℃と予報がでていた。休み休みゆっくり峠を目指す。やがて稜線の上の空が開け、尾根筋をわたる鈴の音を響かせる登山者の姿が見えてきた。
鳥首峠は大持山に続く主稜線にあり、道幅も広く峠の風の通る場所である。お昼には少し早いが、ここで昼食をとることになった。
5月の山は一番活力を感じる。日に日に緑の色が変わる。真夏になれば、山の緑は全体に色濃く同じような色合いになる。若葉の色の違いもあるかも知れないが、芽吹きの時期の差で、山肌の濃淡がパッチワークのような景色となり山笑う季節となるのだろう。
「アカヤシオが楽しめます」と案内に書いたが、私はまだ見たことがない。それらしき花は何箇所かに群生していたが、ミツバツツジかヤマツツジかはっきりしなかった。ネットで調べたが多分これがアカヤシオであろう。ウノタワはかってこの地は沼だった。そこに山の化身の鵜が住んでおり、猟師が殺してしまう。すると鵜もろとも沼が消えてしまった伝説があるらしい。少し遅れがちとなっているため、辻野さんにはここで金子さんとショートカットで山中に出るコースをとって貰いしばしの別れとなった。 
ここからは、3人のメンバーで大持山を目指す。川俣さんを先頭にピッチが上がり、ぐんぐん登って行く、追いつくのがやっとである。途中、武川岳から歩いている同年輩の30人ほどの団体に出会った。女性だけの団体と思ったが、最後の列に3人の男性が付いている。大変な女性パワーである。高い山低い山何処でも女性の方が多い気がする。
大持山分岐地点からは隣の武川岳が構え、伊豆ヶ岳の稜線も、少し霞んだなかで確認できた。分岐から山頂まで10分とあるが、先を急ぎ川俣さんは4分で、僕らも5分ほどで辿り着いた。 
山頂は狭く大勢の登山客が休んでいた。若者の一人に山頂のスナップ写真を頼んだ。間に川乗山ではないかと上杉さんが云っていたが、写真には白く写っているばかりである。山頂では別にハムを行なっている団体もおり、大声を上げている。早々に下山開始し先程の分岐点もそのまま通過し、かけ降りるように下って行く。 妻坂峠に着いた時は、バスの時間に十分間に合う時間となっていた。
 上手く行けば金子さん達と名郷のバス停で落ち合えるかも知れないと携帯で連絡しようとしたが、圏外と通じず車道に出てやっと通じることができた。結局、1本後のバスに乗り込み、東飯能駅で落ち合うことができた。八王子駅で下車し居酒屋の生ビールで乾いた喉を潤すことができた。今後の会の運営についての幾つかのご意見も拝聴することもできた。 長張記
上手く行けば金子さん達と名郷のバス停で落ち合えるかも知れないと携帯で連絡しようとしたが、圏外と通じず車道に出てやっと通じることができた。結局、1本後のバスに乗り込み、東飯能駅で落ち合うことができた。八王子駅で下車し居酒屋の生ビールで乾いた喉を潤すことができた。今後の会の運営についての幾つかのご意見も拝聴することもできた。 長張記
テニスコート・6月の予約ができました。
6月のテニスコートの予約ができましたのでお知らせいたします。
恵泉女学園の近く、一本杉公園内のコートで各日とも8:00~10:00です。
6月4日(土) Cコート
6月7日(火) C・Dコート
6月14日(火) C・Dコート
6月21日(火) C・Dコート
6月28日(火) C・Dコート です。
奮ってご参加ください。
新たに参加をご希望の方、メールをください。
お待ちしています。
担当窓口:依田敬一 yodak1jp@yahoo.co.jp
2011.04(第122回) 坪 山
2011年4月16日
昨年、ある山歩きの例会で川俣さんから坪山のイワウチワを是非とも見たいと云われていた。私もイワウチワは見たことがない。似たものでイワカガミがあるが、昨年白馬岳で鑑賞できた。イワウチワは花の色がそれより白いらしい。花の時期にタイミングが合えば良いのだが、今回のコースは、よほど花好きな人以外は訪れないそうである。 (さらに…)
2011.03(第 121回) 乞田川沿ハイキング
○午後、永山駅でハイキングのメンバーと待ち合わせる。川面、長張、橋本、浅井
氏。
○予定していた乞田川沿いは、サクラが未だ殆んど咲いていないので、川面氏の案内
で、貝取団地を抜けるコースを選び、木蓮、辛夷等の花を愛でながら、パルテノン多
摩へ行く。財布を忘れて戻った湯浅氏はこヽで合流。「商店事始」、「一ノ宮万平」
の二つの企画展を観る。「商店」の会場に担当の橋場氏がいたので、時間の許す限り
の解説を受け、「一ノ宮万平」を観て、16時近くになり駅前へ行く。これから自ら
の資料が出ている展覧会を観に行くという途中の寺沢史氏と遇々出遭う。立ち話で分
かれ、カリオン館の蕎麦屋で一献傾ける。
ゴルフクラブ
2010年12月10日於昭和の森ゴルフ場、3組
久し振りの優勝で嬉しさも一入。勝因は老いてパワーが無くなったので、基本に帰り、それを忠実に実行出来た事です。しかし、一緒にまわつた稲積さんはロングドライブを楽しんでいた。しかも77才の喜寿!
ゴルフは人それぞれの楽しみが出来るスポーツ、また皆でも楽しめるすばらしいスポーツです。
「早稲スポ・オッカケたい」へのお誘い
早慶戦(野球、ラグビー、サッカー、テニス等)・箱根駅伝を中心に熱く応援して、試合後の祝勝会で美酒を飲みながら大いに盛り上がる楽しい会です。
校友の皆さんは勿論の事、ご家族・ご友人大歓迎です。気軽にご参加下さい。
予定につきましては、その都度お知らせします。
テニスクラブ
毎週火曜日、朝8時~10時が主な練習日です。 場所は、一本杉公園の中にある市営のテニスコートです。 ほとんど2面取れますので十分練習ができます。稲垣コーチがじっくり指導してくれますので上達することうけあい。 お気軽にご参加ください。 お問合せは、 yodak1jp@yhoo.co.jp まで。
グルメの会
サークル紹介
うまい料理と酒を楽しみながら心おきなく語り合おう。グルメの会は談論風発がモットーだ。お店は味と値段に目配りし、世話役が探す。メンバーの注文を聞きながら下見もする。こってり風のファンが意外に多いが、さっぱり風も。 以上
2011.02(第120回) 丹沢三ノ塔
1月の東京の降水量は観測来最少だったそうだ。その反面裏日本の豪雪は厳しいものであった。日本列島の背骨の山脈が影響しているのであり、丹沢山塊も地域の気候に影響を及ぼして春夏秋冬自然の恵みを多くしているところである。
2月に入り東京でも雪が積もる日があり、多摩地区から望む丹沢の積雪した山塊は、山の冬の気配を出していた。丹沢の表尾根と呼ばれる尾根筋は、ヤビツ峠から主峰である塔の岳まで延びている。今日のコースは中間の三ノ塔で尾根から降りるコースとなるが、2004年7月に同じルートが開催されている。
秦野駅改札口前で8時少し過ぎに一同合流した。今日のメンバーは宇田川さん・上杉さん・金子さん・長張の4名となった。
秦野駅前のバス停には既に満員バスが停車していた。中央乗車口のステップに乗り込みそのまま1時間弱、ヤビツ峠の終点に着いた。ヤビツ峠は丹沢山地の南北をつなぐ峠であり、数少ない車道の一つであるが、雪が降って道が凍結すると、バスは途中までしか行かない。今日は凍結のため途中の蓑毛から峠までの1時間ほどの歩行を覚悟していたが、バスは順調に満員のまま峠に到着した。バスから降りた多くの人達は大山方面に向かっていた。
ヤビツ峠は、旧峠道を改修する際に矢櫃(矢を収める箱)が見つかったのでヤビツ峠という名前がついたそうだ。その矢櫃は戦国時代に武田軍と北条軍が戦いを交えた時のものだと伝えられている。
峠から車道を暫く下り、富士見橋から山道に9時半に入る。雪は積っているが歩き難いほどではない。スパッツや軽アイゼンの装備を必要とするほどではなさそうである。
登山道は良く整備されて二ノ塔に近づくと木の階段道となる。木道も雪に覆われている。右側には大山の姿が見え隠れしていたが、徐々に全容が見えてくる。
二ノ塔山頂は開けていた。雪は残っているがぬかるんではいない。そこに先客もいる。行く手には三ノ塔が構えている。その先は富士の雄姿があるはずだが見ることはできない。
山は風もなく鳥の鳴き声もなく静かであり、我々も男衆だけの寡黙な行進が続く。
三ノ塔頂には11時に辿り着いた。広い頂の展望は素晴らしいものと想像できるが、今日は生憎の雲がかかりパノラマは一級とは云えない。隣の裾を大きく南北に広げた大山は、頂付近にある通信施設や建物が見えていた。
東南部には相模湾が一望でき、江の島が雲で霞んだなかで薄っすらと見えている。三浦半島や伊豆半島も何とか確認することができる。表尾根の続きである塔ノ岳は、雲に遮られていたが、手前の幾つかのピークを辿る尾根道が続いていた。
頂上には無人小屋があった。薄暗い小屋の中の土間にはベンチがあり暖かく食事ができるが、外のベンチで食事をすることにした。
頂の広場にある樹木の小枝には霧氷が張り付き一面の花のようにも見える。近寄って見ると、細い梢の片方だけに硬く白い結晶が付着している。風向きが一定なのか、海側の湿った空気が冷えて付着したものかは解らなかった。
11時半から下山開始し、長い下りの最終に風の吊り橋を渡り、大倉バス停ターミナルに着いた。バス停広場には、地域の人達による農産物の青空市場が広がっていた。前々回、中川さんの陣馬山麓の柚子と梅干の土産は、奥方に大変褒められたことを思い出した。地域の産物には旨い物があることを知り、蕗のトウをみていたが、隣で上杉さんが持った南京豆は生であり炒ったものが隣にあると言われているのを聞き、私も一袋買ってみた。蕗のトウは早速天ぷらにして食べたが少し苦味が強かった。南京豆は大変旨くもっと買ってくれば良かったと後悔した。待機している1時38分発のバスに乗り、渋沢駅前のそば屋の生ビールで乾杯した。寒い中の山歩きであったが、冷たいビールは旨かった。 長張 記
2011.01(第119回) 払沢ノ滝・浅間嶺
今年最初の山歩きは払沢ノ滝に寄った後、浅間嶺のハイキングである。特に厳冬の中で凍りついた払沢ノ滝の姿は絶景と云われている。都民であれば一度は訪れてみたいスポットの一つである。一週間ほど前から朝晩の冷え込みは寝床を離れるのが躊躇するほど厳しくなっている。
今日のメンバーは中川さん・橋本さん・金子さん・長張の4名となった。9時40分武蔵五日市駅を降りた。バスの便はあまり良くない。タクシーに滝までの料金をただすと2500円と交渉の余地はなく、一同460円のバス行きで決定。59分発の払沢ノ滝入口行きのバスに乗り込んだ。バスはあまり込んではいなかった。大半のハイカーは途中で降り、終点まで行く者は少数であった。
今回のコースは前回2004年に湯浅さんと山岸さん2名で行なわれていることが記念文集に載っていた。その時は今回の逆のコースとなっている。
滝入口のバス停の前には豆腐のちとせ屋の店が構えている。その店の裏の道に入り滝へと向う。交通整理員の話では、全面凍結とはいかないが半分は凍っていると教えてくれた。
15分ほど進むと凍結した真っ白な滝が見えてきた。東京の滝の冬には凍ってしまう見事な景色である。滝の両端は凍結し中央の奥に水が落ちている。滝つぼも水の落ちる所以外は凍結している。体は歩いてきたせいかあまり寒さを感じさせない。暫く滝を鑑賞し記念写真を撮った後浅間嶺へのコースへ引き返した 。
。
テレビでも放映されていたが、元郵便局の建物を、そのまま内装を土産屋に改装利用しているところが紹介されていた。そこの親爺さんが、遥か先の天狗滝が見えると双眼鏡をセットして見せてくれた。私の肉眼では見えない白い筋が、はっきり流としてとらえていた。大岳山中腹に落ちる剥き出しの岩を滑る滝である。
時坂峠までの道は車道を主体に、脇の山道などを繰り返し単調な登り路を進む。峠の茶屋には12時に着いた。見晴の良い場所にベンチが置かれ。十数人のハイカーが食事をしている。
食事の場を求めなおも進むことにした。休憩所の峠の茶屋姉妹店みちこは無人で閉まっていた。前庭にある水車は凍り付いて廻っていない。傍らには植栽されたかシモバシラの氷の華が数箇所点在していた。ここも食事には適してはいなかった。更に進む。
尾根筋の起伏の少ない落葉が積もる場所で一同めいめい食事をとる。12時半である。風は予報ほど強くなく、さほど寒さを感じさせない。落葉樹の梢の向こう側に、大岳山・御前山・三頭山の奥多摩三山が目の前に広がっているが、暖かい季節になれば一面の緑で覆われる。
御前山の左奥には鷹ノ巣山も眺められる。
食事を済ませ先を急ぐ。幾人ものパーティーに出合うが、逆方向に向うルートの方が多いようだ。1時少し過ぎに浅間嶺に着いた。山頂というよりは、平坦な広い尾根の一部で何処がピークなのかはっきりしない。嶺とはこのような場所を云うらしい。カヤトの枯草が一面に広がり見通しの良い場所であった。富士の裾の一部が雲の間から見えていた。
後は1時間10分ほどで人里のバス停に着く。人里と書いてへんぼりと読む。一昔前には東京の秘境と云われた場所の一つである。何でこんな読みになるのか調べてみたら古墳時代に遡るようだ。「フンボル」が訛ったものではないかとの説がある。フンはモンゴル語の人間を意味し、ボルは新羅語の集落を意味する。この地域に、大陸からの渡来人系の集団が近畿地方から移住したと考えられている。人里バス停の裏には枝垂れ桜の冬芽が春を待っていた。
1時間も待ったバスは座ることができず、つり革に必死に掴りながら40分で武蔵五日市駅に着いた。立川駅で下車し「味工房」で新年の祝杯を挙げることができた。中川さんは90まで山登りを頑張りたいと。取敢えずは80までの目標にしたらと皆に諭されている。益々お元気で我々も見習いたい。 長張 記
« Older Entries Newer Entries »