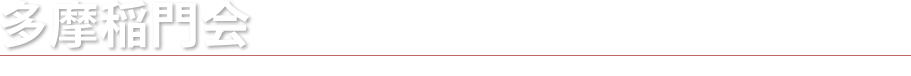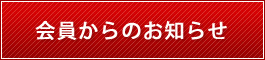Author Archive
2017.2(第163回)八王子市由木地区散策(小山内裏公園)
2017-02-19
 八王子市由木地区散策の4回目は、2月14日小山内裏公園散策コースである。参加者は、櫻井和子さん、中西摩可比さん、西村 弘さん、小林 勲さん、林 譲さん、長張6名で京王相模原線南大沢駅を1時に集合し出発した。櫻井さん中西さんは常連、西村さんの里山歩きは続いての参加、小林さんは久し振り、林さんも腰痛が治り久方ぶりとなった。
八王子市由木地区散策の4回目は、2月14日小山内裏公園散策コースである。参加者は、櫻井和子さん、中西摩可比さん、西村 弘さん、小林 勲さん、林 譲さん、長張6名で京王相模原線南大沢駅を1時に集合し出発した。櫻井さん中西さんは常連、西村さんの里山歩きは続いての参加、小林さんは久し振り、林さんも腰痛が治り久方ぶりとなった。
 風もなく陽だまりは暖かい。駅前広場から首都大学方面に進み、ニュータウン通りを跨ぎ直ぐに左折して広い通りに並行した遊歩道を歩く。
風もなく陽だまりは暖かい。駅前広場から首都大学方面に進み、ニュータウン通りを跨ぎ直ぐに左折して広い通りに並行した遊歩道を歩く。
遊歩道は幅広く贅沢に続き、やがて戸建て住宅やお洒落な設計の中層マンションなどが現れる。東京郊外に統一的に開発されたモダンな住宅地の景観を感じる。
 平日のせいか子供の遊ぶ姿や行き交う人の姿も少ない。住宅から遊歩道には直接行き来する事はできないのも、遊歩道は隔離されている感じがする。
平日のせいか子供の遊ぶ姿や行き交う人の姿も少ない。住宅から遊歩道には直接行き来する事はできないのも、遊歩道は隔離されている感じがする。
遊歩道は大栗川の支流である大田川の左岸に並行している。谷戸の面影はないが、一番低い所にニュータウン通りや京王線が走り、やがて丘陵のトンネルに入って行く。遊歩道は緩やかに真っすぐ上る公園内の道のようである。
 遊歩道に隣接する南大沢緑地に入ると、昔この辺りにあったマイマイ井戸を模した渦巻き状の溝があり、中央に丸い窪みを作り雨水が流れ込むようになっている。底は深くはないが水気はある。谷戸の側面は急傾斜となり、上部には平らな平地が広がり、マンションの建物が梢を通して今の時期には見渡せるが、葉が茂れば隠れていまい、広い空間に緑の林が続くようになる。崖からは所々湧水が流れるようである。
遊歩道に隣接する南大沢緑地に入ると、昔この辺りにあったマイマイ井戸を模した渦巻き状の溝があり、中央に丸い窪みを作り雨水が流れ込むようになっている。底は深くはないが水気はある。谷戸の側面は急傾斜となり、上部には平らな平地が広がり、マンションの建物が梢を通して今の時期には見渡せるが、葉が茂れば隠れていまい、広い空間に緑の林が続くようになる。崖からは所々湧水が流れるようである。
南大沢緑地を過ぎると桜並木は終わり、小山内裏公園に入る。急坂を上ると戦車道路のある尾根の台地に出る。
 戦車道は、旧陸軍が当時の戦車の性能試験や操縦技術向上のために、丘陵の林を拓き造られた。戦後防衛庁からURが受け継ぎ都市住宅開発のための土砂運搬に利用され、現在は公園として維持されている。
戦車道は、旧陸軍が当時の戦車の性能試験や操縦技術向上のために、丘陵の林を拓き造られた。戦後防衛庁からURが受け継ぎ都市住宅開発のための土砂運搬に利用され、現在は公園として維持されている。
桜並木はまだ固い蕾であったが、開花している樹を見つけ全員の集合写真を撮る。
 今の時期に咲く桜は、河津桜と思うが濃いピンクの大きな花の特徴の何本かの低木が道の脇に並んでいた。カメラを向ける人もいる。
今の時期に咲く桜は、河津桜と思うが濃いピンクの大きな花の特徴の何本かの低木が道の脇に並んでいた。カメラを向ける人もいる。
戦車道は地元の人達らのジョギングコースにもなっているようで、かなり高齢の方の姿が見受けられ驚いた。
戦車道は尾根に沿ってくねってはいるが、平坦な道である。尾根の下は京王線・ニュータウン通りのトンネルが走っている。大栗川の支流太田川の源流の右岸に入り、出発点である南大沢駅に向かう。
 途中の展望台から、丹沢山塊が雪雲の下に間近に見渡せる。一番左側の高い山が大山である。多摩丘陵の南端からの眺めは、手前の山襞で隠れることがなく、大山は大きく裾野を広げている。相模平野はこの大山を巻きながら裏側まで続いている。
途中の展望台から、丹沢山塊が雪雲の下に間近に見渡せる。一番左側の高い山が大山である。多摩丘陵の南端からの眺めは、手前の山襞で隠れることがなく、大山は大きく裾野を広げている。相模平野はこの大山を巻きながら裏側まで続いている。
 南大沢駅に向かう途中寄り道をして、大平公園による。そこは小さな山全体の公園で山頂には休憩所の古民家風の建物が建っていた。駅から駅へ、今日のコースは一度も車道に立つことのない散策であった。
南大沢駅に向かう途中寄り道をして、大平公園による。そこは小さな山全体の公園で山頂には休憩所の古民家風の建物が建っていた。駅から駅へ、今日のコースは一度も車道に立つことのない散策であった。
4時丁度南大沢駅に着いた。駅近くの居酒屋「隠れ庵・忍屋」で懇親会。整備された公園のような南大沢の街並みや、林の中の散策に皆満足されたようである。来月3月は中西さんが90才を迎えられる。4回続けた由木地区の散策は一先ず終了し、次回の例会は中西さんの卒寿のお祝いを兼ねて、高尾登山A・Bコースをそれぞれ歩き、Cコースは京王クラブに集り、懇親会を予定したいと思っている。
長張 記
「中村草田男を語る」歴史に遊ぶ会
2017-02-12
第37回「歴史に遊ぶ会」は2月10日午後、多摩市関戸の京王クラブで<「萬緑」廃刊を機に中村草田男を語る>という演題となった。<降る雪や明治は遠くなりにけり>という句で知られる草田男はまた<萬緑の中や吾子の歯生え初むる>も代表句とされる。その名を冠にした俳誌「萬緑」が3月に終刊となることから草田男も歴史になったというわけである。
まず筆者が雑誌「俳句」の昨年11月号に載った口絵写真を話題にした。<「萬緑」800号記念「成就の宴」という見出し。写真に<「いつも父草田男と論争していた(金子)兜太さんが今日、隣に座ってくださっていることが嬉しい」と、弓子氏>というキャプション。中村弓子氏(元お茶の水女子大教授)は草田男の3女だ。そこで「草田男と金子兜太の論争」について言及した。続いて<山本健吉との「軽み」論争>、日野草城との<ミヤコ・ホテル論争>などを話題にした。
<ミヤコ・ホテル論争>は草城がフィクションとしながら新婚初夜の模様を俳句にし、室生犀星が評価したことについて草田男が「あるものは、草城という人から発する堪えざるほどの悪臭ばかりである」などと痛烈に批判。草城も「瞋れるドン・キホーテ」として反論、応酬しあった。後に草城が死病の床についた時、草田男は妻(直子)の勧めで草城を見舞った。
<妻抱かな春晝の砂利踏みて帰る>、<終生まぶしきもの女人ぞと泉奏づ>という句に表れているように草田男は女性と愛を讃歌する俳人だった。
草田男の俳句について「説明省略で難解」「写実より象徴」「言葉の二重性」「蕪村ではなく芭蕉に通じる」などについても語った。昭和21年に草田男が「萬緑」を創刊した際に参加した高弟、香西照雄の著「中村草田男」をテキストにした。
また草田男が郷里・松山の縁で高浜虚子の門人になったことや虚子主宰のホトトギスを去るまでの経緯についても話題にした。
「歴史に遊ぶ会」だけでなく同じ稲門会のサークル「俳句同好会」にも声をかけ10人が参加した。例会後は京王クラブのラウンジで9人が懇親した。参加者の一人から「刺激的だった」という感想を聞いた。
また筆者が知らないことについても参加者から教えていただいた。元会長の中川邦雄氏は赤城さかえという俳人が戦後の俳壇の論争に深く関わったと言った。中川氏は赤城と定期的に会う関係だったという。筆者は今後、勉強を続けて次は俳句同好会の番外として「中村草田男を語る」の続編をもとうと思った。
その日は有志が3次会まで楽しんだ。京王クラブから京王線聖蹟桜ケ丘駅に行く途中にカラオケスナック「麗」があり、カラオケサークル「いねの会」の例会場になっている。「麗」に立ち寄り、何曲か歌った。「歴史に遊ぶ会」、「俳句同好会」、「いねの会」を一緒に行った日ともなった。
(文責・川面)
第12回南大沢碁会
2017-02-12
囲碁の会では2月2日(木)、第12回南大沢碁会を行った。
参加者(敬称略)
多摩・・・人見哲爾九段、上杉雅好七段、西村幸一四段、梶本進司四段、井石道彦四段、平松和巳三段
女性ゲスト・・・吉田京二段、児島春代二段(稲門ママ)
稲城・・・豊島澄雄五段
八王子・・・中西公一四段(調布)
日野・・・大高秀樹初段
今回1月下旬に会場確保できず、2月2日に行った。寒い季節で風邪・インフルエンザによる直前キャンセルもあり、参加者は11名にとどまった。
対局に先駆け昨年12月に逝去された城所睦雄さんのご冥福を祈り黙祷。
2回戦を終わって連勝者は、人見九段(多摩)、上杉七段(多摩)、井石四段(多摩)の3名。3回戦は得点順に、上杉七段対人見九段、井石四段対平松三段(ここまで1勝1敗+136点の4番手)。人見九段、井石四段が勝利し、この両者で決勝対局。井石四段が18目差で人見九段を制し4連勝、本碁会ではV2となった。
優勝:井石四段(多摩)、4勝0敗+358点
準優勝:中西四段(八王子)、3勝1敗+302点
3位:西村四段(多摩)、3勝1敗+290点
BB賞:梶本四段(多摩)、1勝3敗+175点
1回戦組み合わせは抽選だが、人見九段は大高初段との対局となり最大ハンデ差(8子)となった。大高初段は慎重に打ち健闘したが惜しくも盤面ジゴだった。大高初段は3回戦でも井石四段に1目差(負け)と勝敗以上に健闘振りが目立った。
午後5時から会場近くの”まるかみ水産・まぐろ人”で打ち上げ懇親会、参加者は6名。優勝の井石四段、平松三段(両者とも昇段リーチ)の話を中心に6月のオール早稲田での昇段話などで弾んだ。なお、多摩稲門会チームとしてもAクラス優勝が目標!
なお、小生、個人的事情もあり(6月ごろ郷里に引っ越す予定)多摩稲門会囲碁の会世話人を今回で引退。次期世話人は平松さん、井石さんにお願いしています。4月に京王クラブで碁会を行いたいと平松さんからお話あり。
(西村)
What’s Jazz vol.44
2017-02-05
今回は久しぶりに、実力派のマリア・エヴァさんのヴォーカルと貫田重夫さんのsax を楽しむことができます。
満席が予想されますので、ご希望の方は早めにチケット確保をお願いします。
よろしくお願いいたします。
山中 康廣
多摩稲門会 「第63回文化フォーラム・新年賀詞交歓会」
2017-02-05
平成29年1月28日(土)14時から18時、多摩市永山の多摩永山情報教育センター内にある展望サロン「美膳」で「多摩稲門会『第63回文化フォーラム・新年賀詞交歓会』」が開催された。
第63回文化フォーラムは、鎌倉稲門会の会員である坂(ばん)麗(れい)水(すい)氏の薩摩琵琶の演奏と多摩稲門会幹事浪久圭司氏の朗読とのコラボ演奏会であった。琵琶の音色を初めて生で聴く人がほとんどで、開演前から“未知との遭遇”のような雰囲気が感じられた。
長張紘一幹事長の開会の辞、依田敬一会長の年始挨拶に続き、尾ノ井光昭文化フォーラム担当副会長が本日の文化フォーラムの内容と出演者のプロフィールを紹介した。拍手の中で、薩摩琵琶奏者坂麗水氏が登場した。
 最初の演目の『扇の的』は平家物語に出てくる那須与一の話だが、その背景の解説のあと薩摩琵琶演奏が始まった。その演奏と謡いは時には激しく時には心に染み入り、聴衆はじっと聴き入った。約20分の演奏は聴衆を別世界に引き込んでいた。圧巻の演奏であった。
最初の演目の『扇の的』は平家物語に出てくる那須与一の話だが、その背景の解説のあと薩摩琵琶演奏が始まった。その演奏と謡いは時には激しく時には心に染み入り、聴衆はじっと聴き入った。約20分の演奏は聴衆を別世界に引き込んでいた。圧巻の演奏であった。
 次は浪久圭司氏の朗読『菊の典侍』。司馬遼太郎作「花妖譚」第7話の物語で、朗々とした語りに聴衆が同化した。坂氏の琵琶演奏が途中途中に入り、朗読全体を一層重厚なものにした。
次は浪久圭司氏の朗読『菊の典侍』。司馬遼太郎作「花妖譚」第7話の物語で、朗々とした語りに聴衆が同化した。坂氏の琵琶演奏が途中途中に入り、朗読全体を一層重厚なものにした。
最後は坂氏の琵琶演奏に戻り、『四条畷』という「太平記」の時代の話を、演奏と謡いで集まった70名超の観衆に感銘と余韻を与えた。ちょうど除夜の鐘がゴーンと打ち鳴らされてから余韻がしばらく残るように、演奏の最後に“ジャラーン”と、撥(ばち)で弦を弾き終わった後の静寂、そしてある種の余韻が耳と心に残響のように残った感動の演奏会だった。その後坂氏との質疑応答があった。その中で、坂氏は昨年もフランスで薩摩琵琶の演奏会を開いたのだが、坂氏によると、ヨーロッパでは近年テロなどで民衆の心がひどくすさんできているので、“心が癒される”日本古来の琵琶演奏が見直されているということであった。日本の禅も海外で普及されており、日本的な心の精神文化が世界各国で受け入れられているのだろう。尾ノ井光昭副会長の閉会の辞で、第63回文化フォーラムを終了した。
引き続き第2部の新年賀詞交歓会が、尾ノ井光昭副会長の開会の辞、藤井國男副会長の乾杯音頭で始まり、益田幸兒幹事の司会・進行で進められた。来賓の鎌倉稲門会稲田明子副会長、多摩三田会澤雄二氏のご祝辞のあと、なごやかな歓談の時間となった。菊池恵子会員から坂麗水氏に花束が贈呈された。新春の邦楽の催しにふさわしく着物姿の女性もいて華やかな懇親会となった。酒を酌み交わし、広く親交を深め、和気あいあいとした楽しい新年会となった。会場の展望サロン「美膳」から見る多摩の夕景は美しく、参加者もしばし見とれていた。たぶん夕景を見ながら薩摩琵琶が奏でた諸行無常の余韻にひたっていたのだろう。稲垣友三副幹事長の閉会の挨拶、野宇進幹事の力強いエールの発声のあと、参加者が全員で肩を組んで校歌「都の西北」を斉唱し、閉宴となった。
文化フォーラム及び新年賀詞交歓会参加者(敬称略):
浅井隆夫 新井正子 新井真澄 井上一良 稲垣友三 遠藤千尋 尾ノ井光昭 加来健一郎 河合一郎 川面忠男 川俣あけみ 神田康子 菊池恵子 菊沢光江 小林 勲 子幡嘉之 櫻井和子 佐藤達雄 白井昭男 田島重光 近沢市子 辻野多都子 寺沢 史 中川邦雄 長張紘一 浪久圭司 西村幸一 西村 弘 野宇 進 平松和己 福田 宏 福田かほる 藤井國男 星野英仁 益田幸兒 又木淳一 松本靖子 山中康廣 湯浅芳衞 吉川啓次郎 吉田 浩 吉田富康 依田敬一 (以上43名)その他お客様多数
(稲垣友三 記)
グルメの会 2017/01/25
2017-01-29
「トランプを肴にスペインの味とワインにひたる」
63回目のグルメの会は25日、京王永山駅近くのスペイン料理店「ウン・べシート」で開いた。10種類以上のパエリア(スペイン風炊き込みご飯)が食べられる人気店で、男性10人、女性ひとりの計11人が参加。米国でトランプ新大統領就任、日本では稀勢の里が19年ぶりの日本出身横綱に決まった直後とあって、のっけから談論風発のにぎやかさとなった。
まずは浪久圭司さんが「トランプにかきまわされそうな1年。でも地に足をつけ、みなさん健康で」と音頭をとり、生ビールで乾杯。恒例のショートスピーチで西村弘さんは「ヒトラーとトランプは全く同じと感じている」と強い警戒感を示した。
山中康廣さんは稀勢の里の横綱昇進を率直に歓び、「横綱になれば自分だけでなく、日本人みんなが喜ぶとお父さんは言っていた」と感動の大きさを表現した。
料理はまず、スペイン風オムレツ、エスカルゴときのこの煮込みなど3種の前菜からスタート、ニンジンドレッシングのサラダなどをはさんで、メイン料理が二つ登場。きのこのバルサニコソースをかけた豚のロース肉と、アサリと白ワインのバターソースをかけた鯛のソテーを各人が取り分けた。
湯浅芳衛さんは、築地の後継市場に予定されている豊洲について「見直し大賛成。小池百合子東京都知事はがんばって欲しい」と石原慎太郎元都知事を追及する構えを支持し、河合一郎さんも同調した。
最後にお店推薦のパエリアが2種類運ばれた。「魚介のサフラン風」と「どっさりアサリ」のいずれもが「本場の味」(スペイン旅行経験者)だけあって、スペイン産のハウスワインとの取り合わせが絶妙だった。
(世話役 浅井隆夫)
「山歩きの会」 2月例会のご案内
2017-01-22
2月例会は里山散策コース4回目、小山内裏公園コースです。多摩丘陵の主稜線上に位置しており、多摩川水系と境川水系の分水嶺でもあります。戦前、戦車の試走場として開発され、丘陵の尾根を幅広い歩道(戦車道)が続きます。道は直線ではなく戦車の試験操作のためくねくねと曲がりくねり、丘の上の散歩道としては快適な時間を過ごすことができます。時間があれば大平公園にもよります。ご検討の上、体調にあわせてご参加をお待ちします。
1.日時 2月14日(火)
2.予定コース Bコース
南大沢駅から、小山内裏公園に入り南大沢駅に戻ります。 (歩行5.7キロメートル)
○集合 (13:00)京王相模原線南大沢駅改札口前広場
徒歩開始 南大沢駅→内裏谷戸→桜並木→小山内裏公園→大平公園→南大沢駅へ
○持ち物・装備
・ハイキングスタイルで(長袖シャツ・ウインドヤッケ・ジャンパー等)ご参加下さい。飲み物、間食等は各自のお好みで。雨具(折り畳み傘)、
○雨天の場合は中止します。迷うような場合は、メールか電話でお尋ね下さい。
参加ご希望の方は、長張(tel 042-337-1792、e-mail nagahari@ttv.ne.jp)にまでにお知らせ下さい。
「いねの会」の1月例会は新年会
2017-01-22
 カラオケサークル「いねの会」の1月例会は原則通り第3火曜日の17日正午から多摩市関戸のいつもの会場「麗」で行われた(写真)。新年初の月例会なので幹事たちが相談し、最寄りの旭鮨聖蹟桜ヶ丘駅店の鮨を昼食のメーンにした。参加者が16人と多かったので、店のママが前日、店に注文し、当日はママと2人の幹事が旭鮨から麗まで運んだ。
カラオケサークル「いねの会」の1月例会は原則通り第3火曜日の17日正午から多摩市関戸のいつもの会場「麗」で行われた(写真)。新年初の月例会なので幹事たちが相談し、最寄りの旭鮨聖蹟桜ヶ丘駅店の鮨を昼食のメーンにした。参加者が16人と多かったので、店のママが前日、店に注文し、当日はママと2人の幹事が旭鮨から麗まで運んだ。
会員からシャンパンの差し入れがあり、青木会長の挨拶に続く音頭で乾杯した。いつも歌い出しは12時半頃からだが、当日は参加者が多いことから15分ほど早めた。そうして貸し切タイムが終わる5時までに各人が4曲を歌うことができた。
この日、早稲田大学野球部の往年の名選手、亀田 健さんが昨年末の忘年会を兼ねた例会に続いて参加した。松山出身の亀田さんは忘年会にご当地ソングの「夜明けのブルース」を歌ったが、新年会でも選曲した。その際、「待ってました」の掛け声。〽ここは松山 二番丁の店♪と歌えば、何人かが〽松山、松山♪と囃し、雰囲気を盛り上げた。
亀田さんは稲門会のサークル「早稲田スポーツ・オッカケたい長」の湯浅芳衛さんが誘ったようだ。その湯浅さんは選曲の中に青森県民謡の「八戸小唄」を入れた。〽唄に夜明けた鴎の港♪と歌い、これまた正月らしい気分に盛り上げた。
飲んで、歌って、おしゃべりするのが好きな人たちの集いだ。各テーブルでおしゃべりの輪ができた。筆者は亀田さんの席に行き、早大の往年の名投手、末吉俊信について訊ねた。亀田さんのお話で昭和22年から東京6大学で44勝をあげ、プロの毎日オリオンズに入団、退団後は毎日新聞の記者になったと知った。
来る1月28日午後2時からの多摩稲門会新春文化フォーラムで薩摩琵琶が演奏されることも話題になった。奏者は鎌倉稲門会の坂麗水さん、多摩稲門会の浪久圭司さんの朗読とのコラボである。またサークル「歴史に遊ぶ会」と「俳句同好会」が一緒に「中村草田男を語る会」を持つことも話題になった。「降る雪や明治は遠くなり」の句で知られる草田男が創刊した俳誌「萬緑」が3月号で廃刊になるからだ。このように「いねの会」はカラオケサークであるとともに稲門会員が情報を交流する場にもなっている。
(文責・川面)
俳句同好会・新年初句会
2017-01-22
俳句同好会は1月20日の初句会が第37回目、サークル活動の4年目に入った。当日は9人が各自3句ずつ投句、5句ずつ選句した。
<杣人の踏みにし古道寒葵>は2人が特選、3人が並選とし過半数5人が選ぶ高点句となった。「一読して光景が目に映る。寒葵という季語が生きている」などと評された。作者が稲門会のサークル「山歩きの会」に参加して見た実景で山歩きが吟行になったのだ。<父の書の淑気うなじに肩に寄す>は5人が選句、並選ながら高点句となった。
句会後、4人が最寄りの店で余韻にひたりつつミニ新年会を行った。
当日の選句は以下の通り。カッコ内は選句者、特選句は◎で表記した。
杣人の踏みにし古道寒葵 又木淳一(川俣◎、長張◎、辻野、中川、平松)
半額の河豚鍋せせり二合半(こなから)に 川面忠男(中川◎、萩尾◎、又木)
怪我癒えし妻とこの道春近し 川面忠男(宮地◎、長張、又木)
元朝の晴れの極みに雀跳ぬ 川俣あけみ(川面◎、萩尾)
元日の夕べ自販機煌々と 宮地麗子(辻野◎、萩尾)
氏神や欅の高き初社 川面忠男(平松◎)
二日はや開く手擦れの「方丈記」 川俣あけみ(又木◎)
父の書の淑気うなじに肩に寄す 川俣あけみ(川面、中川、長張、又木、宮地)
一歩ごと膝痛みおり冬の蠅 中川邦雄(辻野、長張、萩尾、宮地)
七草の椀の中にも小宇宙 平松和己(川面、中川、長張)
からからと葉も走り出で年移る 長張紘一(川俣、中川、平松)
車椅子の友現るる冬至かな 長張紘一(川面、宮地)
初富士や降りしホームを間違えて 宮地麗子(川又、平松)
米田先生を偲びて
短日の恩師の棺の薄明り 辻野多都子(川面、川俣)
初日拝む老いてますます日本人 萩尾昇平(川俣、又木)
新玉の真澄の空に白い月 平松和己(辻野)
故郷の忘じ難きや老の春 又木淳一(平松)
故郷離れ後ろめたきは床暖房 萩尾昇平(辻野)
認知症の友の忠告寒日向 中川邦雄(宮地)
晴天も年神様のお計らい 長張紘一(萩尾)
(文責・川面)
2017.1(第162回)八王子市由木地区散策(府中カントリークラブ一周)
2017-01-15
 八王子市由木地区散策の3回目は、1月10日、府中カントリークラブを一周するコースである。参加者は、櫻井和子さん、中西摩可比さん、中川邦雄さん、西村弘さん、浅井隆夫さん、又木淳一さん、長張7名で京王線多摩センター駅を1時に出発した。
八王子市由木地区散策の3回目は、1月10日、府中カントリークラブを一周するコースである。参加者は、櫻井和子さん、中西摩可比さん、中川邦雄さん、西村弘さん、浅井隆夫さん、又木淳一さん、長張7名で京王線多摩センター駅を1時に出発した。
正月三が日は天候に恵まれ暖かい日が続いた。今週に入り、寒の戻りの反動は僕らの体には応える。
 多摩ニュータウン通りを少し西に向い、直ぐに愛宕丘陵の坂を上る。山王下緑地斜面の階段の落ち葉を、地元のボランティアの人たちが清掃をしていた。
多摩ニュータウン通りを少し西に向い、直ぐに愛宕丘陵の坂を上る。山王下緑地斜面の階段の落ち葉を、地元のボランティアの人たちが清掃をしていた。
丘陵に入ると下の街並みとは違う景色が続く。広い空間の中に研究所、野菜工場、住宅マンション、看護学校、介護施設、大塚西公園、東中野公園が続く。
 大塚西公園にある梅の古木は、一斉に赤い花を咲かせていた。風に乗りほのかな香りが漂っているが、風邪気味の私には香りは感じられなかった。
大塚西公園にある梅の古木は、一斉に赤い花を咲かせていた。風に乗りほのかな香りが漂っているが、風邪気味の私には香りは感じられなかった。
大塚西公園から東中野公園へ向かう。
愛宕通りを跨ぐ塗料の禿げた古い歩道橋を渡ると東中野公園に入る。
 園内の池には、アオサギ、シラサギ、カルガモの群れが泳いでいる。風の無い陽だまりは暖かい。
園内の池には、アオサギ、シラサギ、カルガモの群れが泳いでいる。風の無い陽だまりは暖かい。
公園を出て下って行くと、多摩ニュータウン通りの松が谷トンネルの上にでた。トンネルの上は広い遊歩道が続いている。府中カントリークラブに沿って、高い金網が設置されており、ゴルフ場の様子も見ることができる。トンネルは終わりニュウタウン通りの歩道にでる。鹿島丘陵を通過するトンネルは乞田川流域から大栗川流域と変わる。松が谷トンネル西の交差点から秋葉台公園に入る。
 秋葉台公園の北側は開けている。京王線がこの下を走っている。秋葉台公園の中央には階段ミラミッドのような石組みの高台の設備がある。上からの眺めは良く、大栗川の向こうの丘陵に中央大学や明星大学の校舎が間近に、そして緑の丘陵が続いている。
秋葉台公園の北側は開けている。京王線がこの下を走っている。秋葉台公園の中央には階段ミラミッドのような石組みの高台の設備がある。上からの眺めは良く、大栗川の向こうの丘陵に中央大学や明星大学の校舎が間近に、そして緑の丘陵が続いている。